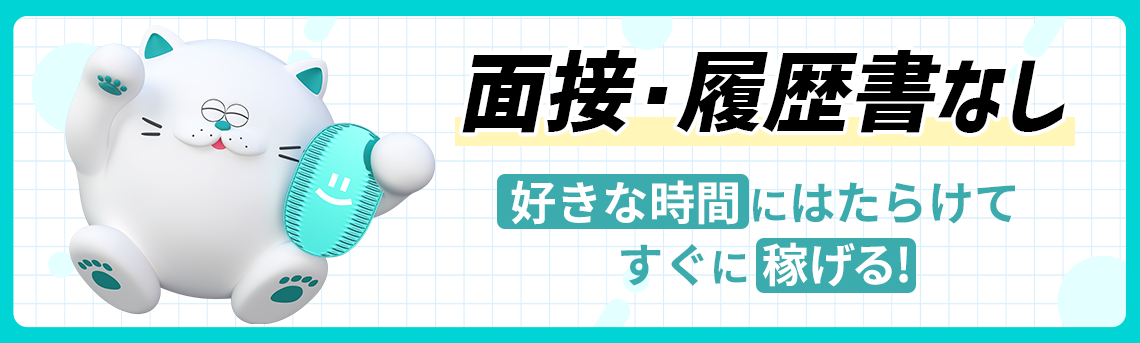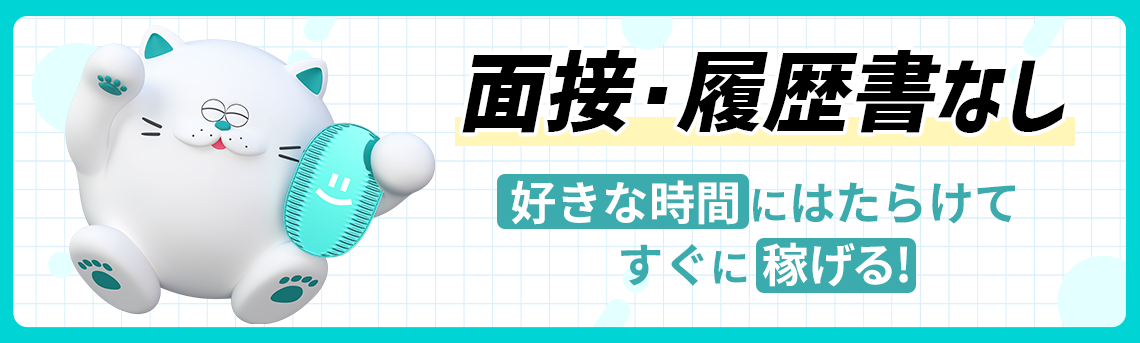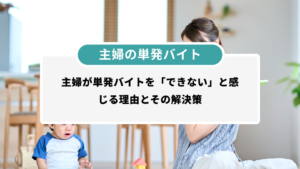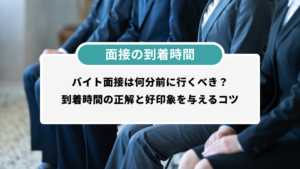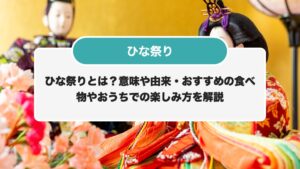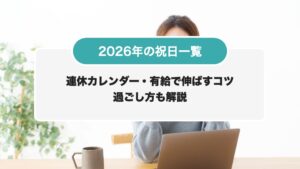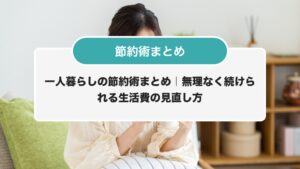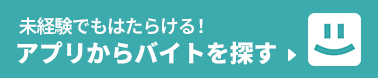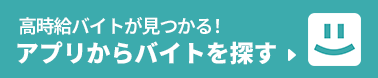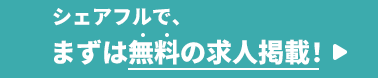【2026年最新版】主婦年金廃止で何が変わる?制度変更の背景と影響をわかりやすく解説
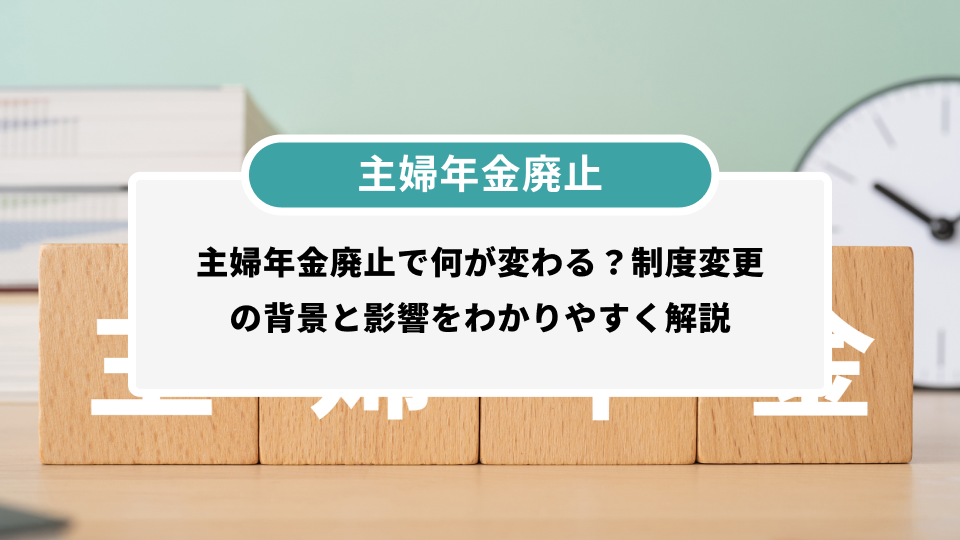
「主婦年金が廃止されるらしい」というニュース、最近よく耳にします。
でも、制度が変わると言われても「具体的にどう変わるの?」「自分には関係あるの?」と、いまいちピンとこない方も多いでしょう。
この記事では、「主婦年金」と呼ばれる第3号被保険者制度について、基礎から廃止の背景・今後のスケジュールまでわかりやすく解説します。さらに、「専業主婦や扶養内パート勤務の方への影響」「新しいはたらき方の選択肢」「今からできる準備」まで具体的にお伝えします。
「主婦(・主夫)年金=第3号被保険者」とは?制度の基本

第3号被保険者制度は、会社員や公務員の配偶者で20歳以上60歳未満の人が対象。加入していても保険料は自分で払わず、夫(または妻)の厚生年金保険料に含まれた形で負担されます。
この制度によって、たとえ長年専業主婦であっても、条件を満たせば老齢基礎年金を満額受け取れる仕組みになっています。
例:40年間ずっと第3号の場合、年間約83万円(月約6.9万円)の基礎年金がもらえる(2025年度満額)
加給年金・遺族年金・老齢基礎年金との関係性
加給年金:夫が厚生年金を受給し始めたとき、条件によって妻に加算されるお金
遺族年金:夫が亡くなった際に受け取れる年金
老齢基礎年金:全国民共通で支給される年金
第3号廃止は、これらの受給条件や金額にも将来的に影響する可能性があります。
専業主婦はなぜ保険料を払わなくてよかったのか?制度廃止の背景は?

専業主婦は、会社員など第2号被保険者の「被扶養配偶者」として国民年金の第3号被保険者に該当すると、本人が保険料を直接納めなくても加入扱いになります。保険料は配偶者の厚生年金保険料と税金(国庫負担)で賄われるため、要件を満たす専業主婦は“自己負担0円”でも年金の加入期間としてカウントされてきました。
制度廃止の背景:高齢化・財源不足・社会構造の変化
日本は少子高齢化が急速に進み、年金を支える現役世代の人数が減っています。その一方で、年金を受け取る高齢者は増え続け、年金財源に大きな負担がかかっています。
さらに、共働き世帯が当たり前になった今、「専業主婦だけが保険料を払わずに年金を受け取れるのは不公平では?」という意見が強まりました。こうした人口構造の変化(高齢化)・財源不足・社会の意識変化が重なり、第3号被保険者制度(主婦年金)を見直す動きが加速しています。
「3号被保険者制度の限界」とは?
- 少子高齢化で年金財源が逼迫
- 共働き世帯が主流になり「公平性」への疑問が増加
- 国際的にも「配偶者だけ保険料免除」という制度は珍しい
こうした背景から、「専業主婦にも保険料を自己負担してもらうべき」という議論が進み、制度見直しが現実味を帯びています。
2025年以降、私たちに起こることとは?
現時点では、今後専業主婦も国民年金保険料(年額約20万円)を自己負担する可能性が高いとされています。
家計にとっては年間20万円の支出増。10年続けば、200万円の負担増です。
主婦年金廃止は「いつから」?変更スケジュールと影響範囲

制度改正のスケジュール(想定)
- 2025年:法案提出・審議開始
- 2026〜2027年:段階的導入(例:半額負担から開始)
- 2028年以降:完全廃止・新制度へ移行
※今のところ「主婦年金(=国民年金の第3号被保険者)」の“廃止時期”を示した政府の公式スケジュールや発表は出ていません。
専業主婦・パートタイマー・扶養内勤務者への影響比較
専業主婦
これまで保険料を払わずに国民年金に加入できていましたが、制度廃止後は自分で保険料を負担する必要が出てきます。年間約20万円の負担増が見込まれます。
パートタイマー
勤務時間や収入によっては、扶養から外れて社会保険料を自己負担する可能性があります。場合によっては手取り額が減ることもあります。
扶養内勤務者
扶養の条件や収入上限が変わる可能性があり、はたらく時間や収入の調整が必要になるケースがあります。
年金の代わりに何が必要になる?自助努力の必要性
主婦年金が廃止されれば、これまで国が担っていた一部の保障を、自分自身で補う必要が出てきます。
そのためには、「自助努力」が欠かせません。
具体的には、
資産形成:iDeCoやつみたてNISAを活用して、老後資金を長期的に積み立てる
就労による収入確保:扶養内・扶養外を問わず、安定的な収入源を持つ
支出の見直し:固定費削減や生活スタイルの調整で家計に余裕を持たせる
特に、収入と資産の両面から将来の生活を支える準備をしておくことで、制度変更による影響を最小限に抑えることができます。
年金制度が変わると「はたらき方」はどう変わる?

扶養の壁(年収103万/130万/150万)の再考
保険料を払うなら「扶養内にこだわらずもっとはたらいて稼ぐ」という選択も出てきます。
たとえば年収103万円→150万円にすると、社会保険料を払っても手取りが増えるケースがあります。
👇「扶養内で副業できる収入は?」気になる方はこちらの記事をチェック!
扶養内で副業できる収入はいくらまで?注意点を徹底解説
社会保険加入の条件緩和と企業側の対応
週20時間未満でも加入できる方向で議論されており、短時間勤務でも保障を得やすくなる可能性があります。対象者の増加に伴い企業の保険料負担が拡大するため、シフト設計や雇用区分の見直し、勤怠・人事システムの改修が必要になります。適用基準や手続きの周知、労働時間の管理ルール整備、費用試算の早期実施など、実務面での準備を前倒しで進めることが望まれます。
「週20時間」から始める新しいはたらき方
1日4時間×週5日など、自分のペースで長期的に続けられるはたらき方が増えると予想されます。学業・育児・介護、副業や学び直しと両立しやすく、生活設計の柔軟性も高まります。短時間でも社会保険が付く雇用が広がれば、安心感を保ちながら段階的に労働時間を伸縮する“スライド型”の働き方も選びやすくなります。
「扶養から外れる」のは損?得?年金・手取りを徹底比較

収入別シミュレーション:手取り・年金・保険料の変化
主婦年金廃止後は、収入額によって手取りや将来の年金額、保険料の負担が大きく変わります。以下は扶養内・扶養外それぞれのパターン例です。あくまで概算となりますが、自身に近いものを参考にしてみてください。
年収120万円(扶養内)
社会保険料の自己負担はなし。所得税や住民税もほぼかからず、手取りはほぼ年収と同額の約120万円。ただし将来の年金は基礎年金のみ(約83万円/年)。
年収160万円(扶養外)
社会保険料の自己負担が年間約22万円発生し、手取りは約138万円。ただし、厚生年金に加入することで将来の年金額は基礎年金+厚生年金(約100〜110万円/年)に増える可能性あり。
年収200万円(フルタイムに近い勤務)
社会保険料負担は年間約27万円、所得税・住民税も発生し、手取りは約160万円前後。それでも厚生年金期間が長くなるため、将来の年金額は120万円以上/年になる見込み。
このように、短期的には扶養内のほうが手取りは多く見えますが、長期的に考えると厚生年金の上乗せがある扶養外勤務のほうが老後の収入面で有利になるケースもあります。
| 年収 | 扶養区分 | 社会保険料負担 | 手取り額(概算) | 将来の年金額(概算/年) |
| 120万円 | 扶養内 | なし | 約120万円 | 約83万円(基礎年金のみ) |
| 160万円 | 扶養外 | 約22万円 | 約138万円 | 約100〜110万円 |
| 200万円 | 扶養外 | 約27万円 | 約160万円 | 約120万円以上 |
加給年金がなくなると年収はいくら下がる?
月1万5,000円の加給年金がなくなると、年間18万円の減収。10年で180万円の差になります。
専業主婦 vs 週3パート勤務 vs フルタイムで将来もらえる年金額の違い
将来の年金額は、はたらき方や加入期間によって大きく変わります。以下は2025年度水準をもとにした概算例です(40年間の加入を想定)。
| はたらき方 | 勤務時間(週) | 年金種別 | 年金額(40年間加入想定/年) |
| 専業主婦 | 0時間 | 基礎年金のみ | 約83万円 |
| 週3パート勤務 | 12~18時間 (1日4〜6時間想定) | 基礎年金+一部厚生年金 | 約100万円 |
| フルタイム | 週40時間 (1日8時間) | 基礎年金+厚生年金 | 約160万円 |
将来が不安なら、「今から備える」ための3つのステップ

ステップ①:情報をキャッチアップする(信頼できる情報源とは)
SNSや噂だけに頼らず、厚生労働省HPや公的年金相談窓口で正確な情報を入手することが重要です。あわせて「施行日・対象範囲・経過措置」の3点を必ず確認し、自治体や年金機構のリーフレット/Q&A、ねんきんネットで自分の記録も照合すると安心です。
ステップ②:家計とライフプランの見直し
年間20万円の保険料負担を想定して、家計を調整したり、老後資金の目標額も再設定することが重要です。手取りの変化(社会保険料+税)を月次で把握し、固定費や積立NISA・iDeCoの拠出配分を調整。「加入する/しない」「勤務時間を増減」の複数シナリオで1年・5年のキャッシュフローを試算すると判断がぶれにくくなります。。
ステップ③:短時間・柔軟にはたらける環境を見つける
扶養の条件や勤務時間の成約にとらわれず、自分のペースではたらける環境を探しましょう。例えば、スキマ時間ではたらけるスキマバイトアプリ「シェアフル」では、履歴書不要で即日勤務できる案件もあり、家庭と両立しやすいはたらき方が見つかります。
主婦・パート向け 社会保険と年金のよくある質問(Q&A)
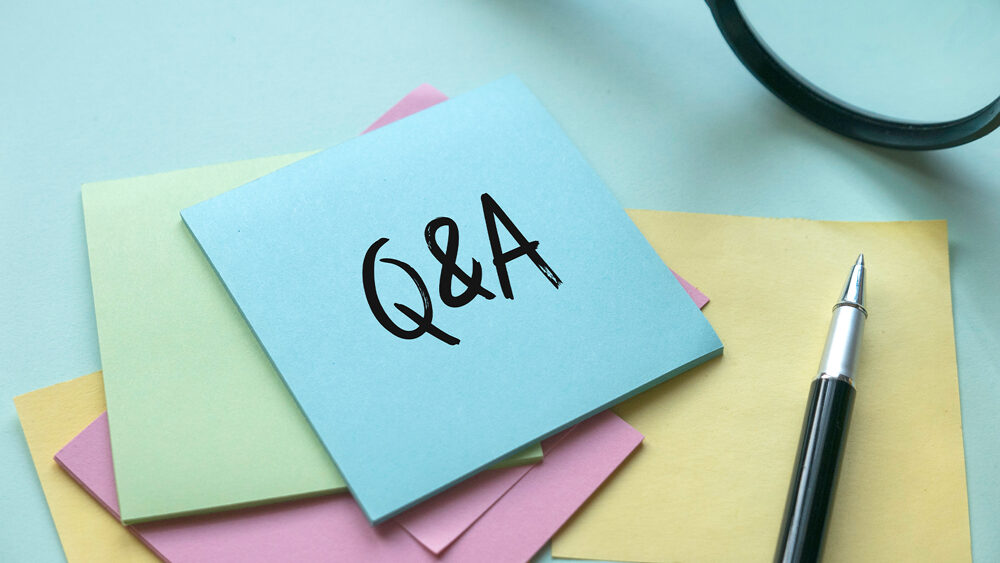
【まとめ】主婦年金廃止は「終わり」ではなく「始まり」|今すぐできる行動を!

主婦年金の廃止は、多くの家庭にとって大きな変化です。突然の制度変更に不安を感じるのは自然なことですが、それは同時に、自分らしいはたらき方や資産づくりを見直すきっかけにもなります。
今からできることはたくさんあります。たとえば、「少しずつ収入を増やすはたらき方を試す」「iDeCoやNISAで老後資金を積み立てる」「家計の固定費を見直す」など、小さな行動から始められます。これらは将来の安心感を育てる種になります。
大切なのは、「変わること」に備えること。情報を正しくキャッチし、自分の立場や家計に合わせた選択を重ねていけば、制度が変わっても生活の安定は守れます。
主婦年金廃止は終わりではなく、これからの人生をより主体的にデザインできる新しいスタートだと考えて、今できる一歩を踏み出してみませんか。