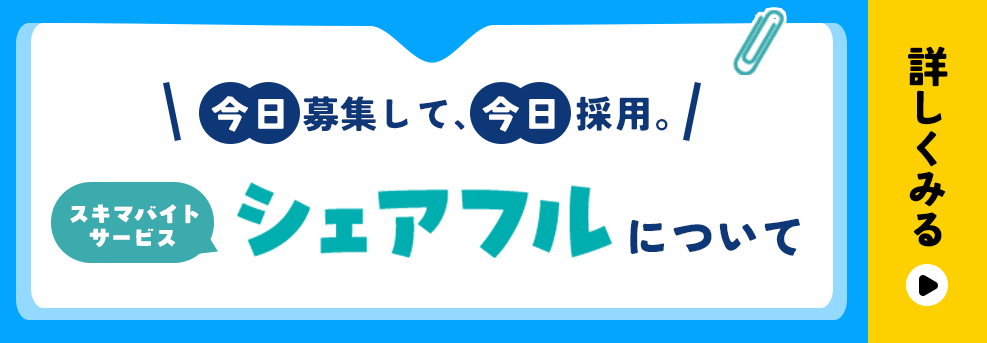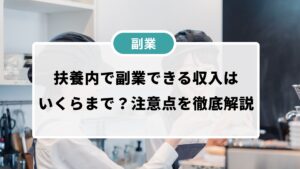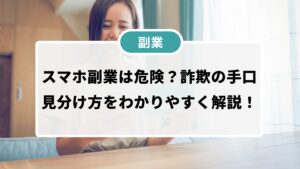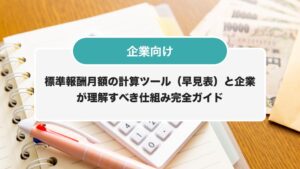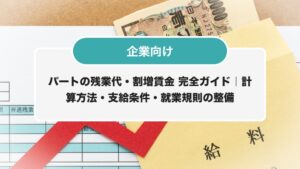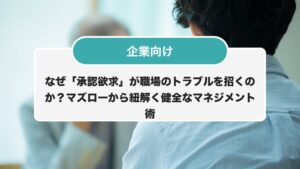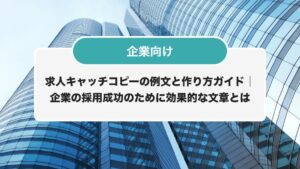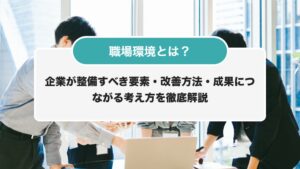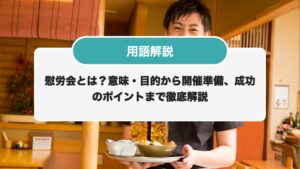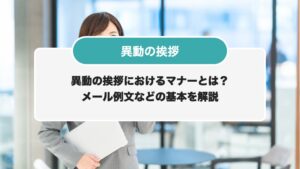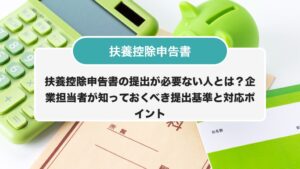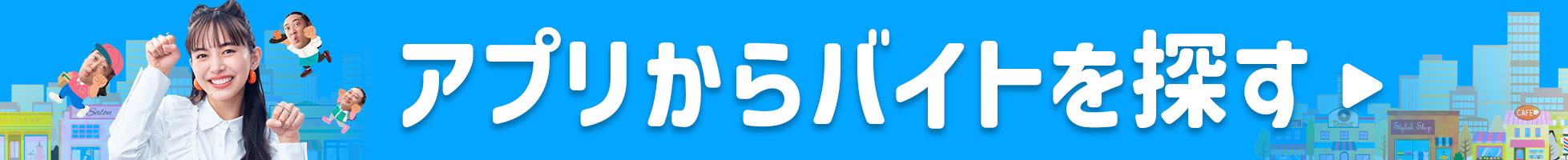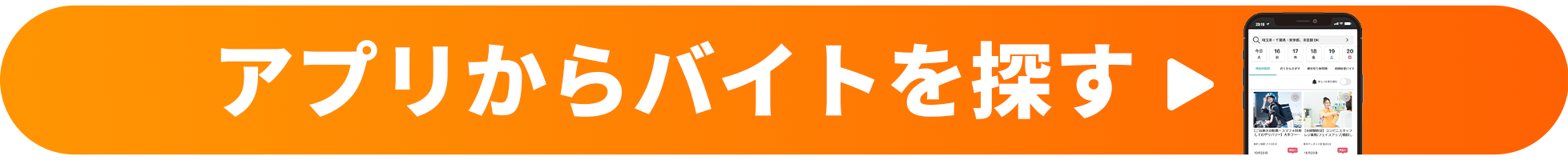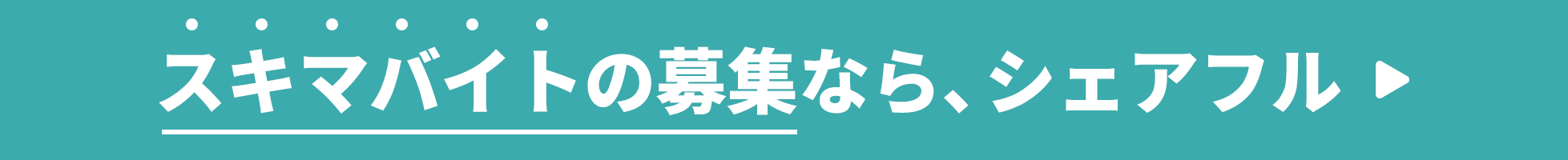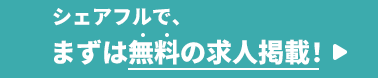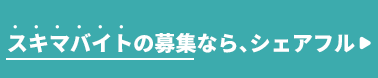アルバイト・パートの採用コストとは?採用単価の平均や削減方法を解説
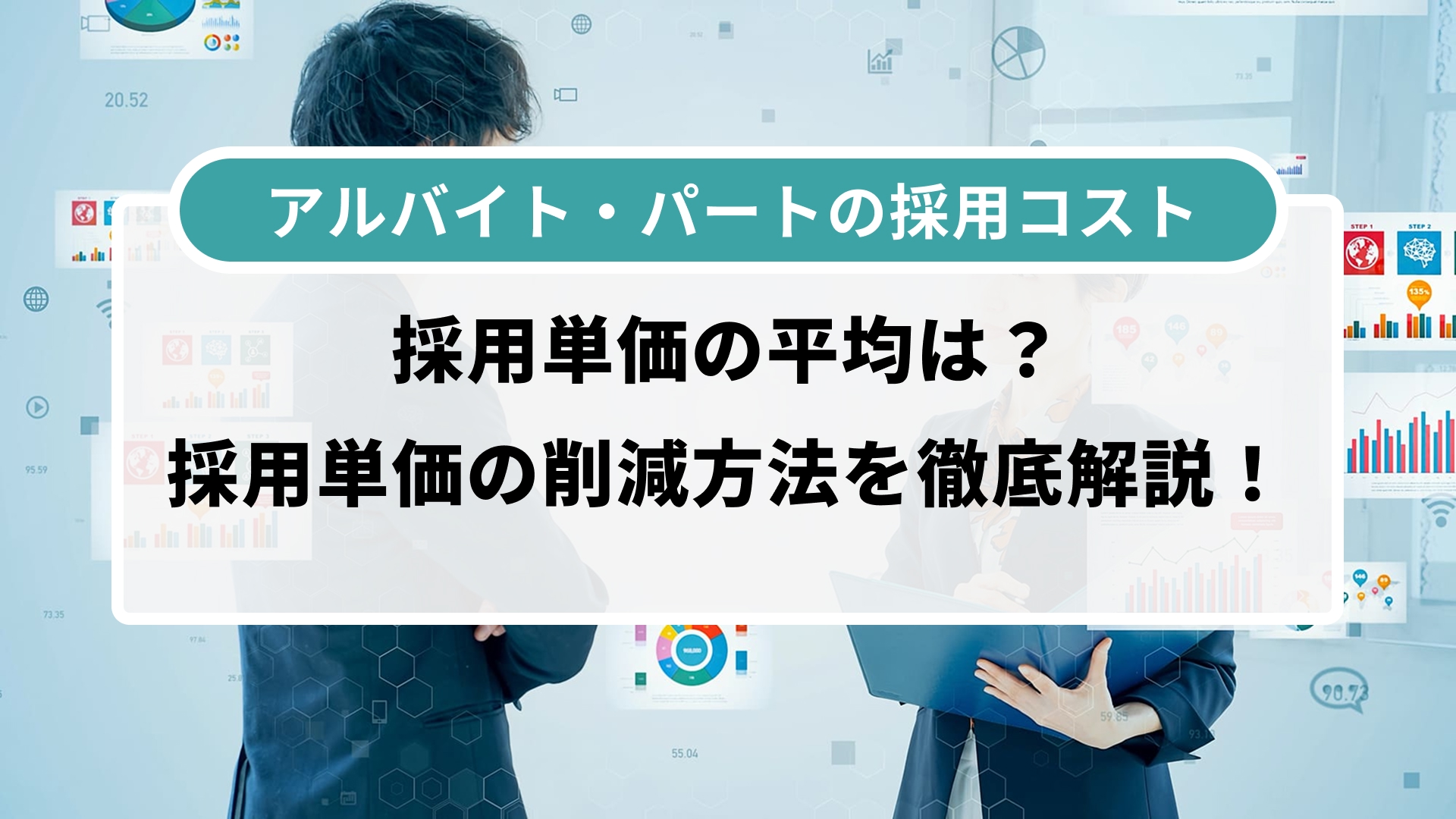
「アルバイトの採用コストは、どのくらいかけるべきか」「他社はアルバイトにどのくらいのコストをかけているのか」と気になる方もいるのではないでしょうか。
採用予算がある限り、採用コストを把握してコントロールすることは重要です。
この記事では、採用コストや採用単価の違い、その計算方法や、アルバイトの平均採用単価を解説します。また、アルバイトの採用コストを軽減する方法も紹介しているので、ぜひ参考にしてみてください。
アルバイトの採用コストとは?

アルバイトの採用コストとは、採用活動全体においてかかった費用であり、内部コストと外部コストから成り立っています。
採用の内部コストとは、採用担当者や面接官、入社に当たっての労務担当者の人件費など、自社内で発生する費用です。また、応募者が面接に来るための交通費や採用時に支給する入社お祝い金などは、内部コストになります。
採用の外部コストとは、求人広告の掲載費、人材紹介会社への紹介料、採用イベントへの出展費用など、自社外に支払う費用です。採用代行に採用業務や支援を依頼した場合にかかる費用も外部コストになります。
アルバイトの採用単価との違い
アルバイトの採用コストと採用単価は異なります。アルバイトの採用単価は、一人採用するのにかかった費用です。
採用コストを採用人数で割って採用単価を出すことで、採用活動のパフォーマンスをはかることができます。なるべく少ない採用コストで多くの人数を採用できれば、採用単価は下がり、効率的に採用ができているといえるでしょう。
採用コストと採用単価の計算方法
採用コスト=(内部コスト)+(外部コスト)
採用単価=(採用コスト)/(採用人数)
たとえば、アルバイト10人採用するのに採用の内部コストが100万円、外部コストが50万円だった場合は、以下となります。
採用コスト=100+50=150万円
採用単価=150/10=15万円
アルバイトの平均採用単価
株式会社ツナグ・ソリューションズが2012年に実施した調査によると、アルバイトの平均採用単価は52,000 円でした。
しかし、このデータは10年以上前のデータであるため、近年の物価高の影響や採用手法の広がりなどから現在のアルバイトの平均採用単価と乖離がある可能性があります。
一番重要なのは、自社内での採用コストや採用単価を把握して、いかに効率よく優秀な人材を確保するか、試行錯誤することでしょう。
【出典】アルバイト・パートに関する求人広告の応募状況と求職者の意識調査,株式会社ツナグ・ソリューションズ
アルバイトの採用単価の推移
株式会社マイナビが運営する「マイナビバイト」が行った調査では、2019〜2022
年の採用単価は以下のように推移しています。
| アルバイト1名あたりの採用単価 | |
|---|---|
| 2019年 | 6.4万円 |
| 2020年 | 5.2万円 |
| 2021年 | 6.0万円 |
| 2022年 | 7.0万円 |
【出典】マイナビバイト通信|採用活動に関する最新調査データについて
2019年から2020年は、コロナの影響で採用活動が大幅に減少したことで、採用単価が下がっていると考えられます。その後は緩やかに採用単価も戻っており、2022年にはコロナ前の採用単価を超えています。
高齢化や人口減少によって労働力不足が加速すると、採用の難易度も上がり採用単価も高くなることが予想されます。
業種別のアルバイトの採用難易度
業種ごとの最新のアルバイトの採用単価のデータがないため、業種別にアルバイトの有効求人倍率をまとめます。
有効求人倍率とは、有効求人件数を有効求職者数で割ったものです。有効求人倍率が1を超えると求人のほうが多く、人材不足を示しています。有効求人倍率が高いほど採用難易度が高く、採用コストがかかる可能性が高いと考えられるでしょう。
| 業種 | アルバイト・パートの有効求人倍率 |
|---|---|
| 介護サービス業 | 4.53 |
| 接客・給仕業 | 3.70 |
| 保健医療サービス業 | 3.29 |
| 飲食調理業 | 2.71 |
| 販売業 | 1.85 |
| 清掃業 | 1.51 |
| 生産工程業 | 1.25 |
| 建設・採掘(建築・土木・測量技術者を除く) | 0.97 |
| 事務業 | 0.52 |
【出典】一般職業紹介状況(令和7年1月分)について |厚生労働省 参考統計表より作成
アルバイトの採用コストを削減する方法

最後に、アルバイトの採用コストを削減する方法を紹介します。効率的な採用活動を行うことで、採用コストが下がり、同時に採用単価も下げることにつながります。
アルバイトの採用媒体を見直す
アルバイトの求人サイトは、さまざまな種類があり、料金形態やターゲットが異なります。料金形態は、掲載料金がかかるものや成果報酬型のもの、追加料金を払って広告枠に掲載してもらうものなどがあります。
また学生をターゲットにしている場合、大学や専門学校には低コストで求人広告が出せる媒体もあります。
採用コストを下げるには、ターゲットによって媒体を使い分けたり、複数の媒体を比較して費用対効果の高いものに絞ったりするのが有効でしょう。
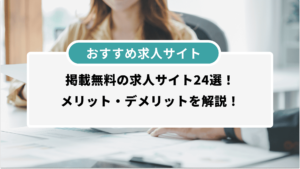
リファラル採用や知人紹介を強化する
アルバイトの採用には、リファラル採用(社員または取引先からの紹介を介した採用)や知人紹介も有効です。紹介元には謝礼を支払いますが、求人広告費と比較すると費用も手間も抑えられるでしょう。
紹介元が社内の信頼のおける人であれば、紹介先の人も一般募集よりは、一定の信頼がおけるでしょう。また、紹介元から職場の雰囲気や仕事内容を聞いた上で応募意志が取れるため、応募後のミスマッチも少なくなります。
SNSや自社HPを活用する
近年はSNSの種類や用途も広がり、SNSを活用した採用(ソーシャルリクルーティング)を行う企業も増えています。Facebook(フェイスブック)やLinkedIn(リンクトイン)では、企業アカウントを作成して求人を掲載することができます。TikTokやInstagram、X(旧Twitter)で認知を獲得したり、ブランディングを行ったりする企業も少なくありません。
また自社HPに採用ページを作ったり、採用専用のHPを運用することも選択肢の1つです。SNSやHPの運用には、スキルや工数も必要なので、社内のリソースを考えて検討しましょう。
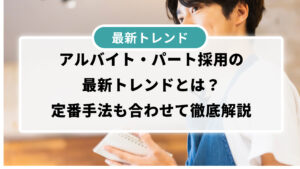
採用代行に依頼する
社内にアルバイト採用のリソースやノウハウがない場合は、採用代行業者に依頼するのも選択肢の1つです。採用代行業者が、採用計画や媒体選定、母集団形成、選考、実績の振り返りなどの採用活動を代行してくれます。
採用代行業者によって費用はさまざまで、依頼する業務や求人の採用難易度によっても費用は変わります。ただし、採用代行業者は採用のスペシャリストなので、うまく利用すれば高い費用対効果も得られるでしょう。
既存のアルバイトの定着率を上げる
離職率の高さが人材不足の原因の場合、既存のアルバイトの定着率を上げることも重要です。そもそも辞める人がいなければ、欠員補充で採用する必要はなくなります。
アルバイトの定着率を上げるには、辞める原因を解消しなくてはいけません。たとえば、シフトの希望を通しやすくしたり、時給を上げたり、まかない制度(食事補助)を導入するなどが挙げられます。
一時的にはコストがかかるかもしれませんが、長期ではたらいてくれれば採用や教育のコストが削減できるでしょう。
社員やアルバイトのスキル教育をする
今まで一部の人にしかできなかった仕事をできる人が増えることで、人材不足が解消される可能性があります。すなわち、既存社員やアルバイトのスキルが上がれば、必要だった採用人数を減らし、採用要件を緩和したりできます。
具体的には、スキル教育をして仕事ができる人を増やす、マニュアルを整え業務効率化をはかる、といった方法が有効です。
採用コストを削減しながらアルバイトを活用しよう
アルバイトの採用コストは、内部コストと外部コストから成り、採用にかかったすべての費用を指します。その採用コストを採用人数で割ったものが、採用単価です。
採用単価は、採用業務を効率的に行う上で重要な指標となります。採用コストならびに採用単価を下げるために、試行錯誤して、良い人材を活用していきましょう。