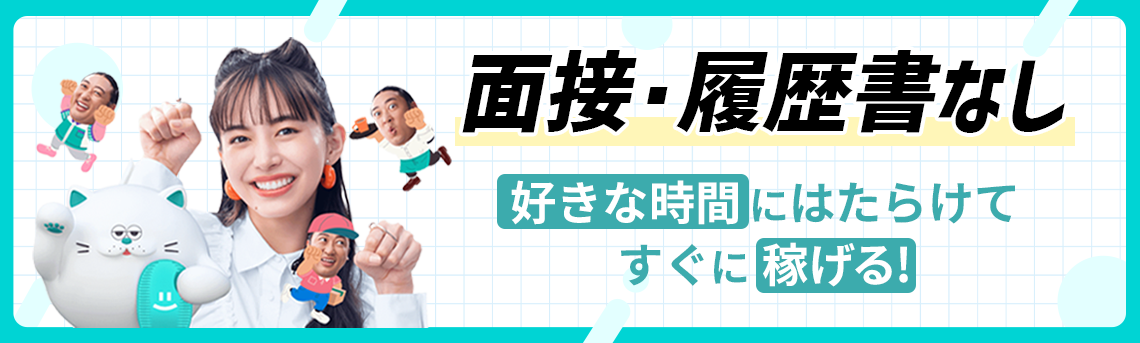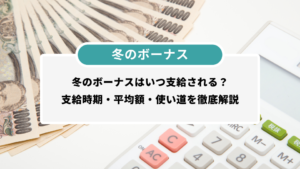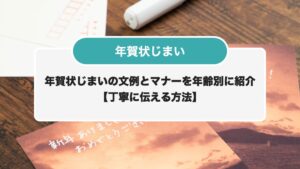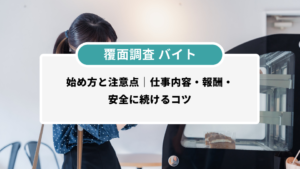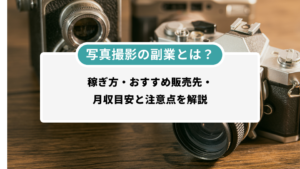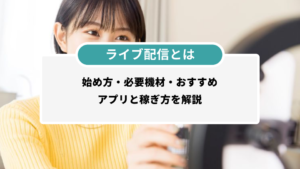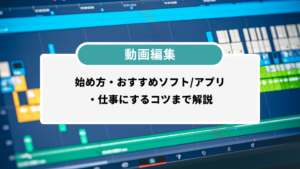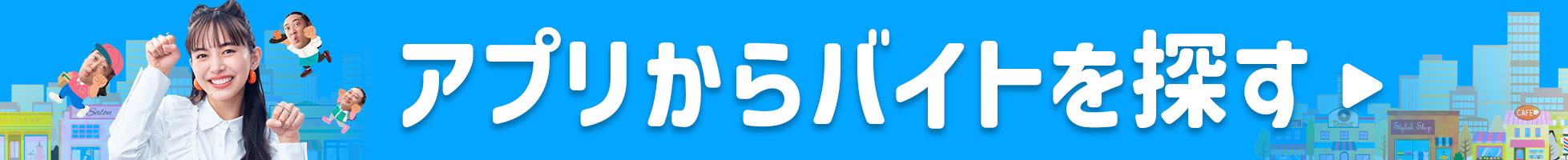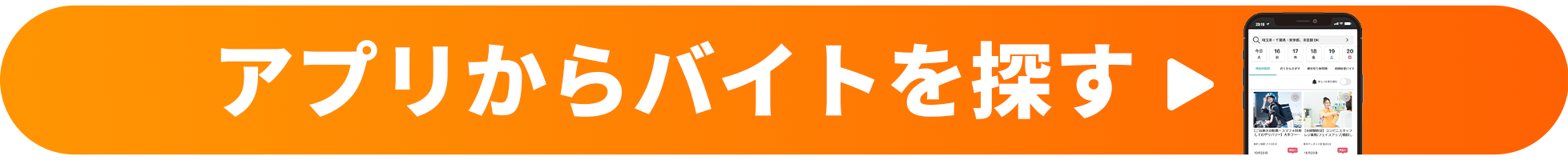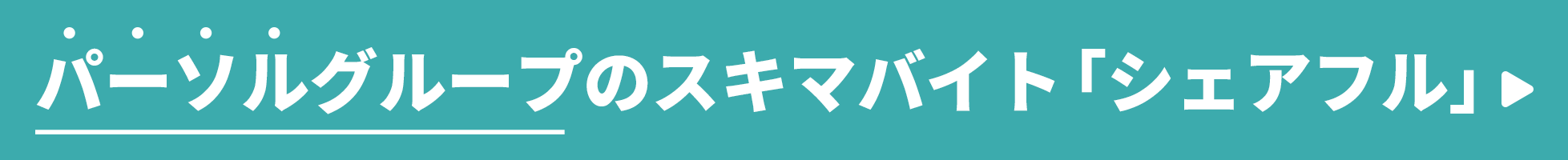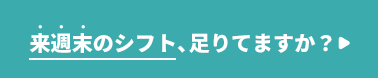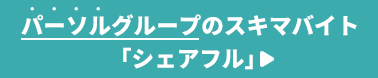【2025年最新版】ボーナスの平均はいくら?|年代・業種・企業規模別に徹底比較
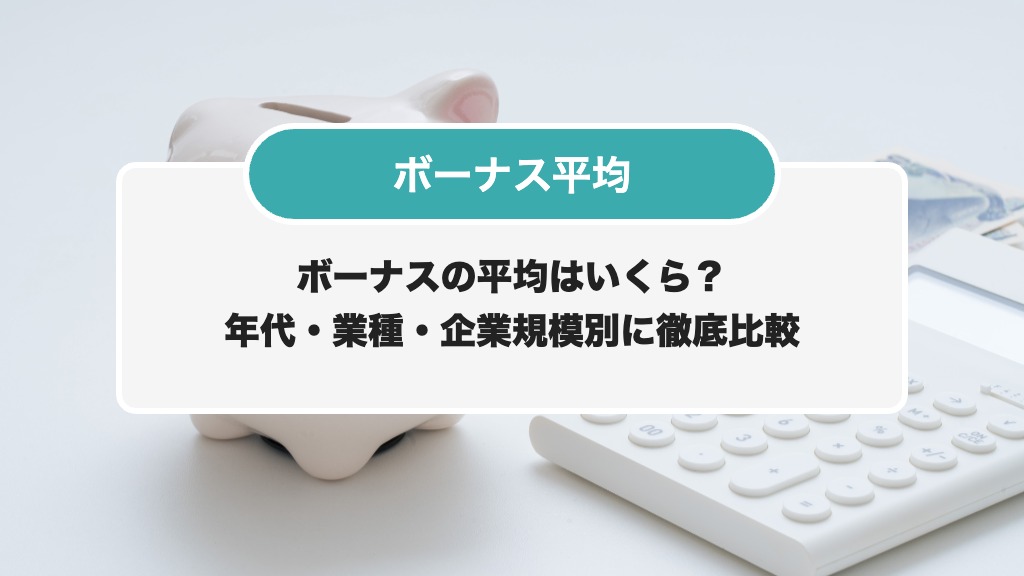
「自分のボーナスって平均より多いのかな?」
「業種や年齢でどのくらい差があるんだろう?」
そんな疑問を持つ人は多いはずです。
2025年現在、日本のボーナス事情は“業種間・企業規模間で二極化”が進んでいると言われています。
大企業では過去最高水準の支給が続く傾向にある一方、中小企業では物価高や人件費の影響で減少傾向とも言われています。
この記事では、最新データ(経団連・厚労省など)をもとに、年代別・業種別・企業規模別のリアルな平均額を解説します。
また、ボーナスが少ない・もらえないときにできる対策も紹介します。
ボーナスの平均とは?基礎をおさらい

ボーナス(賞与)の定義
ボーナスとは、企業が従業員に支払う「業績連動型の特別報酬」のことです。基本給とは異なり、企業の業績・個人の成果・在籍期間などによって金額が変動します。
夏(6〜7月)・冬(12月)が一般的な支給時期で、会社によっては年1回または業績連動型の特別賞与のみの場合もあります。
支給額は「業績・勤続年数・会社規模」で変わる
ボーナス額を左右する主な要素は3つあります。
- 企業業績:黒字企業ほど支給率が高くなる傾向
- 勤続年数:在籍年数が長いほど支給額が増える
- 会社規模:大企業は1人当たり支給額が中小企業の約2倍という傾向があるデータも
つまり、「同じ年齢・職種」でも勤務先によって大きく差が出るのが特徴です。
ボーナス平均の算出方法
経団連や厚労省のデータでは、ボーナスは「支給総額÷対象従業員数」で算出されています。
なお、正社員のみを対象とするケースが多く、非正規雇用は含まれない場合があります。
【最新データ】2025年のボーナス平均額|年代・業種・企業規模別まとめ(参考値)

ここからは、経団連の「2025年夏季賞与・一時金大手企業集計」および厚生労働省「賃金構造基本統計調査」などをもとに、年代・業種・企業規模ごとのボーナス平均額を見ていきましょう。
民間企業全体の平均支給額
2025年の民間企業における平均ボーナス支給額は、夏・冬合わせておよそ80万〜85万円前後との推計(年平均)となっています。
- 夏季平均:約42万円
- 冬季平均:約43万円
→年間合計:約85万円前後
ただし、これには大企業の影響が大きく、中小企業では年平均60万円前後が一般的です。
業種別ボーナス平均
経団連の調査の参考値によると、業種による差は以下の通りとなっています。
| 業種 | 平均支給額 | 傾向 |
| 製造業(自動車・電機など) | 約97万円 | 円安・輸出好調で高水準を維持 |
| 非製造業(サービス・商社など) | 約85万円 | 回復基調だが業績格差が大きい |
| 建設業 | 約92万円 | 公共事業増加で堅調 |
| 小売・飲食業 | 約55万円 | 物価高・人件費増で抑え傾向 |
| IT・通信業 | 約78万円 | 人材確保競争で前年より増加 |
業種間で約40万円以上の差が出ており、特に製造業と小売業の格差が顕著です。
企業規模別ボーナス平均
企業規模が大きいほど支給額も高くなる傾向は例年通りです。
| 企業規模 | 平均年間支給額 | 傾向 |
| 大企業(従業員1,000人以上) | 約95万円 | 安定して高水準。3ヶ月分超の企業も |
| 中堅企業(300〜999人) | 約70万円 | 業績による差が大きい |
| 中小企業(299人以下) | 約55万円 | 物価高の影響で減少傾向 |
大企業では「過去5年で最高水準」となる一方、中小企業では依然として業績格差がボーナスに直結しています。
年代別ボーナス平均
年齢が上がるほど支給額も増える傾向があります。
以下は厚労省データをもとにしたおおよその目安です。
| 年代 | 平均支給額(年間) | コメント |
| 20代前半 | 約45万円 | 初ボーナスをもらう層も多い |
| 20代後半 | 約60万円 | 昇給・昇格で増加傾向 |
| 30代 | 約80万円 | 責任ある役職で差が出始める |
| 40代 | 約95万円 | 管理職層が中心。ピーク帯 |
| 50代以上 | 約100万円前後 | 勤続年数と役職で大きく変動 |
ボーナスは何ヶ月分?支給月数の相場を比較

平均は「約1.5〜2.5ヶ月分」
多くの企業では、年間のボーナス総額は基本給の1.5〜2.5ヶ月分が目安。
夏・冬それぞれ1ヶ月前後の支給が一般的です。
大企業では3ヶ月以上も(業績好調企業の例)
製造業・総合商社・金融など一部の大手では、3〜4ヶ月分のボーナスを支給するケースもあります。
業績に連動するため、好調な年は“年収の約3割”がボーナスになる人も。
公務員・民間のボーナス比較
国家公務員のボーナス(期末手当+勤勉手当)は、人事院の勧告と政府決定によって毎年見直されます。
2024年度(直近実績)では、年間支給月数は約4.50ヶ月分(期末2.60ヶ月+勤勉1.90ヶ月)でした。
2025年度も同水準の勧告が想定されていますが、正式決定は例年年末の予算編成時点となります。
民間企業では業績連動による変動が大きい一方で、
公務員のボーナスは安定しており、年次による上下幅が比較的小さいのが特徴です。
【2025年版】ボーナスの使い道ランキング
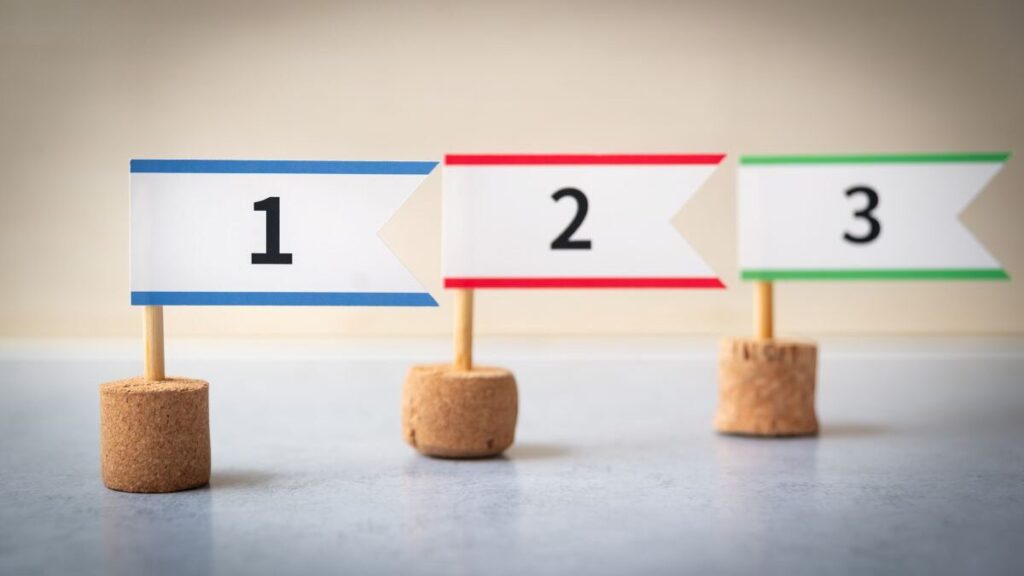
ボーナスの使い方にもトレンドがあります。2025年最新の調査では、以下のような結果が出ています👇
1位貯蓄・投資(将来への備え)
将来不安や物価上昇を背景に、「まずは貯蓄」「NISAなどで投資」が定番です。
将来の安心を優先する堅実な使い方がトップとなっています。
2位生活費の補填(物価高・教育費など)
教育費・住宅ローン・光熱費など、生活基盤を支える支出に回す人が増加中です。
「ボーナス=生活を守る資金源」という考え方が広がっています。
3位旅行・レジャー
コロナ後の回復で、国内外旅行や推し活への支出が再び上位になりました。
「経験にお金を使う」という姿勢が若年層に定着しています。
4位自己投資(資格・学習・副業)
資格取得やスキルアップにボーナスを充てる人も増加中です。
「将来の収入を増やすための投資」として、学び直しを選ぶ社会人も多く見られます。
5位自分や家族へのご褒美
1年間がんばった自分へのねぎらいとして、ちょっと贅沢な食事やファッション、家族旅行などに使う人も多くいます。
「思い出に残る使い方」で、心のリフレッシュを優先する傾向が広がっています。
ボーナスが少ない・もらえないときの対策

まずは家計の見直しを
ボーナスを当てにしすぎず、毎月の固定費を減らす工夫が第一歩です。
通信費・サブスク・保険料などを見直すだけでも月数千円の改善が期待できます。
副業や短期バイトで“プチボーナス”をつくる
ボーナスが少なくても、副業・短期バイトで自分だけのボーナスを作る人が増えています。
休日や空き時間を使って収入をプラスすることで、年間トータルではボーナス並みの効果も。
スキマバイトでできる新しいはたらき方
スキマバイトアプリ「シェアフル」なら、1日単位・数時間単位ではたらけるスキマバイトが多数掲載。
本業に支障なく、ちょっとした時間を使って“自分でつくるボーナス”が実現できます。
アプリ上では、就業実績が証明として残るため、転職時のアピールにも活かせます。
(参考:https://sharefull.com/information/7975/)
本業+αでボーナスの差を埋める
物価高が続く今、「収入を増やす工夫」が欠かせません。
投資や副業、シェアフルなどの短期バイトを活用して本業+αの収入を得ることで、ボーナス格差を自分の力でカバーできます。
ボーナスに関する知識とQ&A

税金・社会保険料はどうなる?
ボーナスにも所得税・住民税・社会保険料がかかります。
通常の給与とは別計算で課税され、手取りは支給額の約8〜15%減程度が一般的です。
ボーナスカットの原因と会社の判断基準は?
業績悪化・人件費高騰・部門成績などが主な理由。
企業によっては「役員のみカット」「社員全体で均等減額」といった形を取ります。
非正規・契約社員・派遣社員のボーナス事情とは?
支給されないケースもありますが、業績連動型・特別手当として支給される企業も増加中。
契約内容や評価制度を確認しておきましょう。
ボーナスっていつもらえるの?
一般的には6月と12月の年2回。
ただし、企業によっては年1回(決算賞与のみ)や業績ボーナス制度を採用している場合もあります。
まとめ|ボーナスの平均を知って、自分に合ったはたらき方を
ボーナスの平均を知ることで、自分の立ち位置や将来設計を考えるヒントになります。
業種や会社規模で差が出るのは自然なこと。大切なのは、その差をどう埋めていくかです。
節約や副業を組み合わせれば、ボーナスが少なくても生活のゆとりを作ることは十分可能。
シェアフルでスキマ時間にはたらきながら、自分で“+αのボーナス”をつくるのも賢い選択です。