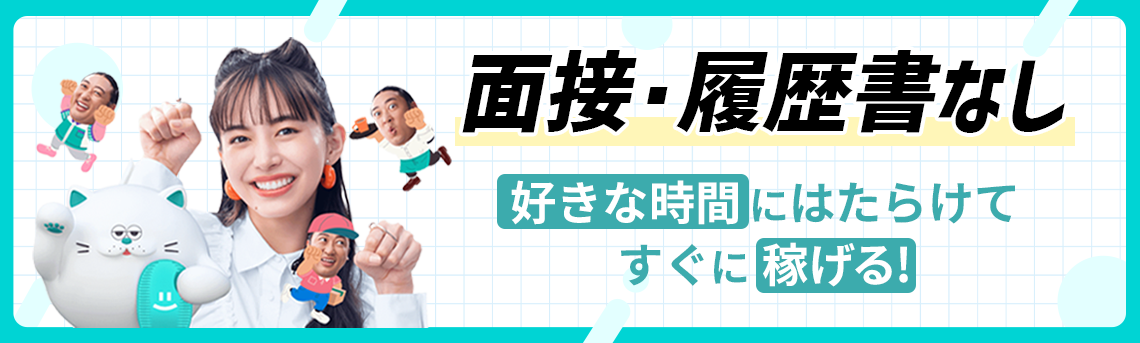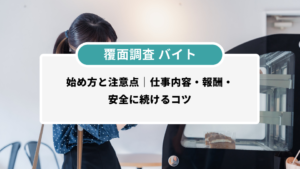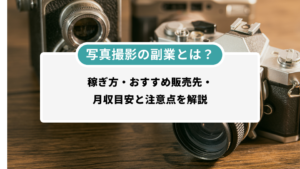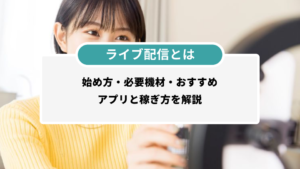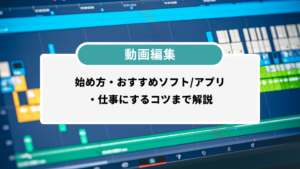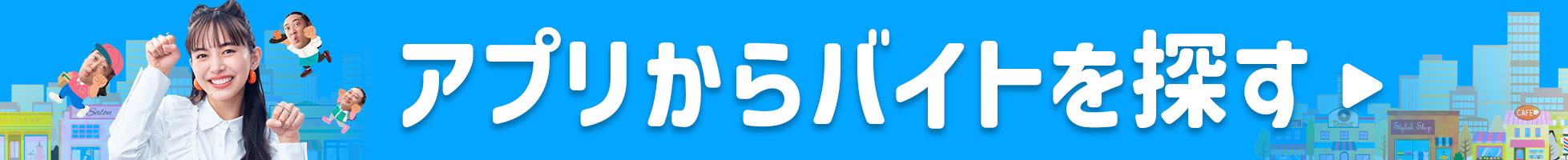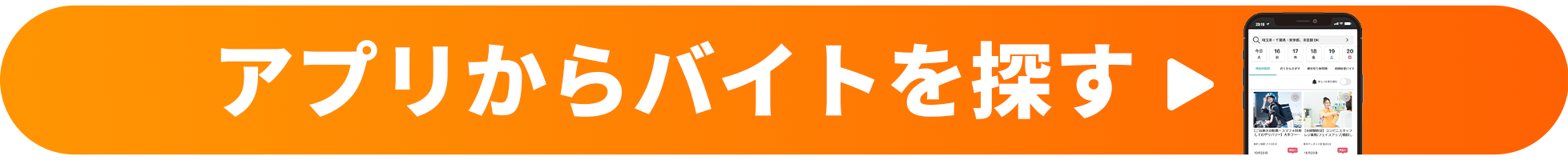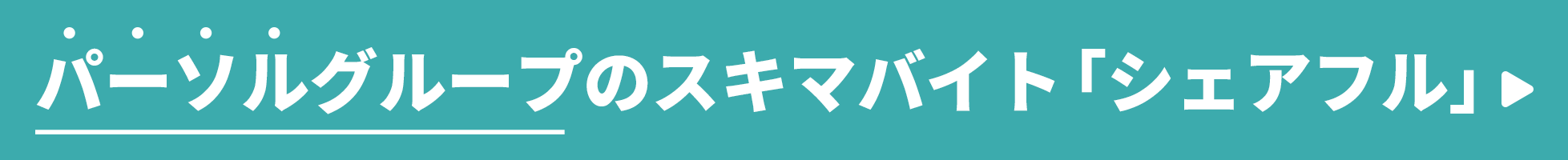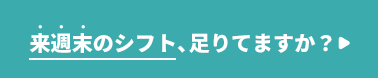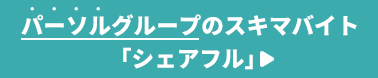アルバイト雇用でよくある労働基準法違反|10ケースとリスク・対策を解説

本記事では、アルバイト雇用に関する労働基準法の基本を解説し、よくある違反事例やそのリスク、適切な対策について分かりやすく解説します。健全な組織運営のためにも、法令を正しく理解し、日々の雇用実務に正しく反映させていきましょう。
アルバイトを雇用する際、企業は労働基準法を遵守する義務があります。しかし、実際には法律の細かい規定を把握していないために、気付かぬうちに違反してしまうケースもあります。もし労働基準法違反が発覚すれば、行政指導や罰則の対象となるだけでなく、会社の信用にも影響を及ぼしかねないため注意が必要です。
本記事では、アルバイト雇用に関する労働基準法の基本を解説し、よくある違反事例やそのリスク、適切な対策について分かりやすく解説します。
アルバイトにも適用される労働基準法とは?

労働基準法とは、労働者の権利を守るために定められた法律です。賃金や労働時間、休憩、解雇といった労働条件の最低基準を示しており、すべての企業がこのルールを守らなければなりません。雇用者と労働者の間には立場の違いがあり、労働者の権利が軽視されることもあります。こうした背景から、労働基準法は「はらたく人を保護する」目的で制定されました。
この法律は、企業に雇われている労働者であれば、正社員だけでなく、アルバイトやパート、契約社員にも適用されます。
労働基準法では、以下のような事項についてルールが定められています。
- 労働時間(法定労働時間、休憩、残業、深夜労働など)
- 賃金(最低賃金、割増賃金、賃金の支払い方法など)
- 休暇(有給休暇、産休・育休など)
- 解雇(解雇の条件、予告義務など)
- 労働契約(雇用契約の内容、労働条件の明示など)
- 安全衛生(職場の安全確保、健康診断など)
- 未成年者の労働(労働時間の制限、深夜労働の禁止など)
特に、従業員数が増えると、一人ひとりの労働環境を適切に管理することが難しくなります。アルバイトも含め、法令を遵守した労務管理体制を整えることが重要です。
アルバイト雇用において労働基準法違反となる10のケース

アルバイトを雇用する際、労働基準法に違反してしまうケースは意外と多く見られます。特に、長時間労働や残業代の未払い、適切な休憩時間を与えないことなどは典型的な違反例です。ここでは、よくある10のケースを紹介します。
ケース1. 長時間労働
アルバイトであっても、労働時間には上限が定められています。労働基準法では、1日8時間・1週40時間を超えてはたらかせることは原則として認められていません。これを超える場合は、事前に「36協定」を締結し、労働基準監督署へ届け出る必要があります。ただし、36協定を締結していたとしても、臨時的な特別の事情がない限り月45時間・年360時間までが限度となっています。
また、アルバイトが複数の職場を掛け持ちしている場合、合計労働時間も基準を超えないように注意が必要です。一つの職場で法定労働時間を超えていなくても、掛け持ちによって超過した場合、後に雇用契約を結んだ側の会社が割増賃金の支払い義務を負うことになります。知らずにはたらかせてしまうケースもあるため、勤務状況の確認を怠らないようにしましょう。
本人が「稼ぎたい」と希望していたとしても、労働時間の管理は会社側の責任です。無理のない勤務時間を設定し、適切な労務管理を行いましょう。
ケース2. 休憩なし
労働基準法では、労働時間に応じて休憩時間を与えることが義務付けられています。具体的には、労働時間が6時間を超える場合は少なくとも45分、8時間を超える場合は少なくとも1時間の休憩を、労働時間の途中に与えなければなりません。これはあくまでも最低付与時間なので、多く与える分に関しては会社の裁量に委ねられています。また、労働時間が6時間ぴったり、あるいは6時間未満の場合は休憩を与える必要はありません。
なお、業務の都合上、まとまった休憩を取ることが難しい場合もあるでしょう。そのような場合、労使協定を締結していれば、休憩時間を分割して与えることも可能です。たとえば、45分の休憩を30分と15分に分けて取得させることは認められています。
ケース3. 最低賃金を下回る時給設定
アルバイトの時給は、法律で定められた最低賃金以上にする必要があります。最低賃金には2種類あり、都道府県ごとに設定される「地域別最低賃金」と、特定の産業や職種に適用される「特定最低賃金」です。地域別最低賃金は、各都道府県内のすべての労働者に適用され、毎年見直しが行われています。
以下は、主要な都道府県の2024年度の地域別最低賃金です。
| 都道府県 | 最低賃金(円/時間) |
| 北海道 | 1,010 |
| 東京都 | 1,163 |
| 愛知県 | 1,077 |
| 大阪府 | 1,114 |
| 福岡県 | 992 |
| 沖縄県 | 952 |
参照:厚生労働省「地域別最低賃金の全国一覧」
最低賃金を下回る時給設定は、最低賃金法違反となり、罰則の対象となります。アルバイトを雇用する際は、最新の最低賃金を確認し、適切な賃金設定を行いましょう。
ケース4. 残業代未払い・深夜割増なし
最近では、残業代を全く支払わないという企業はほとんどなくなりました。しかし、正しく計算されていなかったり、そもそも適切な基準で支払われていなかったりするケースは依然として存在します。特にアルバイトの場合、「シフト制だから残業はない」という誤解から、本来支払われるべき残業代が支払われていないことがあるのも現状です。
労働基準法では、労働時間や時間帯に応じて、以下のような割増賃金を支払うことが企業側に義務付けられています。
| 割増賃金の種類 | 割増率(通常賃金に対する割合) | 適用条件 |
| 法定時間外労働 | 25%以上 | 1日8時間・週40時間を超えたとき |
| 60時間超/月の法定時間外労働 | 50%以上 | 月間の時間外労働が60時間を超えたとき |
| 深夜労働 | 25%以上 | 22時から5時までの間にはたらかせたとき |
| 休日手当 | 35%以上 | 法定休日(週1日)にはたらかせたとき |
たとえば、通常の時給が1,000円の場合、時間外労働(25%増)では1,250円、月60時間を超える時間外労働(50%増)では1,500円、休日労働(35%増)では1,350円、深夜労働(25%増)では1,250円の賃金を支払わなければなりません。
さらに、時間外労働が深夜に及ぶ場合、割増率は合算され、50%以上(25%+25%)となります。同様に、休日労働が深夜に及ぶ場合、割増率は60%以上(35%+25%)です。
ケース5. 有給休暇を与えない
アルバイトを雇用する際、意外と見落とされがちなのが有給休暇の付与です。
労働基準法では、雇入れから6カ月以上継続勤務し、その期間の8割以上出勤した労働者には年次有給休暇を与えなければならないと定められています。この規定はアルバイトにも適用され、労働日数や勤続年数に応じて日数が決まります。
たとえば、週5日勤務の労働者には6か月経過時点で10日間、その後、最大20日まで増加します。一方、週の労働日数が少ない場合も、所定労働日数に応じた「比例付与」のルールがあり、たとえば週3日勤務なら6カ月後に5日間の有給休暇を付与しなければなりません。
年次有給休暇の付与日数を詳しく知りたい方は、厚生労働省の「アルバイトを雇う際、始める前に知っておきたいポイント」をご確認ください。
ケース6. 会社都合での一方的な解雇
アルバイトだからといって、企業側が自由に解雇できるわけではありません。労働基準法では、解雇には正当な理由が必要とされており、一方的な解雇は認められないのが原則です。
たとえば、勤務態度が著しく悪い、会社のルールに従わない、経営上やむを得ない事情がある場合などに限り、解雇が認められる可能性があります。ただし、「シフトに入れなくなったから」「売上が落ちてきたから」といった理由だけで解雇はできません。
また、会社が労働者を解雇する場合は、原則として少なくとも30日前までに解雇予告を行う必要があります。これを守らず即時解雇する場合は、30日分以上の平均賃金(解雇予告手当)を支払う義務が生じます。
ケース7. 代替要員を探すよう指示
アルバイトであっても、企業と雇用契約を締結している以上、その労働力の使い方は会社の裁量に委ねられています。このため、「休むなら自分で代わりを見つけてほしい」といった指示を、正当な業務指示だと考えてしまう会社もいるかもしれません。
ですが、これは労働契約の趣旨を逸脱する行為です。労働者には自分の業務を遂行する義務はありますが、代替人員の確保まで責任を負う立場にはありません。代替要員を見付けられなければ休めないという空気をつくることは、企業の配慮義務を欠いた対応であり、業務命令権の濫用とみなされる可能性があります。
ケース8. 退勤や欠勤に対する極端なペナルティ
アルバイトが遅刻や無断欠勤をした際、会社としては業務に支障が出ることから、何らかのペナルティを検討することもあるでしょう。しかし、労働基準法では、労働者に対する減給の制裁について、以下のように制限を設けています。
- 減給額の上限:1回の事案につき、平均賃金の半日分を超えてはならない
- 総額の制限:減給の総額が、1賃金支払期における賃金総額の10分の1を超えてはならない
たとえば、1日の平均賃金が8,000円の労働者が遅刻した場合、減給できるのは最大でも4,000円までです。また、月の賃金が20万円の場合、たとえ複数回にわたる問題行動があったとしても、減給総額は2万円を超えてはいけません。
これらの制限を超えるペナルティを課すことは、労働基準法違反となるため注意しましょう。
ケース9. シフトの急な変更・キャンセル
会社の都合による急なシフト変更やキャンセルは、労働契約法に抵触する可能性があります。労働契約の変更には労働者と使用者双方の合意が必要であると規定しているためです。
具体的には、シフトが確定した後に、労働者の同意なしに休みにしたり、勤務時間を短縮したりすることは違法となり得ます。また、閑散期だからといって、労働者の了承を得ずに早退を命じることも認められません。
シフト変更やキャンセルを行う際は、労働者との十分なコミュニケーションを図り、双方が納得できる形で調整することが必要です。
ケース10.18歳未満のアルバイトを22時以降にはたらかせている
高校生をはじめとする18歳未満のアルバイトを雇う際には、労働時間に特に注意が必要です。労働基準法では、18歳未満の労働者を午後10時から午前5時までの深夜時間帯に就業させることを原則として禁じています。この規定は、労働者の健康や学業への影響を配慮したものです。
「本人が希望している」「短時間だけだから」などの理由であっても、法律上は例外にはなりません。仮にシフトが22時をまたぐ場合は、21時台のうちに退勤させるなどの対応が求められます。
アルバイト雇用における労働基準法違反の発覚経緯

では、労働基準法違反はどのようにして発覚するのでしょうか。
実際、多くのケースでは従業員からの通報が発端となっているようです。実際、大阪労働局が公表している「令和5年における送検状況について」によれば、2023年に送検された労働基準法違反17件のうち、14件が告訴・告発によるものでした。これは全体の約82%を占めます。
| 発覚の端緒 | 件数 |
| 告訴・告発 | 14 |
| 告訴・告発以外 | 3(うち2件は重大な労働災害) |
| 計 | 17 |
参照:大阪労働局「令和5年における送検状況について」
また、社内で労働者が直接会社に違反を指摘するケースもあります。このような指摘を受けた場合、企業側は速やかに事実関係を調査し、違反が確認された際には迅速に改善策を講じることが必要です。
一方、労働者が労働基準監督署に通報した場合、同署による立入検査が実施され、違反が認められれば是正勧告を受けることになります。このような事態を未然に防ぐためにも、日頃から労務管理を徹底し、労働基準法を遵守する姿勢が重要です。
アルバイト雇用における労働基準法違反が発覚した場合のリスク

労働基準法違反が発覚すると、企業は法的責任を問われるだけでなく、社会的信用を大きく損なう可能性があります。ここでは、企業側が負うことになる具体的なリスクについて解説します。
罰金や懲役刑が科せられることも
労働基準法に違反した企業には、行政指導だけでなく、罰金刑や懲役刑が科される可能性があります。
労働基準法で定められている罰則は、違反内容によって次の4つに分類されます。
- 1年以上10年以下の懲役または20万円以上300万円以下の罰金(強制労働)
- 1年以下の懲役または50万円以下の罰金(最低年齢違反、中間搾取の排除など)
- 6カ月以下の懲役または30万円以下の罰金(不当な解雇、残業代の未払いなど)
- 30万円以下の罰金(労働条件の明示義務違反など)
参照:労働基準監督署対策相談室「労働基準法の罰則」
このなかで最も身近なものとしては、「6カ月以下の懲役または30万円以下の罰金」です。たとえば、労働時間の上限を超えてはたらかせた場合や、賃金を適正に支払わなかった場合などがこれに該当し、違反の程度が悪質であるほど科される罰も重くなります。
仮に悪意がなくても、労働基準法は「知らなかった」「うっかりしていた」では済まされません。事前に正しい知識を身につけ、企業としての責任ある対応を心がけましょう。
企業名や違反内容が公表される可能性がある
労働基準法違反が発覚し、送検まで至った場合、企業名や違反内容が厚生労働省や労働局のホームページ上で公表される可能性があります。ただし、違反があったからといって、すべてのケースで企業名が公表されるわけではありません。
企業名の公表は、厚生労働省が定める「企業名公表の基準」に該当するかどうかで判断されます。たとえば、社会的影響の大きい企業や是正勧告を無視して違反を繰り返している企業、または労働者の健康に重大な危険を及ぼした場合などが該当します。
いわゆるこの「ブラック企業リスト」に名前が載れば、社会的信用の低下は避けられません。その結果、人材採用にも支障が出るおそれがあり、企業にとって深刻なダメージとなるでしょう。
アルバイト雇用において企業が労働基準法に違反しないためには?

労働基準法違反を未然に防ぐには、日頃から法令を正しく理解し、適切な労務管理体制を整えておくことが重要です。ここでは、企業が取るべき具体的な対策をご紹介します。
労務管理を徹底する
アルバイト雇用において労働基準法に違反しないためには、まず基本となる労務管理の徹底が欠かせません。勤務時間、休憩、残業、有給休暇など、労働基準法で定められた内容を正確に把握し、日々の運用に反映させる必要があります。
特に、シフト制ではたらくアルバイトは就業状況が変動しやすく、管理が疎かになりがちです。だからこそ、労働時間の記録や契約内容の明文化など、細かな部分まで管理体制を整えておきましょう。問題の兆候を見逃さず、早めの対策が必要です。
自社に似た業種の「事例」を学ぶ
労働基準法の条文だけを読んでも、実際の業務にどう当てはめるべきか分かりづらいと感じる企業は多いかもしれません。そうしたときに役立つのが、他社の労務トラブルや是正事例です。
特に、自社と同じ業種や規模の企業のケースは参考になりやすく、現場で起きやすい問題点や見落としがちなリスクに気付く手がかりとなるでしょう。厚生労働省や各労働局が公開している事例集なども活用し、トラブルを未然に防ぐ視点を養うことが大切です。
まとめ
本記事では、アルバイトを雇用する際に起こりやすい労働基準法違反のケースや、違反が発覚した場合に企業が負うリスクについて解説しました。
以前は「多少の違反は仕方ない」といった風潮も少なからずありましたが、今はそうした時代ではありません。法令を軽視する企業は、従業員はもちろん、取引先や世間からも信頼を失い、経営に大きな影響を及ぼすことになります。万が一指摘を受けた場合には、事実関係を確認し、必要な是正措置を速やかに講じることが重要です。
健全な組織運営のためにも、法令を正しく理解し、日々の雇用実務に正しく反映させていきましょう。