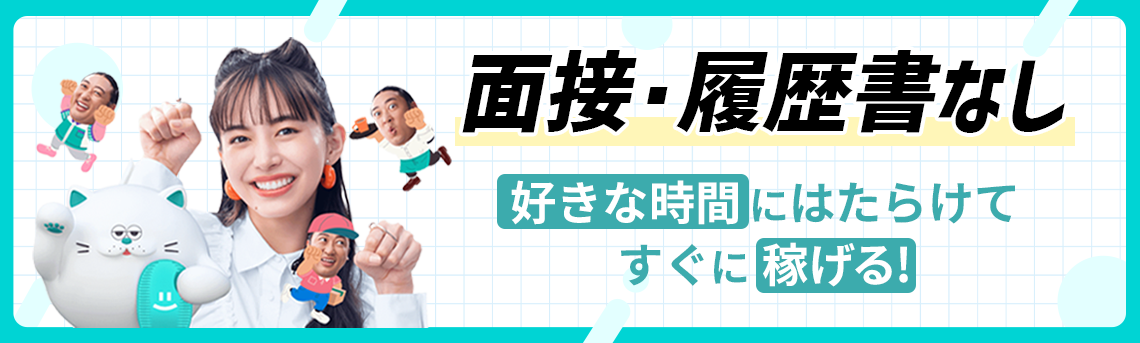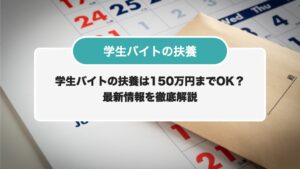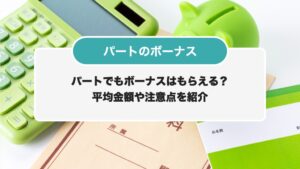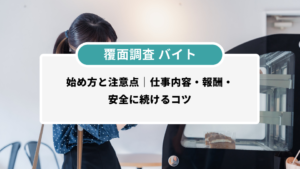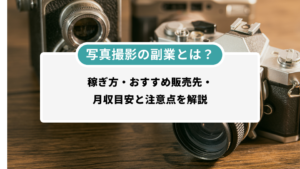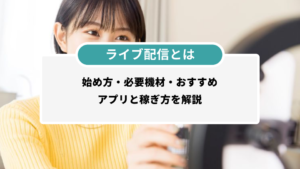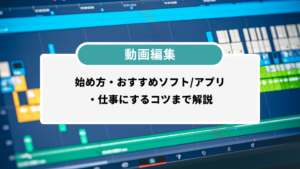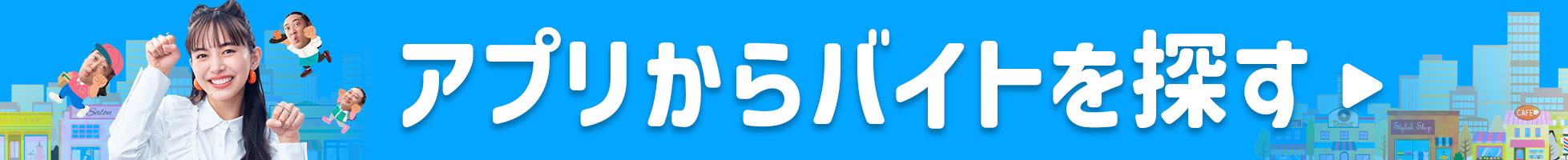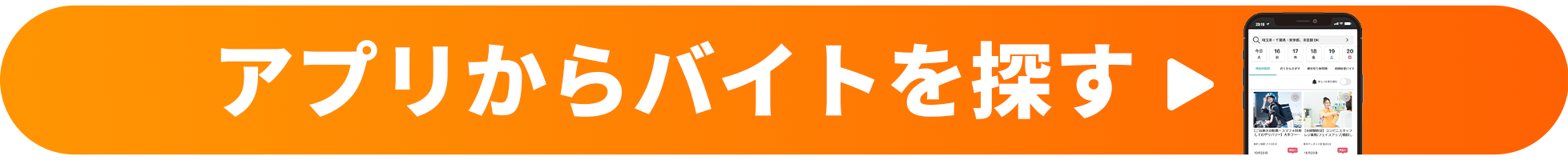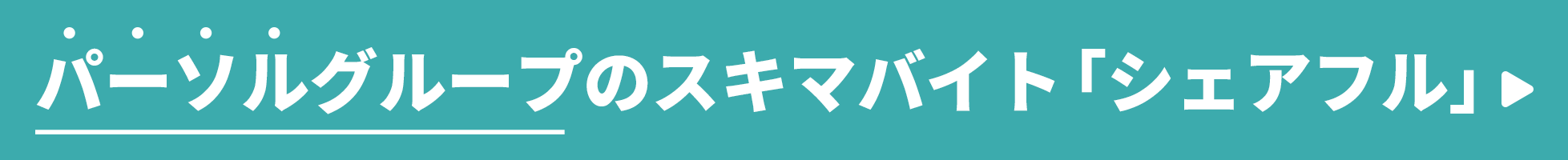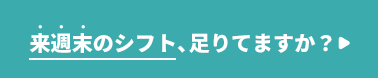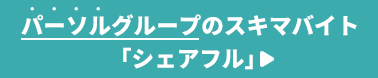【2026年最新版】副業でも社会保険に加入する?手続きや注意点を解説
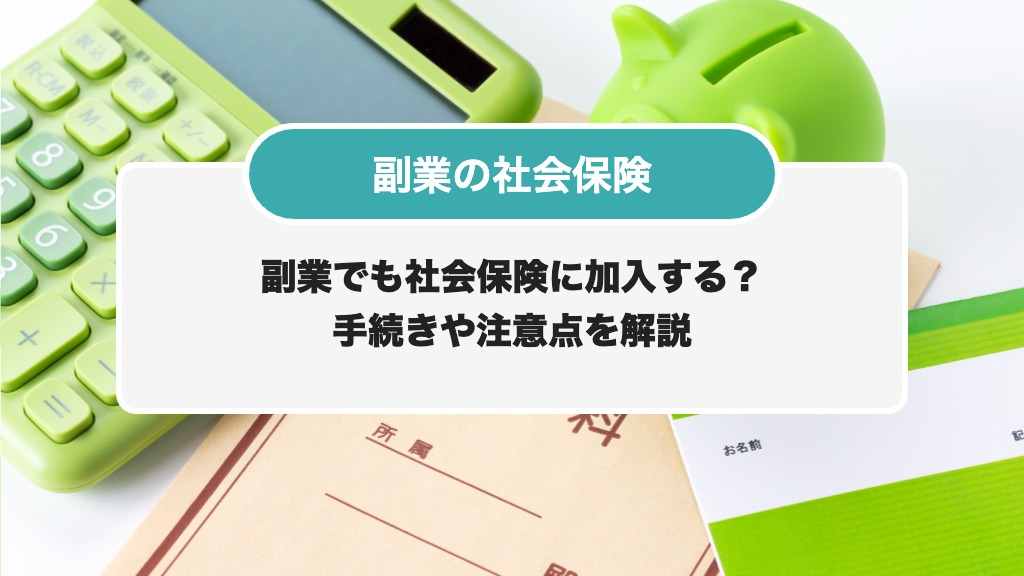
副業を始める際には、稼働時間や収入を気にする人は多いですが、社会保険への加入義務についてはあまり意識されていません。
しかし、必要な社会保険手続きを怠ると、企業も従業員もペナルティを受ける可能性があります。
そこで、この記事では「副業における社会保険加入の必要性」や「加入時の注意点」について解説していきます。
「これから副業を始めよう」と考えている人は、ぜひ参考にしてください。
副業で社会保険の加入が必要になる条件

副業を始めると、「社会保険への加入は必要か」は重要なポイントですが、意識する人は少ないです。
結論、副業で社会保険への加入の必要性は、副業の形態や勤務条件によって異なります。
ここでは、以下の点について解説していきます。
- 副業でも社会保険に加入が必要な条件
- 個人事業主の場合、社会保険に加入する必要があるのか
本業と副業の両方で社会保険に加入が必要な条件
副業でも一定要件を満たすと、副業先の勤務先でも社会保険に加入しなければなりません。
「本業先で社会保険に加入しているから、副業先で加入しなくても大丈夫」と勘違いしている人が多いので、注意して下さい。
副業先でも社会保険に加入する具体的な要件は、以下の通りです。
- 1週間の所定労働時間が20時間以上
- 1か月の収入が88,000円以上
- 勤務期間が2か月を超える見込みがある場合
- 従業員数が101人以上の事業所で勤務する
- 学生でないこと
- 週の所定労働時間と月の所定労働日数が一般社員の4分の3以上
「二以上事業所勤務」と呼ばれるケースで、正社員として本業ではたらきつつ、上記の要件を満たすアルバイトやパート従業員が該当します。
本業・副業の給与の合計金額を基に厚生年金や健康保険の保険料が計算されるためです。
副業を始める際には、ご自身が社会保険の加入要件に該当しているかを確認するようにしましょう。
個人事業主の副業は社会保険に影響なし
個人事業主として副業を始めるケースは、社会保険に加入する必要はありません。
具体的な内容は以下の通りです。
- ブログ運営
- Webライター
- 動画編集
- Webデザイン
- ハンドメイド販売
実際に、私は副業でWebライターをしていますが、副業で社会保険に加入していません。
なぜなら、個人事業主としての収入は事業所得に該当するからです。社会保険料は事業所得には発生しません。本業の給与に対してのみ保険料がかかります。
このように、雇用契約を結ばずに自ら事業として行っている場合は、厚生年金や健康保険に新しく加入する必要はありません。
副業の際に加入が必要な社会保険

雇用関係が発生する場合、副業でも社会保険に加入する必要があります。
しかし、全ての社会保険に加入しなければならないわけではありません。
副業の状況次第で加入が必要になったり、そもそも加入できないケースもあります。
ここでは、それぞれの保険の加入条件について、解説していきます。
加入が必要な保険
雇用契約が発生する副業の場合、以下の5つの社会保険に加入する必要があります。
- 健康保険
- 介護保険
- 厚生年金保険
- 雇用保険
- 労災保険
労災保険はすべての労働者が加入対象のため、本業・副業それぞれの事業所で加入する必要があります。
しかし、その他の保険は、必ずしも本業と副業の両方の会社で加入するわけではありません。
次の項目からは、それぞれの保険の加入条件を解説していきます。
健康保険・介護保険・厚生年金保険の加入条件
副業でも、健康保険・介護保険・厚生年金保険に加入するケースがあります。
加入要件は2022年10月に拡大されました。
以下のいずれかの条件に該当する場合は、3つの保険に加入する義務が生じます。
- 1週間の所定労働時間が20時間以上
- 1か月の収入が88,000円以上
- 勤務期間が2か月を超える見込みがある場合
- 従業員数が101人以上の事業所で勤務する
- 学生でないこと
- 週の所定労働時間と月の所定労働日数が一般社員の4分の3以上
これらの全ての要件を満たすと、本業と副業の合計金額を基に社会保険料が計算されます。そのため、思った以上に保険料の負担が大きくなるでしょう。
保険料の負担を増やさないためにも、副業のはたらき方や収入を調整する必要があるかもしれません。
雇用保険の加入条件
労働者が失業したときや育児・介護などではたらけなくなったときに、生活や就職活動を支えるための制度である雇用保険の加入要件は以下の2点です。
- 加入条件は週の所定労働時間が20時間以上
- 31日以上の継続雇用が見込まれること
ただし、雇用保険については、他の社会保険とは異なり複数の職場で同時に加入することはできません。
雇用保険とその他の保険の加入要件の違いを表にまとめました。
| 健康保険・介護保険・厚生年金保険 | 条件を満たせば複数の職場で加入 |
| 雇用保険 | 主たる賃金支払者でのみ加入※収入が多い本業の勤務先が多い |
つまり、雇用保険は複数の職場で加入できず1社でしか加入できません。
労働保険とその他の社会保険の加入条件は異なることを覚えておきましょう。
副業で社会保険に加入する場合の注意点

副業で社会保険に加入する場合、保険料を納付するだけではいけません。
従業員自身が加入手続きを行う必要があります。この手続きが漏れてしまうと、思いもよらぬペナルティを受ける可能性があります。
そこで、副業で社会保険の加入対象となった際の注意点と加入を怠った場合のペナルティを解説します。
自身で手続きが必要
「二以上事業所勤務」に該当して、副業で社会保険の加入対象となると、自身で加入手続きをしなければなりません。
もしこの手続きをしていないと、企業も従業員にもペナルティが課されてしまう可能性があります。
「二以上事業所勤務」に該当する場合は、ペナルティが課されないように、必ず以下の手続きを取りましょう。
- 副業先に別の企業で社会保険に加入していると伝える
- 健康保険・厚生年金保険 被保険者所属選択・二以上事業所勤務届を提出する
1. 副業先に別の企業で社会保険に加入していると伝える
雇用関係の発生する副業をする際は、別の企業で社会保険に加入していることを伝えましょう。
副業先は従業員を雇用する際に「健康保険・厚生年金保険 被保険者資格取得届」を年金事務所に提出します。その際に「二以上事業所勤務」である旨を記載しなければならないからです。
この報告を怠ってしまうと、副業先は誤った手続きを行ってしまう可能性があります。
企業は、従業員からの報告がなければ、別の仕事をしていると把握することができません。
必ず従業員の方から、別の企業で社会保険に加入している旨を伝えてください。
2. 健康保険・厚生年金保険 被保険者所属選択・二以上事業所勤務届を提出する
副業でも社会保険の加入要件を満たす場合は、自身で「健康保険・厚生年金保険 被保険者所属選択・二以上事業所勤務届」を作成し、年金事務所もしくは事務センターに提出します。
この届出は、就業先が複数ある場合、どちらを「主たる事業所」とするかを指定する届出です。
本業先・副業先のどちらの企業も主たる事業所に指定できます。
ただし、主たる事務所を管轄する年金事務所が窓口になります。社会保険の制度を利用する際は、その年金事務所を利用することになるため慎重に判断しましょう。
基本的には本業の勤務先を主たる事業所とするケースが多いですが、副業先の企業を指定することも可能です。
社会保険の加入手続きを怠った場合
副業の社会保険の加入手続きは従業員自身で行わなければなりません。
もし加入手続きを怠ったり、日本年金機構の加入指示に従わなかった場合、事業主には以下の罰則が科されます。
- 事業主には6か月以下の懲役
- 50万円以下の罰金
- 未払いの保険料を過去2年にさかのぼって納付
保険料の納付は、事業主だけでなく従業員も負担する必要があるため、急な支出になります。
さらに、本来受けられる給付金や年金額にも影響が出る可能性があるため、副業をする際は社会保険への加入が必要かどうかを必ず確認するようにしましょう。
加入が必要な場合は、めんどくさがらずに本業先に申告し、「健康保険・厚生年金保険 被保険者所属選択・二以上事業所勤務届」を作成・提出しましょう。
副業で社会保険料が増える・増えないケース

副業をして社会保険料が増えるかどうか、副業のはたらき方や収入によるところが大きいです。
ここからは、副業をして社会保険料が増えるケースと増えないケースを具体的に紹介していきます。
社会保険が増えるケース
副業によって社会保険料が増えるかどうかは、副業の形態や収入によって大きく左右されます。
ここからは、副業で社会保険料が増える場合と増えない場合を具体的に紹介します。
ただし、この場合でも将来受け取る年金額の増加など、メリットもある点を理解しておきましょう。
パート・アルバイトで週20時間以上はたらいている場合
企業から雇用される形でパートやアルバイトの副業をする場合、以下の条件を満たすと社会保険に加入しなければなりません。
- 1週間の所定労働時間が20時間以上
- 1か月の収入が88,000円以上
- 勤務期間が2か月を超える見込みがある場合
- 従業員数が101人以上の事業所で勤務する
- 学生でないこと
- 週の所定労働時間と月の所定労働日数が一般社員の4分の3以上
1つ目の条件である所定労働時間については、雇用契約書に記載された時間で判断される点には注意が必要です。
ただし、契約上20時間未満でも実際の労働時間が2ヶ月連続で週20時間を超え、その状況が続く見込みがある場合は、3ヶ月目から社会保険に加入しなければなりません。
副業で社会保険に加入すると、本業と副業の収入を合算した額に基づいて保険料が計算されるため、社会保険料の総額は増加します。
法人として会社を設立した場合
社会保険料が増えるもう1つの要件は、「法人として会社を設立」した場合です。
法人を設立すると、代表者として役員報酬を受け取ると、たとえ代表者1人だけの「1人法人」であっても、原則として社会保険への加入義務が生じます。
この場合、本業の給与と法人からの役員報酬を合算して社会保険料が決まるため、保険料が増加します。
さらに、従業員を雇った場合、事業主負担分の保険料が発生するため、さらに保険料は多くなります。
設立した法人から役員報酬を受け取る場合や、従業員を雇う場合は、社会保険料が増えると想定した上で実施しましょう。
社会保険が増えないケース
一方で、社会保険料が増えないケースもあります。
社会保険料は給与所得に対して発生するため、その他の所得の場合、副業で社会保険料を負担する必要はありません。
社会保険料が増えない以下のケースについて、解説していきます。
- 事業所得や雑所得
- 個人事業主としての副業
事業所得や雑所得
社会保険の対象は給与所得のため、副業による所得が事業所得や雑所得の場合、社会保険料の計算対象にはなりません。
最近、副業として人気のWebライターや動画編集で得た副業収入は雑所得に該当するため、社会保険料の対象にならないのです。
そのため、本業の収入のみが社会保険料の計算対象となり、社会保険料は増えません。
個人事業主としての副業
会社員が個人事業主として副業を行う場合も、社会保険料は増加しません。
なぜなら、個人事業から生じる利益に対しては社会保険料がかからないためです。
例えば、飲食店を開業したり、オンラインショップを運営して商品を販売する場合が該当します。
この場合、社会保険料の対象とはならないため、社会保険料が増えることはありません。
副業で二重に社会保険に加入する場合のよくある質問

最後に、副業で社会保険料を納める場合のよくある質問について解説していきます。
- 社会保険料の計算方法
- 受け取れる年金は増えるのか
社会保険料はどのように計算される?
「二以上事業所勤務者」として複数の会社で社会保険に加入する場合、社会保険料は本業と副業の報酬を合算した金額をもとに計算されます。
具体例を挙げて解説します。
- 本業(A社からの)の収入30万円
- 副業(B社からの)の収入20万円
- 合計の収入50万円
この場合、厚生年金保険料は18.3%で労使折半となるため、以下の計算式で求められます。
厚生年金保険料=(30万円+20万円)×18.3%=91,500円
従業員が負担する保険料=91,500円×1/2=45,750円
健康保険料の場合も、保険料率は異なりますが同様の計算で求められます。
受け取れる年金は増える?
副業先の事業所でも厚生年金に加入している場合、将来受け取れる年金額は増加します。
なぜなら、老齢厚生年金の計算の基となる「標準報酬月額」は、本業と副業の報酬を合算した金額で決定されるからです。副業の収入が加わると標準報酬月額が高くなりやすく、その分、将来の年金額もその分増加する傾向にあります。
ただし、2025年3月時点で厚生年金の計算元である報酬比例部分にはそれぞれ上限があります。
- 標準報酬月額:65万円
- 標準賞与額:150万円/1か月
この上限を超える部分は年金額に反映されないと理解しておきましょう。
まとめ
雇用関係のある副業を行い一定の条件を満たす場合は、副業の勤務先でも社会保険に加入する必要があると解説してきました。
ただし、副業の場合、従業員自ら申告したり書類を作成しなければ、ペナルティを受けてしまう可能性があります。
「知らなかった」では済まされないため、副業先の企業でも社会保険に加入する必要があるかは必ず確認しておきましょう。