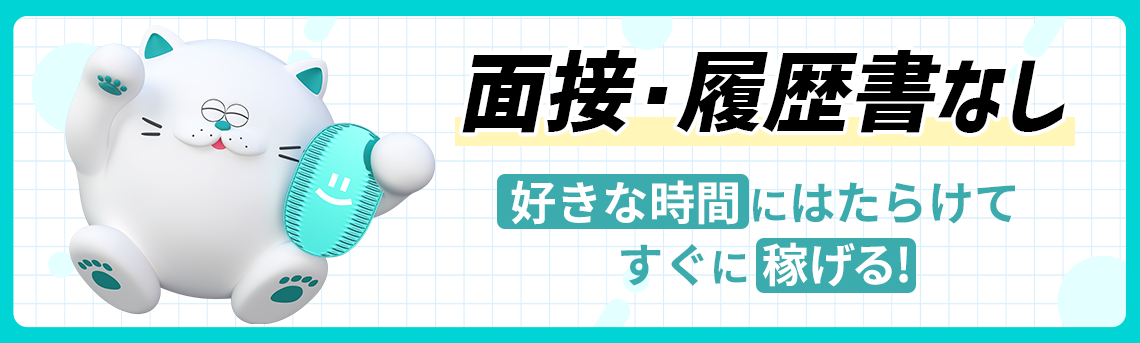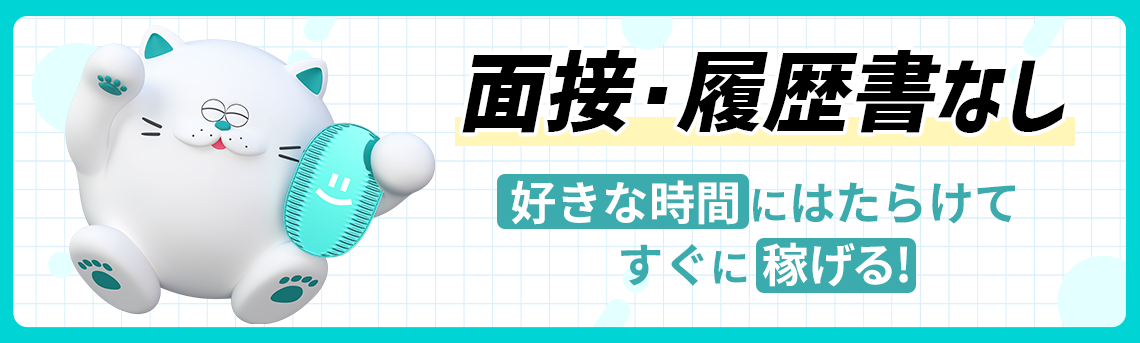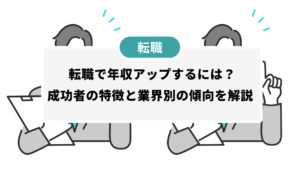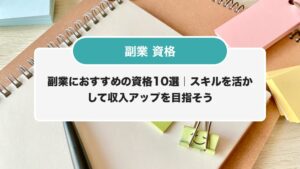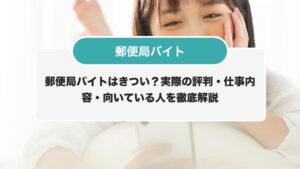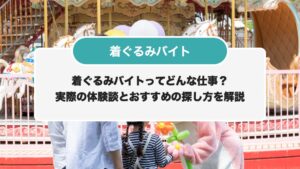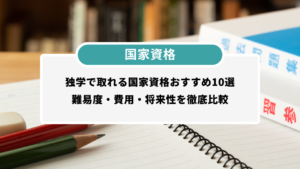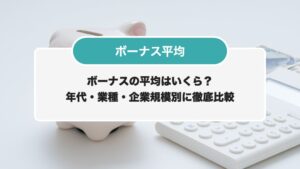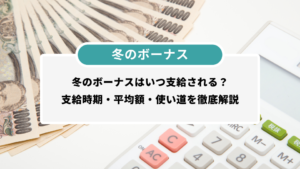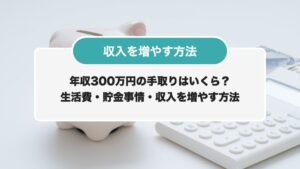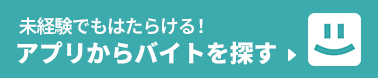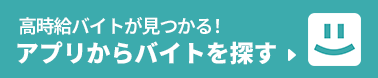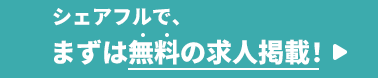平均勤続年数の目安は何年?業界別データと企業選びへの活用法
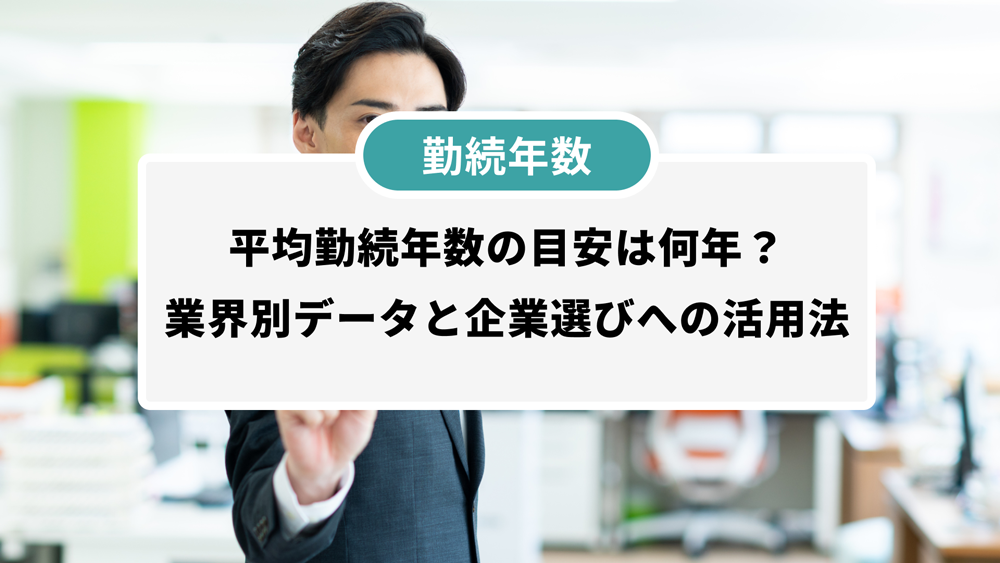
企業を選ぶ際、給与や福利厚生、はたらき方などと並んで注目される指標のひとつが「平均勤続年数」です。一見すると地味な数字かもしれませんが、ここには社員の定着率や企業の風土、はたらきやすさなど、企業の“内側”を知るヒントが詰まっています。
「平均勤続年数が短い=ブラック企業」「長い=安定していて良い会社」といった印象を持たれがちですが、実際には業界特性や企業の成長フェーズによって大きく異なります。この記事では、平均勤続年数の基礎知識から、業界別データ、企業選びや転職活動での活かし方まで、幅広く解説します。数字の裏側にある“本質”を見抜き、自分に合った企業選びに役立ててください。
平均勤続年数とは?知っておきたい基本と数字の見方
勤続年数の定義と計算方法
勤続年数とは、従業員が同じ企業に在籍し続けた期間のことを指し、これは「1社でどれだけ長くはたらいたか」を示す指標であり、採用・定着・退職などの人材の動きが反映されます。
具体的には、正社員を中心に「在籍年数の合計 ÷ 社員数」で計算されます。注意すべきは、パート・アルバイトや契約社員が含まれていない場合もあるという点です。統計を読む際は、対象となる従業員区分を確認することが重要です。
最新の全国平均は何年?【厚生労働省の最新データ】

厚生労働省が公表した「令和5年 賃金構造基本統計調査」によると、日本の平均勤続年数は約12.4年です(正社員全体)。
男女別で見ると、男性が約13.8年、女性が約9.9年となっており、男女で差があるのは結婚・出産・介護などのライフイベントに影響を受けやすい側面もあると考えられます。
※参照元:厚生労働省「賃金構造基本統計調査」
平均勤続年数の目安はどのくらい?
業種や職種によって異なる“目安年数”
平均勤続年数には明確な正解はなく、業界や職種によって大きく異なります。たとえば、メーカーやインフラ系の企業では10年を超えるケースが多く見られますが、営業職や小売業、ベンチャー系では3〜5年が一般的です。
業界特性や職務の専門性、企業の人材戦略などが関係しており、単純に「長ければ良い」というものではありません。
中小企業と大企業でどう違う?
中小企業は人材の流動性が高く、平均勤続年数が短くなりやすい傾向があります。一方で、大企業は雇用の安定性や福利厚生の充実、体系化された人事制度などが背景にあり、比較的長くなる傾向が見られます。
また、スタートアップなどの新興企業では採用活動が活発であり、社員の入れ替わりが多いため、結果として平均年数が短く算出されるケースもあるでしょう。
転職市場で“目安”とされる年数の根拠

転職市場において、よく言われる目安のひとつが「3年」です。これは、業務経験やスキルが一定程度身につく期間とされているためです。3年未満の退職は早期離職と見なされることが多く、採用担当者からの評価が分かれることも。ただし、若手のキャリアチェンジや異業種への挑戦が目的であれば、むしろ積極的に評価されるケースも増えています。
また「5年」は中堅社員と見なされる年次であり、マネジメントや後輩指導の経験があると判断されやすくなります。これらの年数をひとつの“区切り”としてキャリアを考える人も多くいます。新卒からの転職タイミングについて詳しく知りたい方は、こちらの記事も併せてご参照ください。
▶新卒入社した会社を転職するおすすめのタイミングは?
業界別に見る平均勤続年数の実態

長くはたらける業界は?平均勤続年数が長い業界TOP5
厚生労働省や民間調査によると、以下の業界は平均勤続年数が比較的長い傾向にあります。
1.金融・保険業:制度が整っており、福利厚生も充実
2.電力・ガス・インフラ業:公共性が高く、安定感がある
3.製造業(大手):工場勤務などで定着率が高い
4.公務員・公共サービス:転勤が少なく、安定した職場
5.教育・研究機関:専門性が高くキャリアが長期化しやすい
これらの業界は給与水準や福利厚生が安定しており、長くはたらく社員が多いのが特徴です。
短くなりやすい業界は?離職率が高めな業種の特徴
一方、以下の業界では平均勤続年数が短い傾向があります。
1. IT業界:技術革新が激しく、転職によるキャリアアップが多い
2. 飲食・サービス業:労働時間が長く、賃金水準も低め
3. 小売業:土日勤務や不規則なシフトが多く、定着しにくい
これらの業界では人材の入れ替わりが激しく、新規採用も活発なため、平均が押し下げられます。
また、平均勤続年数が短いからといって、必ずしもネガティブな意味を持つわけではありません。たとえば、以下のような背景がある企業も存在します。
・設立間もないスタートアップ企業:新規採用が多く、社員の年齢層も若いため、平均が短くなりやすい
・急成長中の企業:組織の拡大フェーズで新陳代謝が活発な時期にある
・キャリア自立を促す企業風土:一定のスキルや経験を得た後、外部での活躍を前提とした人材戦略を持つ企業もあります
このように、数字の背景には組織の戦略や成長過程が関係していることも多く、単純に「短い=悪い」とは言えません。
「長い=ホワイト企業」「短い=ブラック企業」ではない理由勤続年数が長ければ必ずしもホワイト企業とは限りません。逆に、短い企業がすべてブラック企業というのも誤解です。
たとえば、古い体制に縛られた企業では人が辞めにくく、結果的に平均が伸びるケースもあります。一方で、柔軟なキャリア形成を支援する企業では、成長を促すために短期間での転職も推奨されることがあります。
企業選びや就活・転職活動でどう活かす?
キャリアアドバイザーが重視する視点とは?
キャリアアドバイザーの間では、平均勤続年数は「企業文化の定着度」や「人材戦略の傾向」を測る参考指標とされています。たとえば、平均勤続年数が極端に短い企業では、教育体制やフォローアップの弱さ、人間関係の問題が背景にあることも。一方、長い企業では、昇進のチャンスが少なくポジションが固定されがちという声もあります。
そのため、平均勤続年数を読む際には、「長ければ安定」「短ければ危険」という単純な見方ではなく、「なぜその年数になっているのか」という背景に着目する視点が大切です。
複数企業の勤続年数を比較する際のポイント
複数の企業を比較検討する際、以下のようなポイントを意識すると数字の意味が見えてきます。
・同業種・同規模の企業同士で比較する:たとえばベンチャーと老舗メーカーでは前提が異なるため、直接比較は避けるべきです。
・上場・非上場の違いに留意する:上場企業は公開義務がある一方、非上場企業は任意なので、データの正確性や更新頻度に差が出ます。
・設立年や従業員の平均年齢を加味する:設立5年以内の企業は、そもそも長期在籍の社員がいない可能性もあります。
・数字だけでなく「中の声」を見る:OpenWorkや転職会議といった口コミサイトを参考に、「なぜ辞めたのか」「続いている理由は何か」といった定性的な情報も得ましょう。
退職金制度や離職率など他の指標とあわせて判断しよう

平均勤続年数だけに頼るのではなく、次のような指標を組み合わせて総合的に判断することで、より現実に近い企業の姿が見えてきます。
・離職率(1年以内・3年以内):短期間での離職が多ければ、ミスマッチや過剰労働があるかもしれません。
・退職金制度の有無:長期的な雇用を前提とした制度があるかどうかは、企業の人材戦略を読み解くカギになります。
・教育・研修制度の充実度:社員の成長を企業がどう支援しているかは、定着率に直結するポイントです。
・昇進スピードや評価制度の透明性:「評価が不透明で先が見えない」と感じる職場では、長くはたらきにくい傾向があります。
また、入社後のキャリアステップや異動の可能性、転勤の有無なども含めて、自分のライフスタイルや価値観に合ったはたらき方ができるかを確認することが大切です。
転職先を選ぶ際にチェックすべきポイントや、信頼できる転職サービスを知りたい方はこちらの記事も参考にしてみてください。
▶︎ 本当におすすめしたい転職サイト・転職エージェント10選【職業別にも紹介】
勤続年数に関するよくある質問【Q&A】

Q. 企業の勤続年数はどこで確認できる?
以下の情報源で確認できます。
・有価証券報告書:上場企業の平均勤続年数が記載されています
・会社四季報:全国の上場企業のデータを網羅
・OpenWork、キャリコネなどの口コミサイト
・企業の採用ページ・IR情報
Q. 3年以内の退職は転職で不利になる?
一概に不利とは言えません。重要なのは「辞めた理由」と「その後のキャリアプラン」です。目的や成長の意図が明確であれば、採用側も理解を示すケースが増えています。
Q. 平均勤続年数が短いとブラック企業?
短い理由によります。成長中の企業や若手が多い企業では、自然と平均が短くなる傾向があります。定着支援や育成制度の有無をあわせて確認しましょう。
Q. 平均勤続年数と離職率、どちらを重視すべき?
どちらも大事ですが、離職率の方が“直近の実態”を表すことが多いため、両方の数字をあわせて判断するのがベストです。
まとめ|平均勤続年数を正しく理解して、自分に合った企業選びを
平均勤続年数は、企業の実態を知るための有力な手がかりです。ただし、数字の大小だけで企業の良し悪しを判断するのではなく、業界特性や企業の風土、制度など、背景を理解する視点が求められます。
就活や転職活動を進めるうえで、企業の情報を多角的にチェックし、「自分が納得してはたらける環境」を見つけることが最も大切です。
企業選びに悩んだり、長期ではたらくことに不安を感じている方には、スキマ時間にはたらけるシェアフルの活用もおすすめです。正社員としてのはたらき方を検討しながら、まずは自分に合った職場環境を体験したい方にもぴったり!ぜひ、あなたの新しいはたらき方の選択肢としてチェックしてみてください。