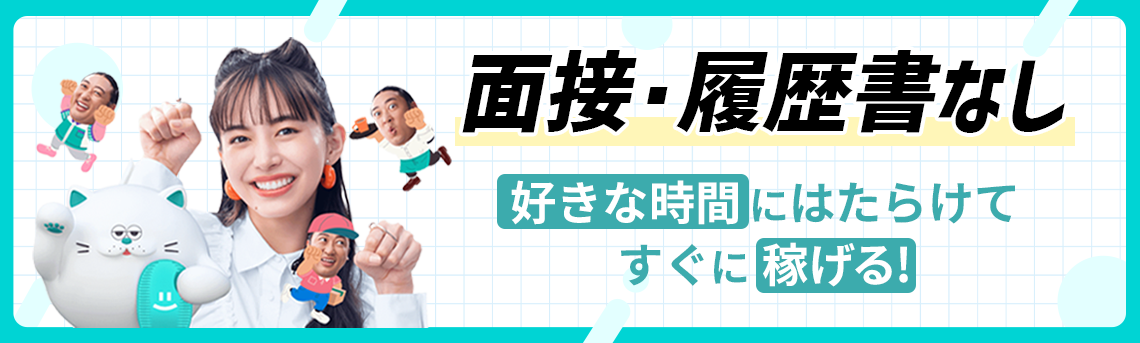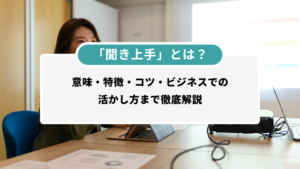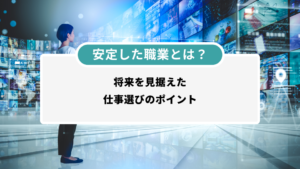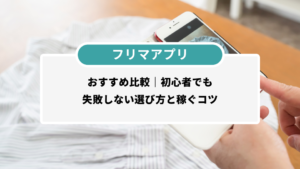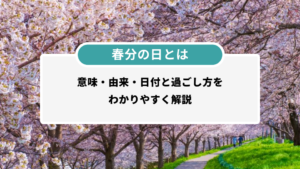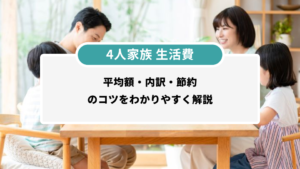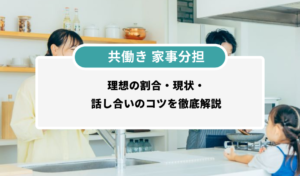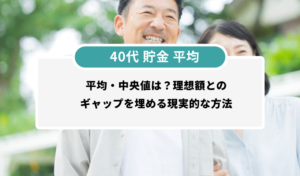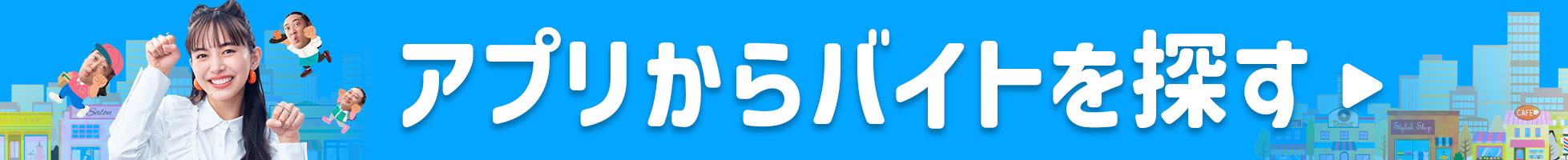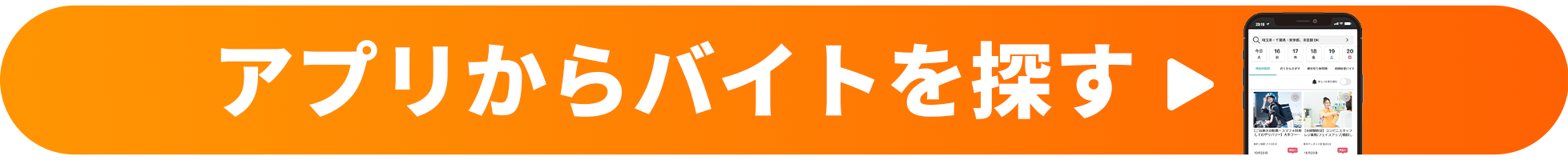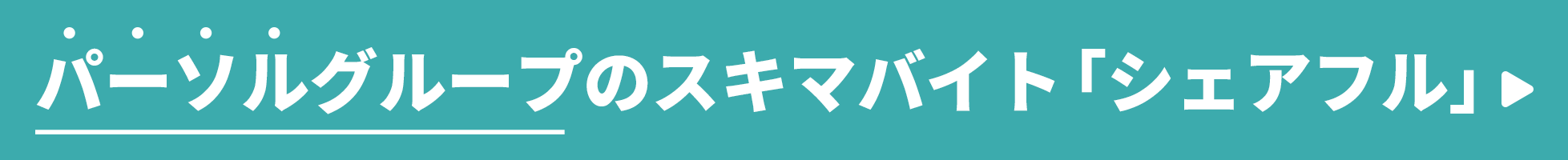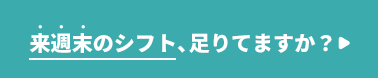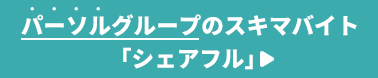【2026年最新版】お彼岸とは?意味・由来・2025年の日程と過ごし方を徹底解説
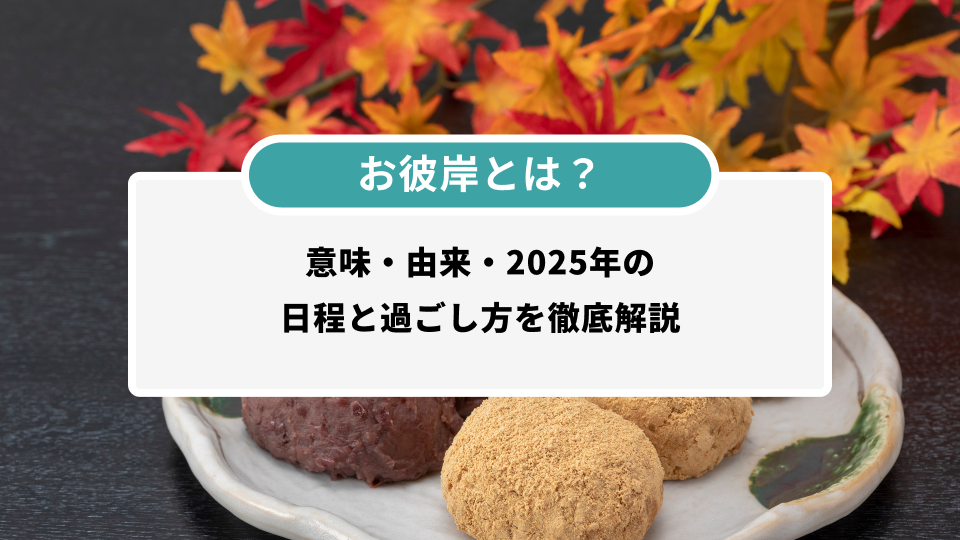
2025年のお彼岸はいつ?【2025年カレンダー付き】

お彼岸とは、春分の日と秋分の日を中日として、その前後3日間を合わせた各7日間のことを指します。2025年(令和7年)の春と秋のお彼岸は以下の通りです。
- 春のお彼岸(2025年)
- 彼岸入り:3月17日(月)
- 中日(春分の日):3月20日(木・祝)
- 彼岸明け:3月23日(日)
- 彼岸入り:3月17日(月)
- 秋のお彼岸(2025年)
- 彼岸入り:9月20日(土)
- 中日(秋分の日):9月23日(火・祝)
- 彼岸明け:9月26日(金)
- 彼岸入り:9月20日(土)
春分・秋分の日は国民の祝日であり、春分は「自然をたたえ、生物をいつくしむ日」、秋分は「祖先を敬い、亡くなった人をしのぶ日」として制定されています。カレンダー上でも季節の節目となる重要な日であり、令和7年のお彼岸も家族やご先祖を敬う行事として多くの人が意識する時期です。
お彼岸の意味と由来

お彼岸の意味と成り立ち
「彼岸」という言葉は、仏教に由来します。サンスクリット語の「パーラミター(波羅蜜多)」が漢訳され、「彼岸=悟りの境地」と解釈されたものです。現世を「此岸(しがん)」と呼び、苦しみや迷いの世界を表します。対して「彼岸」は悟りの世界であり、迷いや苦悩から解放された安らぎの境地です。
「彼岸」と「此岸」の意味
- 此岸(しがん):生きている私たちが暮らす現世
- 彼岸(ひがん):仏の教えに従い、悟りを得た理想の世界
このように「彼岸」と「此岸」は対になる言葉であり、春分・秋分の太陽が真西に沈む時期は、此岸と彼岸がもっとも近づくと考えられてきました。
仏教的な背景と日本文化への定着
お彼岸はインドや中国にはなく、日本独自の仏教行事です。仏教の教えと、日本人の自然崇拝・祖先崇拝が融合する形で根づきました。春分・秋分の日は昼と夜の長さが等しく、自然のバランスが整うとされるため、ご先祖を供養する風習が広がったのです。
お彼岸にすること・過ごし方

お墓参りの意味とマナー
お彼岸といえばお墓参りが代表的な行事です。墓石を清掃し、花や線香、供物を供えて手を合わせます。マナーとしては、まず墓石の周囲を掃き清め、墓石をやさしく洗い、清浄な状態にしてからお供えをします。供花は季節の花を選ぶと良いとされ、故人の好物を供えるのも一般的です。
お彼岸の食べ物(ぼたもち・おはぎ)
お彼岸に欠かせない食べ物が「ぼたもち」と「おはぎ」です。
- 春は牡丹の花にちなんで「ぼたもち」
- 秋は萩の花にちなんで「おはぎ」
と呼び分けられます。小豆の赤色には魔除けの意味があり、先祖への供養としてふるまわれてきました。(「ぼたもち/おはぎ」は地域や家庭で呼び分けており、粒あん/こしあんの違いなど諸説あります。)
供養や法要について
家庭での供養のほか、寺院で法要を営むこともあります。僧侶を招いて読経をしてもらい、親族で参列するのが一般的です。近年はオンラインでの法要や、遠方の親族が参加しやすい形式も増えています。
お彼岸にやってはいけないこと

お墓参りのNG行為
- 墓石に登ったり腰掛けたりする
- 他人のお墓に供え物をする
- 墓地で大声や喫煙をする
こうした行為は不適切とされ、敬意を欠くものとして避けましょう。
不適切な供物や行動
生肉や魚など「殺生を連想させるもの」を供えるのは不適切です。また、供花も棘のある花は避け、菊や季節の花を選ぶのが無難です。アルコールなどは個人の好物として備える慣習もあるため、各宗派・墓苑規約に従うようにしましょう。
仏教的観点で避けられる行為
お彼岸はご先祖を敬う期間であるため、殺生や過度な娯楽は慎むべきとされています。賭け事や大騒ぎする宴会などは控え、静かに過ごすことが推奨されます。
お彼岸にまつわる豆知識

彼岸花と季節感
お彼岸の時期に咲く花として有名なのが彼岸花です。真紅の花が田畑や墓地の周辺に咲き、先祖供養の象徴とされています。花言葉は「情熱」「再会」「あきらめ」など。季節を象徴する花として文学作品にも多く登場します。
「彼岸」という言葉の文化的広がり(例:彼岸島)
「彼岸」という言葉は宗教的な意味だけでなく、文学やエンタメにも使われます。例えば漫画『彼岸島』はホラー作品として有名ですが、「彼岸=死や異世界」というイメージを借用した表現です。こうした文化的広がりも「彼岸」の奥深さを物語っています。
暦とお彼岸(春分・秋分との関係)
春分・秋分は二十四節気のひとつで、季節の大きな節目にあたります。昼と夜の長さが同じになるこの時期は、自然のバランスが整うとされ、古来より重要視されてきました。お彼岸は暦と深く結びついた日本独自の行事といえます。
現代のお彼岸の工夫
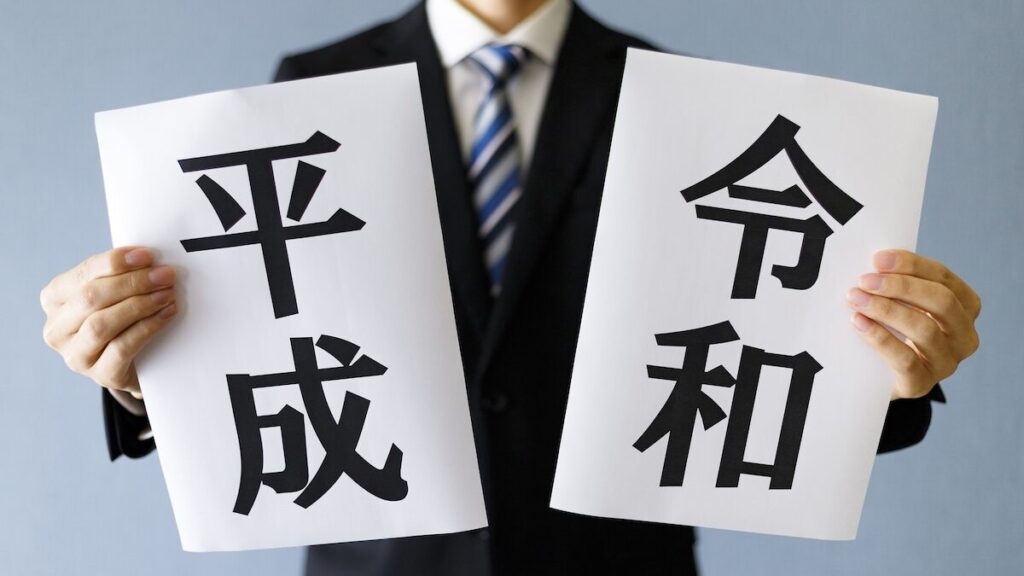
帰省できない場合の供養(オンライン法要・花の配送)
近年ははたらき方の変化や距離の問題から、お墓参りや法要に参加できない人も増えています。その場合は、オンラインで僧侶に読経を依頼したり、花屋から墓地に直接花を配送してもらうサービスを活用できます。デジタル時代ならではの供養方法です。
忙しい人向けチェックリスト
- 供花の手配
- 線香・ろうそくの準備
- 故人の好物を供える
- 墓石の清掃道具(桶・タオル・ブラシ)
- 服装の確認(派手すぎないもの)
短時間でも最低限の準備をして臨めば、十分に供養の気持ちを表すことができます。
お彼岸シーズンを活用したはたらき方

お彼岸時期に需要が増えるしごと(花屋・墓地清掃・飲食店など)
お彼岸は供花や供物の需要が高まり、花屋や和菓子店が繁忙期を迎えます。また、墓地清掃や霊園管理のしごとも増えるほか、親族が集まるため飲食店の利用も増加します。この時期は短期的にはたらく機会が増えるシーズンでもあります。
シェアフルを活用したスキマ時間の有効活用
スキマ時間ではたらきたい人には、単発・短期のしごとが探せるアプリ「シェアフル」の活用がおすすめです。お彼岸シーズンには花屋の補助、飲食店のホールスタッフ、清掃作業などの求人が増えるため、空いた時間を有効に活かせます。アプリから簡単に応募でき、柔軟なはたらき方ができる点も魅力です。
まとめ

お彼岸は、日本独自の仏教行事としてご先祖を敬い、自然を感じる大切な期間です。2025年は春分が3月20日、秋分が9月23日であり、それぞれ前後3日間を含む一週間が「お彼岸」となります。お墓参りや供養、ぼたもちやおはぎを供えるなど、昔から続く風習を守ることで、心の安らぎや家族の絆を深めることができるでしょう。
現代ではオンライン法要や花の配送など、新しい供養の形も生まれています。さらに、この時期は花屋や清掃など季節需要が高まるしごともあり、シェアフルを活用することで効率的なはたらき方も可能です。
お彼岸をきっかけに、ご先祖や家族とのつながりを見直し、自然の恵みに感謝する心を大切にしてみてはいかがでしょうか。