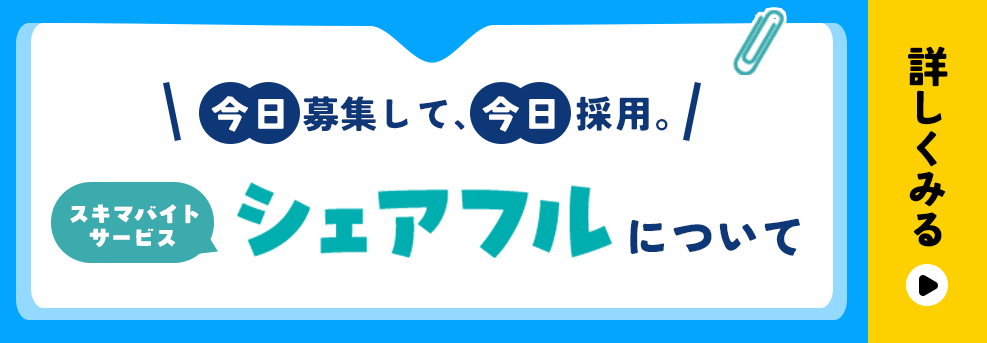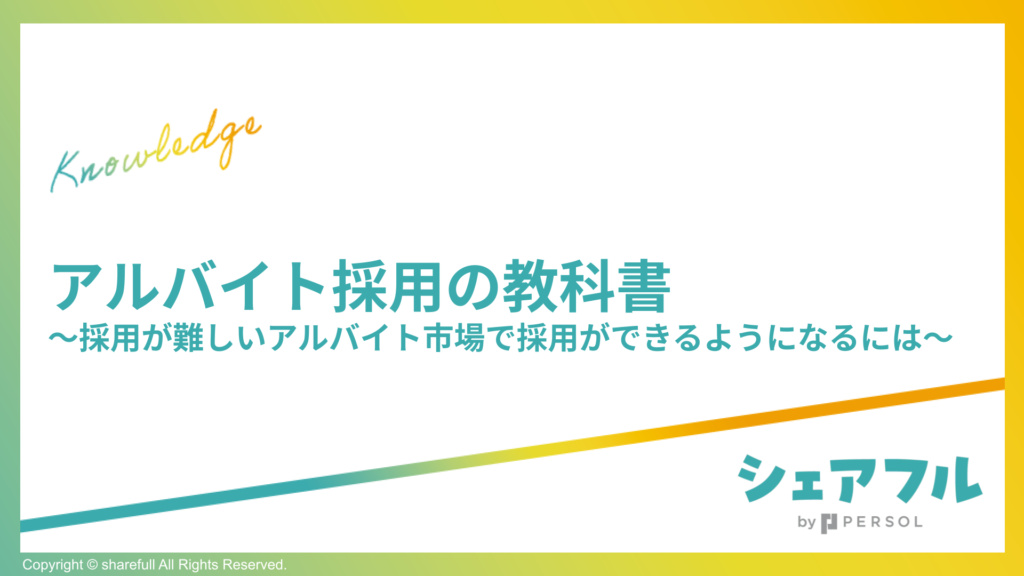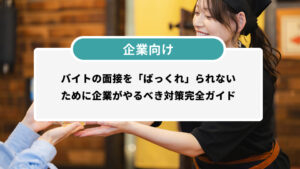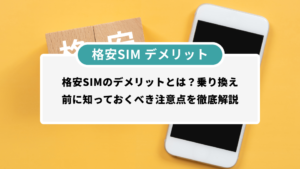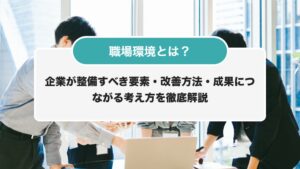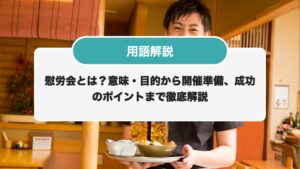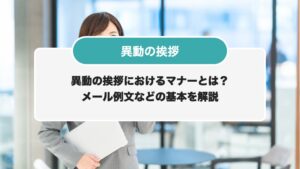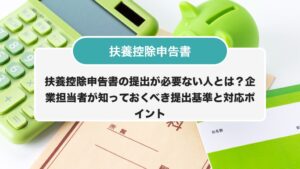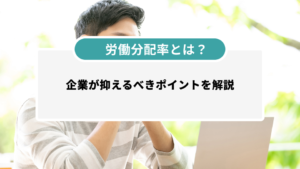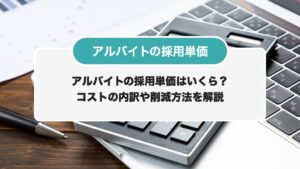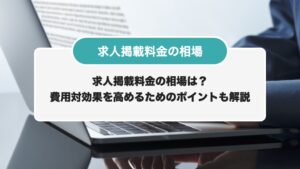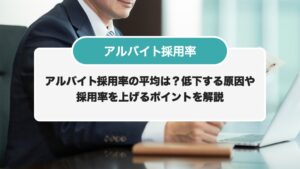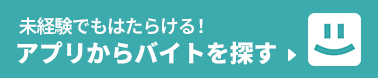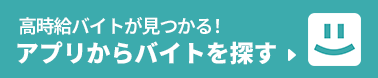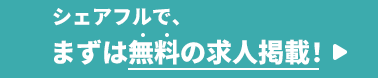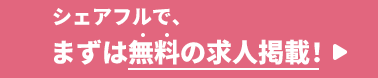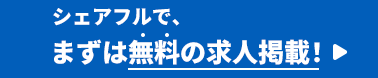【2025年最新版】週30時間を超えたり超えなかったりする従業員は社会保険加入が必須?企業担当者が判断すべき内容を解説
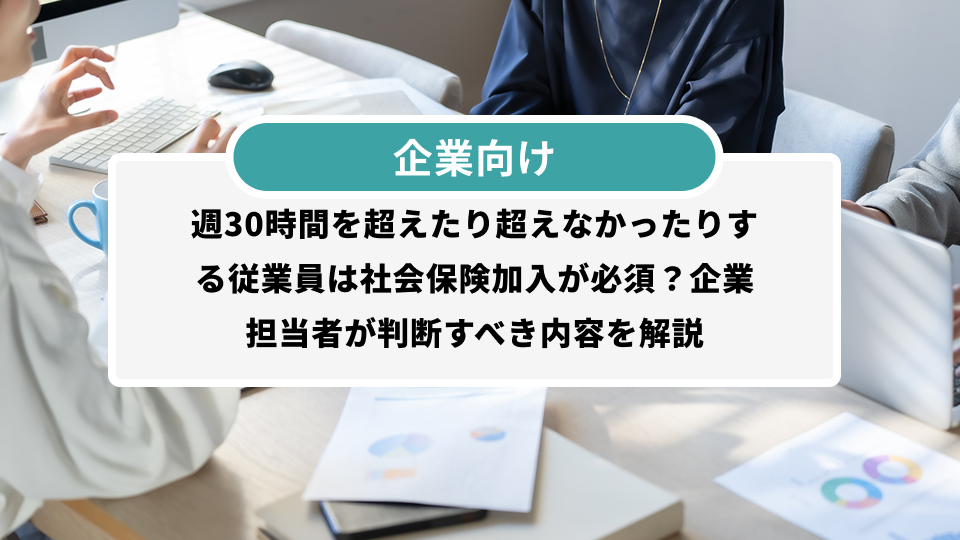
企業の人事・労務担当者にとって、労働時間が週30時間を超えたり超えなかったりする従業員(パート・アルバイト・短時間の雇用形態など)に社会保険(健康保険・厚生年金保険)を適用すべきか、いつ被保険者資格の取得や喪失の手続きが必要かという判断は、採用・配置・勤怠・給与計算・就業規則の運用に直結する最重要テーマです。本記事は、制度の原則と最新動向をふまえつつ、企業側の実務に必要な要件・判断軸・ケース別の考え方・標準報酬や社会保険料の取り扱い・遡及リスク・管理システム運用までを、具体例とチェックポイントを交えて詳しく解説します。
「アルバイト採用を始めたい」「アルバイト採用をしているが、今の方法が正しいか不安」とお考えの方は少なくありません。
レポートでは、「アルバイトとパートの違い」「採用までの流れ」「採用手法」の他、「アルバイト採用コストを下げる方法」などをまとめています。アルバイト採用にお困りの方はぜひご活用ください。
結論:労働時間が週30時間を超えたり超えなかったりする場合、社会保険への加入は雇用契約書の内容によって決まる

まず大前提として、加入要否の一次判断は週の実労働時間の一時的な増減ではなく、雇用契約書や就業規則で定めた週の所定労働時間を主軸に行います。いわゆる4分の3基準(通常の正社員の所定労働時間に対し4分の3以上)を満たす所定労働時間であれば、従業員は原則として被保険者となり、企業には資格取得の手続き義務が発生します。逆に、週によって30時間を超えたり超えなかったりする実労働時間の揺らぎがあっても、所定労働時間が変わらない限り、その都度資格取得・喪失を繰り返すことにはなりません。
一方、短時間労働者に対する適用拡大の枠組みも重要です。所定労働時間が30時間未満であっても、週20時間以上・月額賃金(所定内賃金)8.8万円以上・雇用期間や事業所の規模といった要件に該当するなら、短時間の適用枠で加入対象となり得ます。さらに、契約上は20時間未満で社会保険の対象外としていたとしても、実労働時間が2か月連続で週20時間以上となり、引き続き継続見込みがある場合には、3か月目の初日に資格取得となる運用が明確化されています。つまり、企業の判断は「所定労働時間」を原則としつつ、「連続」と「見込み」によって実態が変わったと評価されるケースも見逃さない、二段構えで行う必要があります。
採用や配置の見直し、業務の繁閑にともなう残業・増員の判断、人材の育成計画など、事業の運用と社会保険の適用は密接に関係します。制度の理解とあわせて、勤怠と給与のデータを一元管理し、対象者の変化を早期に把握できる体制を整えることが、企業側のリスク最小化とコスト最適化に直結します。
[参考]
厚生労働省「社会保険適用拡大特設サイト」https://www.mhlw.go.jp/tekiyoukakudai/koujirei/jugyouin/
社会保険加入の基本要件と判断軸
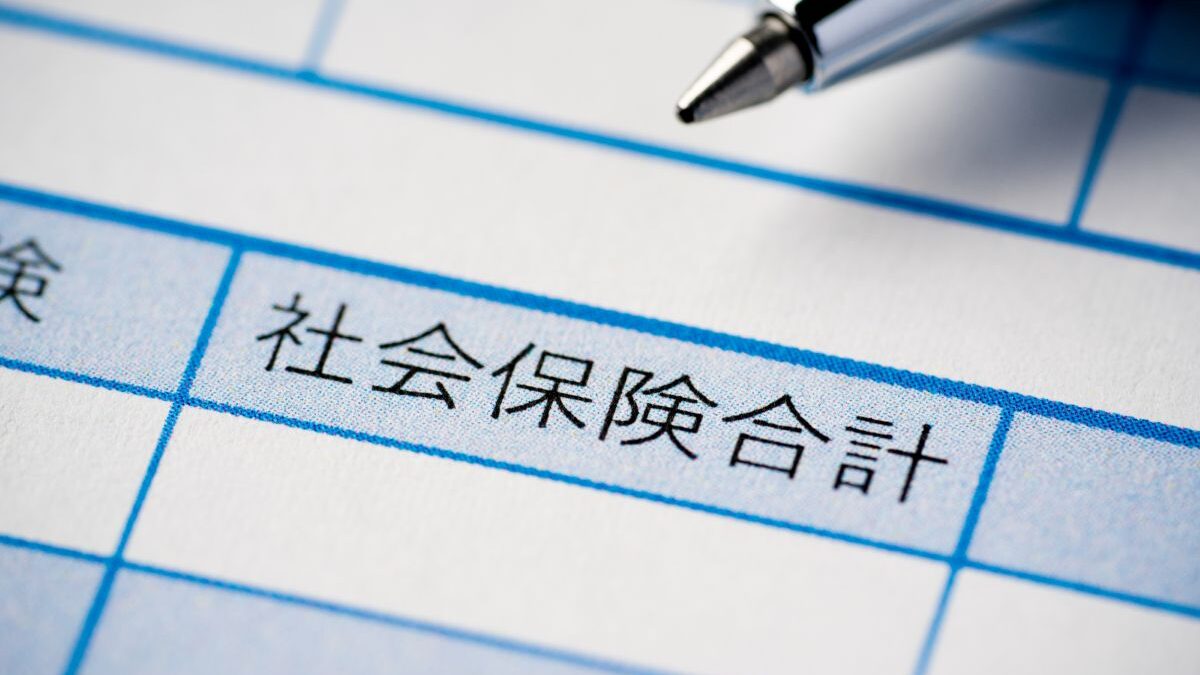
所定労働時間と実労働時間:判断基準の整理
所定労働時間は、就業規則・雇用契約で定めた基準時間です。加入の原則判断は所定労働時間に基づきます。残業や臨時の勤務延長により実労働時間が一時的に増えても、ただちに資格取得・喪失を繰り返すわけではありません。したがって、日々の勤務の増減を理由に手続きを行う必要はなく、所定労働時間の変更や就業規則の改定があった場合に、対象者の見直しを行います。もっとも、所定労働時間と実態の乖離が常態化する場合には、契約の見直しが必要です。
4分の3基準は、事業所の通常の労働者(多くは正社員)の所定労働時間に対して4分の3以上であるかを判断する目安で、週40時間制の企業であれば30時間が概ねの目安になります。ここでいう通常とは、個別の繁忙や一時的な増員ではなく、一般的な勤務の基準を指します。
加入義務発生の要件一覧
加入義務は次の観点で総合判断します。
- 週の所定労働時間が20時間以上(時間外労働は除く)であること
- 給与が月額8.8万円以上(残業代・賞与・通勤手当・臨時の手当は除く)であること
- 継続して2か月を超える雇用が見込まれること
- 学生ではないこと(夜間・休学中・定時制・通信制は加入対象)
※ただし、従業員数が51人以上の企業が対象となります。
これらを「対象」「該当」「対象外」に仕分けし、対象者リストを常時更新しておくことが、労務管理の効率化に寄与します。
週30時間を超えたり超えなかったりするケースの扱い
一時的に30時間を超えるケース
残業や臨時の応援勤務で一時的に週30時間を上回っても、直ちに資格取得の義務が発生するわけではありません。判断は所定労働時間が中心です。もっとも、一定期間にわたり30時間超が連続するなど、所定上の想定を明らかに超えた勤務が常態化している場合は、雇用契約や就業規則の見直しを検討します。所定労働時間の見直しにともない、標準報酬の決定や社会保険料の再計算、給与計算システムの設定変更が必要となる可能性があるため、担当者は早めに準備しましょう。
実務上「超えたり超えなかったり」する月がある場合
繁忙期と閑散期の差が大きい事業では、月ごとに所定労働時間未満と所定労働時間以上の週が混在し、30時間付近を行き来することがあります。ここでも原則は所定労働時間が基準ですが、2か月・3か月など一定期間で見たときに、20時間や30時間のラインを継続的に上回る実態が認められるなら、契約の見直しや短時間枠の加入判定を行います。見直しの際には、雇用契約書の更新、本人への説明と同意、就業規則の改定手続き、労働条件通知書の作成・配布といった実務を、期限内に完了させることが重要です。
契約労働時間を変動型とするケース(変形労働時間制)
季節変動の大きい業務では、所定労働時間の範囲を上下幅で定義する「変形労働時間制」の雇用契約を採用するケースがあります。この場合、上限・下限の幅が過大だと実態との乖離が生じ、短時間枠の要件を満たしているにもかかわらず手続きが遅れるなどのリスクが増します。変動幅の設計は、所定内賃金の見通し、月額賃金の変動、標準報酬の随時改定の可能性、年間の繁閑パターンなどを加味して、管理と説明が可能な範囲に設定しましょう。
参照:厚生労働省 徳島労働局「変形労働時間制」https://jsite.mhlw.go.jp/tokushima-roudoukyoku/hourei_seido_tetsuzuki/roudoukijun_keiyaku/hourei_seido/jikan/henkei01.html
所定労働時間未満で設計された契約だが実労働時間が多いケース
所定労働時間を意図的に低く設定して適用を回避する設計は、実態との乖離が常態化すれば加入義務が発生し、遡及リスクにも直結します。特に、契約は20時間未満としながら実績が2か月連続で20時間以上となり、以降も継続見込みがある場合は、3か月目からの資格取得が必要です。企業側は、勤怠と給与のデータを突合し、短時間枠の要件に該当する可能性を早期に把握できるダッシュボードを用意するなど、管理の具体化が求められます。
参照:日本年金機構「就業規則や雇用契約書等で定められた所定労働時間は週20時間未満ですが、業務の都合等により恒常的に実際の労働時間が週20時間以上となった場合は、どのように取り扱うのですか。」https://www.nenkin.go.jp/faq/kounen/tekiyoukakudai/tanjikan/roudoujigan.html
週20時間を超えたり超えなかったりするケースの扱い

たとえば、雇用契約書上の週の所定労働時間が20時間以上で社会保険に加入している従業員が、繁閑により20時間未満の週がときどき発生しても、直ちに資格喪失とはなりません。逆に、契約上は20時間未満で対象外としつつ、繁忙期に20時間以上が続くなら、短時間枠の適用に該当する可能性が生じます。学生は一般に短時間枠の対象外ですが、休学・定時制・通信制など例外があるため、属性の確認を怠らないでください。
制度は法改正によって適用範囲が拡大してきました。一定の事業所規模(例:従業員数51人以上)への段階的な拡大が行われ、将来的には企業規模要件や賃金要件(月収8.8万円)の撤廃方向が議論されています。事業所の規模・雇用期間・雇用形態に応じた適用判断を、最新の法改正情報に照らして継続的に見直しましょう。
参照:厚生労働省「社会保険の加入対象の拡大について」
https://www.mhlw.go.jp/stf/seisakunitsuite/bunya/0000147284_00021.html
加入義務を怠った場合のリスクと罰則

保険料の追徴と利息
加入の起算日に遡って社会保険料(健康保険・厚生年金保険料)を再計算し、労使折半の負担を精算する必要が生じます。標準報酬の決定・随時改定・定時決定の履歴を点検し、月額賃金や所定内賃金、賞与の取り扱いが適切であったか、控除処理に漏れがないかを確認します。遡及期間が長いほど金額負担が増え、給与計算のやり直し・本人への説明・同意取得・差額控除の分割計画など、実務の負担も拡大します。
参照:日本年金機構「厚生年金・健康保険などの適用促進に向けた取り組み」https://www.nenkin.go.jp/service/kounen/info/torikumi/20150120.html
事業主・従業員への行政上・法的リスク
健康保険法・厚生年金保険法に基づく行政指導・勧告や、従業員からの苦情・紛争リスクが高まります。加入漏れが長期間放置されると、損害の発生や団体交渉・訴訟等の可能性も否定できません。早期の是正と、以降の再発防止策(判定フローの明文化、責任者の特定、システムのアラート設計)が必要です。
実務対応の流れと管理ポイント

制度の理解だけでなく、日々の運用に落とし込むためのフローと管理ポイントを示します。
勤怠・勤務時間記録の管理体制
まず、出退勤の打刻、休憩の付与、残業の事前申請・事後承認、休日・祝日の扱いを、システムで一元化します。週単位のダッシュボードで20時間・30時間の目安に近づく従業員を自動抽出し、担当者へアラートを通知します。勤怠データと給与計算の連携により、標準報酬の決定・随時改定・定時決定に必要なデータを自動集計できる体制を整えましょう。
従業員の適用該当チェックフロー
判定は、入社時、契約更新時、シフト変更時、賃金テーブルの改定時に実施します。週の所定労働時間、所定労働日数、雇用期間、月額賃金(基本給と手当の内訳)、学生か否か、扶養の状況などを一覧で確認し、該当・対象外・保留(要見込み確認)に仕分けます。短時間枠に関しては、2か月連続20時間以上かどうか、以降の見込みがあるかを、シフト計画や受注見通しから具体的に把握します。チェックの記録は管理システムに登録し、回答履歴や承認のログを残すことで、監査対応を容易にします。
被保険者資格取得・喪失の手続き
資格の取得・喪失・氏名変更・賞与支給届など、提出書類と期限を一覧化し、電子申請を基本運用にします。提出前チェックリストには、雇用契約のコピー、労働条件通知書、源泉控除や住民税の変更、標準報酬決定・改定の根拠、本人への周知・同意の履歴を含めます。提出の遅延や記入誤りは、後の差戻しや保険料計算の齟齬につながるため、担当者の交代時にも品質が維持できる標準手順書(SOP)の整備が重要です。申請の完了後は、人事部・現場責任者・経理への周知をテンプレート化し、関係者の理解を促します。
契約書・就業規則の見直し・改定
所定労働時間の定義、変動型契約の上限・下限、固定残業代の有無と計算方法、手当の範囲、所定内賃金に含める項目、雇用期間の更新基準、対象者への周知方法を明記します。変更時は、労働条件の不利益変更の有無を精査し、双方の同意、運用ルールの文書化、周知、施行日の明記、公開日の管理を徹底します。変更後は、勤怠の推移を追い、短時間枠の該当有無を継続監視してください。
最新の法改正・適用拡大動向

2025年6月20日に、「社会経済の変化を踏まえた年金制度の機能強化のための国民年金法等の一部を改正する等の法律案」が公布されました。これにより、今後は社会保険の加入対象が拡大していくこととなります。
現行の社会保険加入対象
適用事業所の正社員または、適用事業所のうち従業員51人以上の企業等にて労働する者で、以下4つの条件全てに当てはまる従業員。
- 週の所定労働時間が20時間以上(時間外労働は除く)であること
- 給与が月額8.8万円以上(残業代・賞与・通勤手当・臨時の手当は除く)であること
- 継続して2か月を超える雇用が見込まれること
- 学生ではないこと(夜間・休学中・定時制・通信制は加入対象)
法改正の内容
1.短時間労働者の企業規模要件を縮小・撤廃
短時間労働者が週20時間以上はたらいた場合、企業規模にかかわらず社会保険加入対象となります。10年かけて段階的に縮小・撤廃され、直近は2027年10月に「従業員36人以上」の企業が加入対象となります。
2.短時間労働者の賃金要件を撤廃
給与が月額88,000円以上であるという条件が撤廃されます。撤廃時期については、公布から3年以内に全国の最低賃金の引き上げ状況を見て判断されます。地域別最低賃金の最低額が1,016円となると、週20時間はたらいた場合に月額88,000円となるためです。
3.個人事業所の適用対象を拡大
現行の法律では、「常時5人以上の者を使用する法定17業種(※)」の事業所は、必ず社会保険に加入することとされています。しかしながら、2029年10年の施行以降は全業種が対象となります。(なお、2029年10月の施工時点で既に存在している事業所は、当分の間対象外となります。)
※法定17業種:
物の製造、土木・建設鉱物採掘、電気、運送、貨物積卸、焼却・清掃、物の販売、金融・保険、保管・賃貸、媒介周旋、集金、教育・研究、医療、通信・報道、社会福祉、弁護士・税理士・社会保険労務士等の法律・会計事務を取り扱う士業
参照:厚生労働省「社会保険の加入対象の拡大について」
https://www.mhlw.go.jp/stf/seisakunitsuite/bunya/0000147284_00021.html
ケース別モデル計算・シミュレーション

ここでは、企業側の負担(社会保険料)と従業員の手取りへの影響をイメージできるよう、代表的な2パターンを示します。金額はあくまで概算であり、料率・標準報酬の等級・事務所の加入団体等により変動します。
例1:所定労働時間32時間/週 → 一部の月で28時間に減るパート
このケースでは、所定労働時間が4分の3基準(週30時間相当)を上回っており、被保険者の資格は維持されます。ある月に実労働が28時間に減っても、一時的な変動であれば資格喪失は生じません。給与計算では、標準報酬の決定と随時改定の要件(固定的賃金の変動)に該当するかを慎重に確認し、必要があれば翌月以降の社会保険料の控除額を調整します。
例2:契約は28時間だが、実績が32時間に増える月が連続
契約上は30時間未満のため4分の3基準は未達ですが、実労働時間が2か月連続で20時間以上となり、以降も継続見込みなら、3か月目から短時間枠での加入が必要です。企業は、該当者の雇用契約を現実に合わせて見直し、所定労働時間の定義・所定労働日数・手当の範囲・残業の取扱いを明文化します。遡及が生じる場合には、社会保険料の追徴・控除スケジュールを本人と合意し、控除方法(複数回分割など)を文書化して周知します。さらに、被扶養者の有無や年収見込みの変化があれば、扶養の見直しや国民年金から厚生年金への切り替えなど、関連する手続きも同時に検討してください。
なお、標準報酬の決定・改定、随時改定、定時決定の判定は、月額賃金の変動幅や固定的賃金の変更が鍵です。手当の新設・廃止、基本給の改定、職種の変更、所定労働時間の変更など、給与テーブルの更新時には、社会保険のルールへの影響を必ずチェックしましょう。
よくある質問(FAQ)
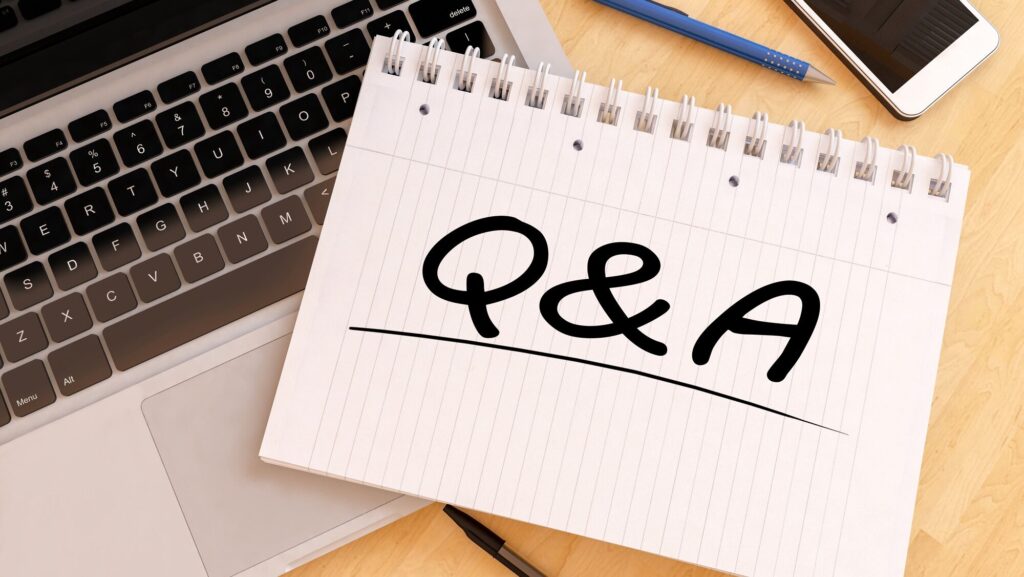
たまたま月に1度だけ週30時間を超えても加入義務は発生する?
一時的な超過で直ちに資格取得とはなりません。加入判定の原則は所定労働時間です。ただし、その状態が連続し、今後も継続見込みが強い場合は、所定労働時間の見直しや短時間枠の適用判定を行いましょう。
就業時間が短くなった場合はどうなる?
所定労働時間が変わらない限り、原則として資格喪失には直結しません。所定労働時間の変更を行う場合は、就業規則の改定、本人説明・同意、給与計算システムの設定変更、標準報酬の等級見直しといった手続きを、期限内に完了させてください。
加入義務が発生したかどうか判断できないときはどうすればいい?
短時間枠の2か月連続・3か月目ルール、4分の3基準、学生の扱い、事業所規模の要件、月額賃金の水準などをチェックリスト化して確認します。曖昧なケースは、社会保険労務士等の専門家に相談するか、所轄の事務所・年金機構窓口に照会し、記録(参照資料・回答・時点)を残しておくとよいでしょう。
契約変更で所定労働時間を下げてもいい?
実態との乖離を目的とした変更は望ましくありません。不利益変更の有無を精査し、双方の同意、運用ルールの文書化、周知、施行日の明記、公開日の管理を徹底します。変更後は、勤怠の推移を追い、短時間枠の該当有無を継続監視してください。
加入漏れが発覚したらどう対応すればよい?
まず対象者と起算日を確定し、標準報酬・保険料を再計算します。遡及の期間と金額を本人へ説明し、控除の方法と回数について合意します。提出書類を準備し、電子申請を行い、社内の関係部署(人事部・経理・拠点管理者)に周知して再発防止策を共有します。
変動勤務で保険料計算が煩雑になるがどう管理する?
勤怠・給与・社会保険のデータを管理システムで連携させ、20時間・30時間・月額賃金の目安に近づいた時点で担当者にアラートを出す設計にします。年間の等級推移と手取りの影響を可視化し、比較資料を定例会議でレビューすると、意思決定が迅速になります。
「アルバイト採用を始めたい」「アルバイト採用をしているが、今の方法が正しいか不安」とお考えの方は少なくありません。
レポートでは、「アルバイトとパートの違い」「採用までの流れ」「採用手法」の他、「アルバイト採用コストを下げる方法」などをまとめています。アルバイト採用にお困りの方はぜひご活用ください。
まとめ

本記事では、週30時間のラインを中心に、所定労働時間と実労働時間、4分の3基準、短時間枠の2か月連続・3か月目ルール、企業規模や月収要件、学生の扱い、遡及リスク、標準報酬と保険料の計算方法、手続きの提出・完了まで、企業側の実務に必要な要点を一気通貫で整理しました。制度は今後も改正・拡大が見込まれるため、最新の公表情報に合わせた就業規則・雇用契約・運用ルールの見直しを継続してください。