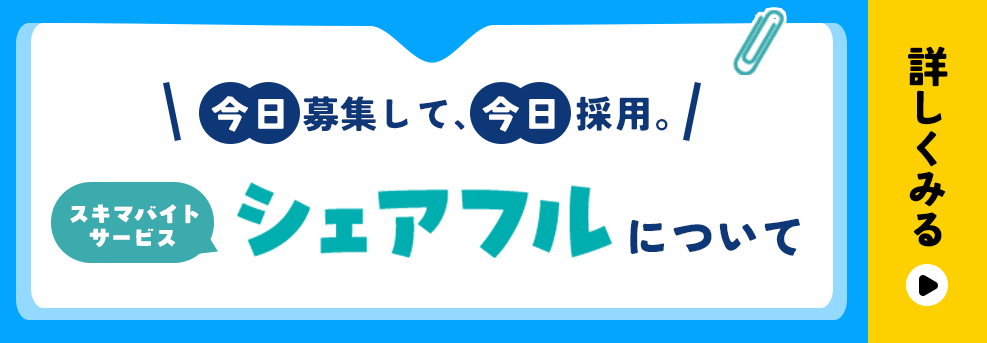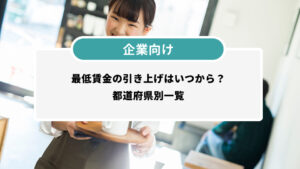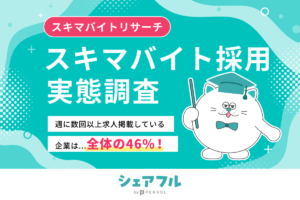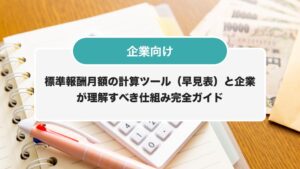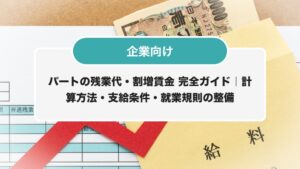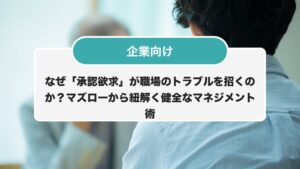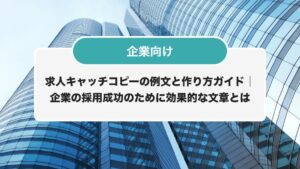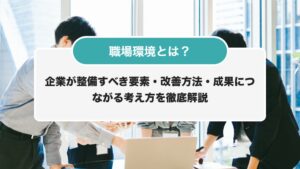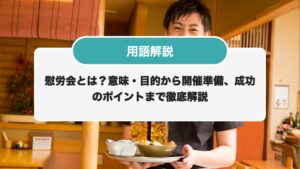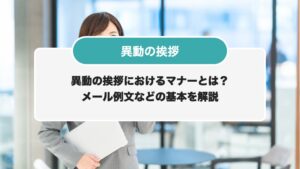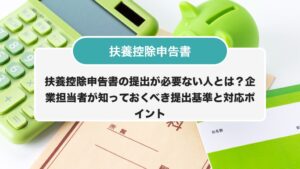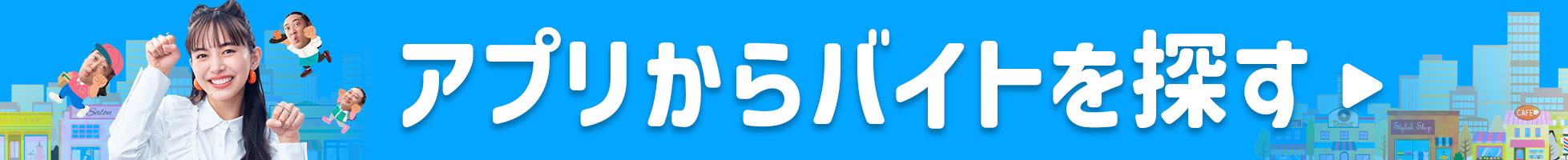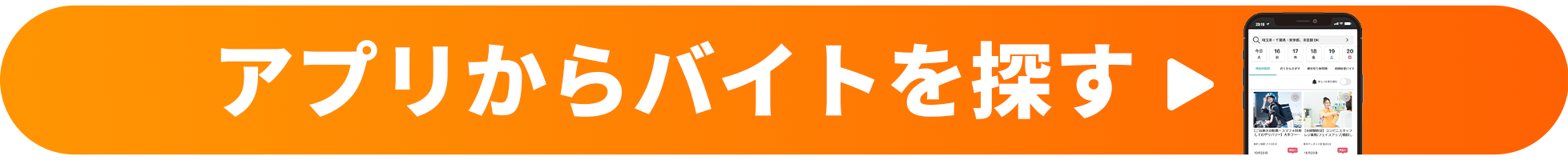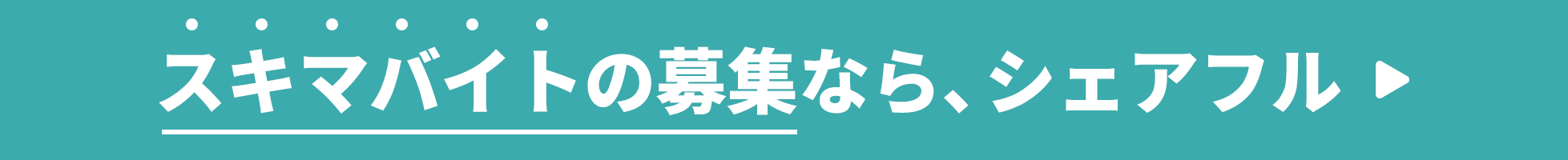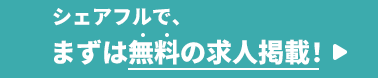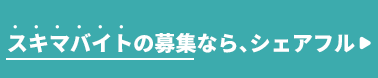【企業向け】スキマバイトを併用する際の注意点やリスク・対応策を解説
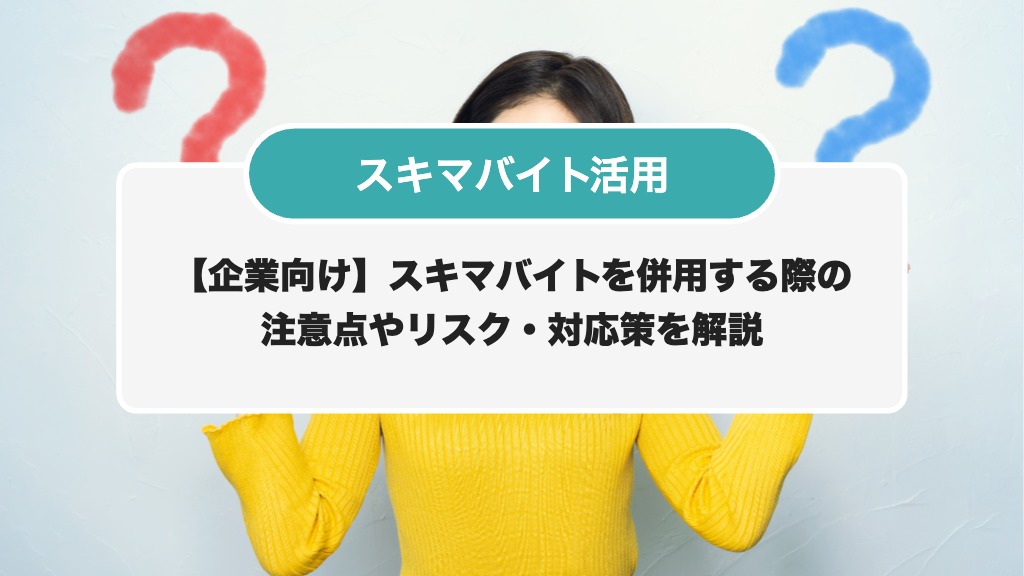
近年、飲食店や小売業を中心に、短時間で勤務できる「スキマバイト」を活用する企業が急増しています。人材確保が難しい時期や、繁忙期などに即戦力のユーザーを採用できる点が大きな魅力です。
しかし「複数のスキマバイトサービスを利用して求人を出したい」という企業が増える一方で、併用には労務管理やデータ処理、応募管理などのリスクも潜んでいます。
この記事では、スキマバイトを併用する際の注意点や課題、併用によって発生するリスクとその対応策を、企業目線でわかりやすく解説します。
複数のスキマバイトを利用すると発生する可能性がある課題とリスク

スキマバイトの併用は、単発・短時間勤務の求人を効率的に集客できる一方で、企業側の管理業務が複雑化する傾向があります。
ここでは、併用によって起こりやすい課題や注意点を具体的に見ていきます。
労務管理の一体性が崩れるリスク:時間・収入の把握難
複数のスキマバイトサービスで人材を募集した場合、各サービスが独立して労働時間や報酬を管理するため、全体の勤務データを統合しづらくなります。
勤務データがサービスごとに独立している場合の注意点
1.社会保険加入対象となる可能性
同一企業で継続的な雇用をされているとみなされた場合、社会保険(健康保険・厚生年金保険)加入対象となる可能性があります。具体的に、社会保険加入対象となる条件は以下の4つです。
- 週の所定労働時間が20時間以上(時間外労働は除く)であること
- 給与が月額8.8万円以上(残業代・賞与・通勤手当・臨時の手当は除く)であること
- 継続して2か月を超える雇用が見込まれること
- 学生ではないこと(夜間・休学中・定時制・通信制は加入対象)
※ただし、従業員数が51人以上の企業が対象となります。
※参考:厚生労働省「社会保険適用拡大特設サイト」https://www.mhlw.go.jp/tekiyoukakudai/koujirei/jugyouin/
2.源泉徴収税額発生対象となる可能性
スキマバイトやスポットワークのように、給与を勤務した日または時間によって計算する場合、次のいずれかの要件に当てはまると、「給与所得の源泉徴収税額表」内、「日額表」の「丙欄」を使用して源泉徴収する税額が求められます。(同一企業での就業の場合)
- あらかじめ定められている雇用契約の期間が2か月以内であること。
- 日々雇い入れている場合には、継続して2か月を超えて支払をしないこと。
※参考:国税庁「No.2514 パートやアルバイトの源泉徴収」https://www.nta.go.jp/taxes/shiraberu/taxanswer/gensen/2514.htm
3.給与支払報告書提出(マイナンバー取得)対象となる可能性
同一企業による年間の給与支払額が30万円を超える場合、市区町村へ給与支払報告書の提出義務が発生します。なお、給与支払報告書にはマイナンバーの記載が必要なため、ユーザーにマイナンバーを提出してもらい、適切な安全管理措置を行う必要が発生します。
なお、年の給与等支払額が30万円以下で、スキマバイトのように退職済みの場合は提出を省略することができます。
※参考:国税庁「No.7411 「給与所得の源泉徴収票」の提出範囲と提出枚数等」https://www.nta.go.jp/taxes/shiraberu/taxanswer/hotei/7411.htm
ケース:複数のスキマバイトサービスで勤務データを管理した場合
源泉徴収・マイナンバー提出が必要になってしまう例
状況
- X社では、年間を通じて繁忙期と閑散期があり、スキマバイトサービスAとBを併用して求人を掲載。
- サービスごとに支払いを管理しており、同一ユーザーへの年間支払額を合算して確認する体制がなかった。
勤務内容
- 同一ユーザーがA・B両サービスから応募し、同一企業・店舗で断続的に勤務。
- Aでの年間支払額:28万円
- Bでの年間支払額:27万円
- 合計:年間55万円の支払い
企業側の対応
- 各サービス単体では支払額が30万円未満だったため、担当者は給与支払報告書の提出やマイナンバーの取得は不要と判断。
- しかし、実際には合算で30万円を超えており、マイナンバーの取得および給与支払報告書の提出が必要なケースだった。
- 結果、税務署や自治体から確認が入り、報告書の再提出やマイナンバー再取得などの修正対応が必要となった。
単体のサービスを利用していれば、サービス側がユーザーによる応募に対して自動で制限を設け、一定条件を超える勤務をブロックする仕組みを持っています。しかし併用時にはそれぞれのサービスが個別に稼働データを管理するため、企業側で合算チェックを行わないと見落としが発生します。
このようなケースは、トラブルに発展する可能性もあるため注意が必要です。
スキマバイトサービス『シェアフル』の対策
スキマバイトサービス『シェアフル』では、上記のようなリスクを回避するために、以下のような仕組みを導入しています。
| 応募制限の目的 | 就業日数による応募制限 | 就業時間による応募制限 | 月収額による応募制限 | 詳細 |
| 社会保険加入ラインへの対策 | 1ヶ月以内に17日以上 | 2ヶ月で合計160時間を超過 | 1カ月の賃金が8.8万円を超える可能性がある | 求人へ応募できない:社会保険加入対象となる可能性 |
| 源泉徴収税額発生ラインへの対策 | 満1週間のうち、6日以上(法定労働時間超過を避けるため) 満1ヶ月のうち、10日以上(源泉徴収税区分の変更を避けるため) | 求人へ応募できない:源泉徴収税額が発生する可能性 | ||
| 給与支払報告書発生(マイナンバー取得)ラインへの対策 | 1月1日〜12月31日の間に支払われた給与支払額が28万円以上 | 求人へ応募できない:マイナンバーの取得が必要になる可能性 |
※全て、同一ユーザーが同一企業に就業しようとした際の応募制限機能
スキマバイトサービス『シェアフル』の「グループ招待機能」なら、就業者の一元管理が簡単に
シェアフルでは「グループ招待機能」を利用することで、他社スキマバイトサービスで就業していたユーザーを簡単にシェアフルへ招待することができます。また、招待したユーザーは自動的にグループ化されるため、招待したユーザーにのみ求人を公開することも可能です。
※他社スキマバイトサービスからの移行に伴い生じた損害等につき、当社は一切責任を負いかねます。
データの複雑化・応募重複・管理負荷増
スキマバイトを複数サービスで募集すると、応募者情報や稼働データがバラバラに管理されるため、応募重複や情報の不整合が起こりやすくなります。
「同じユーザーが複数のアプリから同一案件に応募する」「シフト調整の連絡が異なるサービスから届く」などの混乱が生じるケースもあります。
また、キャンセル発生時の対応やペナルティ処理を各プラットフォームで個別に行う必要があり、担当者の工数が増加します。
就業者視点の安心・評価トラブル防止
スキマバイトの併用は、ユーザー側にも影響を及ぼします。
複数アプリではたらく場合、勤務記録や評価データが分散するため、同一ユーザーに対する信頼スコアや評価が統一されず、マッチングの精度が低下するおそれがあります。
たとえば、あるアプリでの勤務態度が良好でも、別のサービスでキャンセルを繰り返すと、企業側が判断を誤るリスクがあります。
評価の不整合やキャンセル対応の遅れは、ユーザーと企業双方の安心感を損なう要因になります。
そのため、併用時にはユーザーとのコミュニケーションルールや評価方針を明確にし、トラブルを防ぐ体制を整えることが必要です。
まとめ:併用を正しく設計し、効果を最大化しよう
スキマバイトサービスを複数併用することで、企業はより多くの応募機会を得られ、募集スピードや稼働率を向上させることができます。
一方で、労務管理や応募データの整理、キャンセル対応など、管理業務の負荷が高まることも事実です。
併用を成功させるためには、以下の3つのポイントを意識することが重要です。
- サービスごとの制限や機能を理解すること
特に、給与支払額や応募制限などの条件を確認し、労務上のリスクを回避する。 - 管理業務負荷を鑑み、担当者の工数を削減できるようにすること
一度に複数のサービスで人材募集すると、メッセージ対応や評価などを複数サービスで行う必要が生まれるため、工数削減のために仕組み化する。 - ユーザーとの信頼関係を維持すること
評価制度を明確にし、キャンセルやペナルティ対応を一貫して行うことで、安心して応募してもらえる環境を整える。
自社の目的や業務体制に合わせて、最適な運用設計を行い、スキマ時間を有効活用しながら、より効率的な採用活動を実現しましょう。