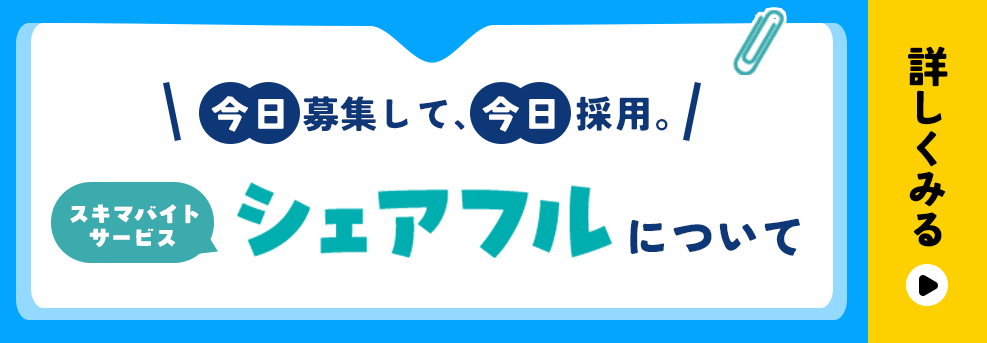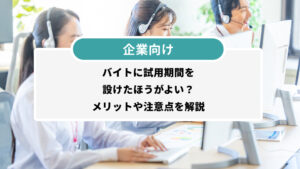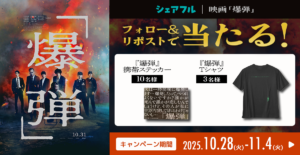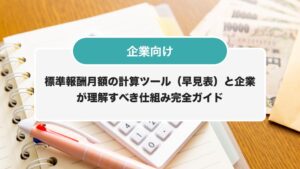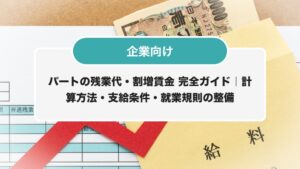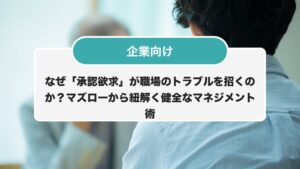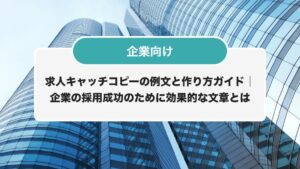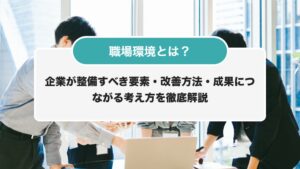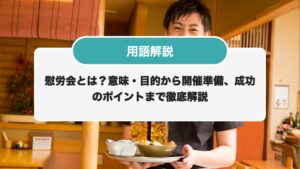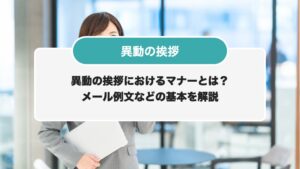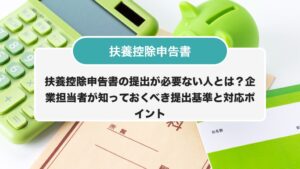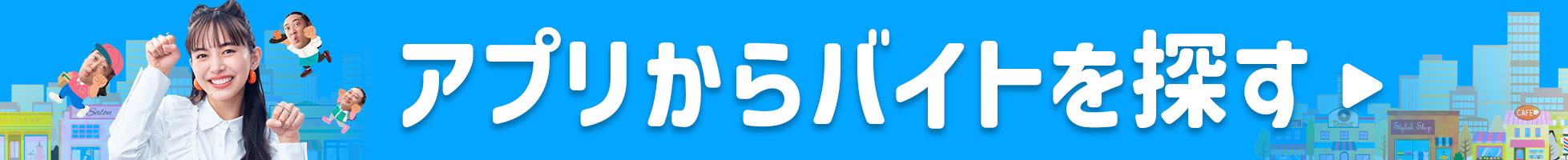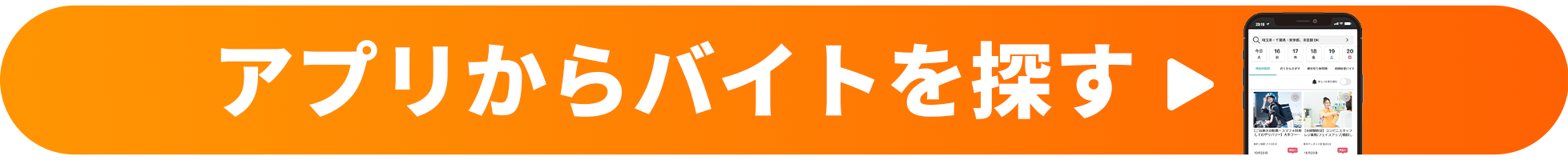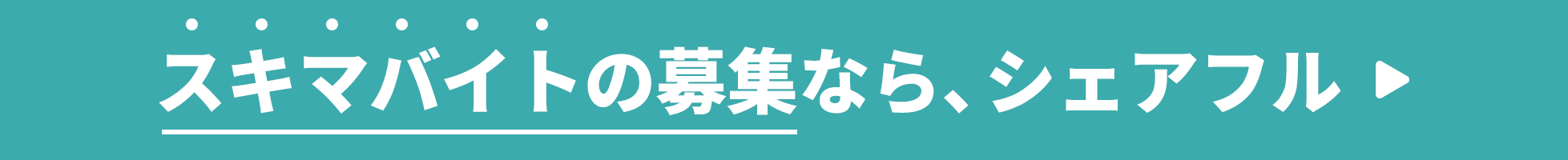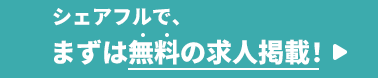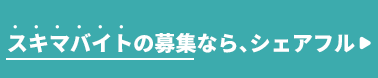バイト不採用の伝え方|採用側が押さえるべき断り方と注意点
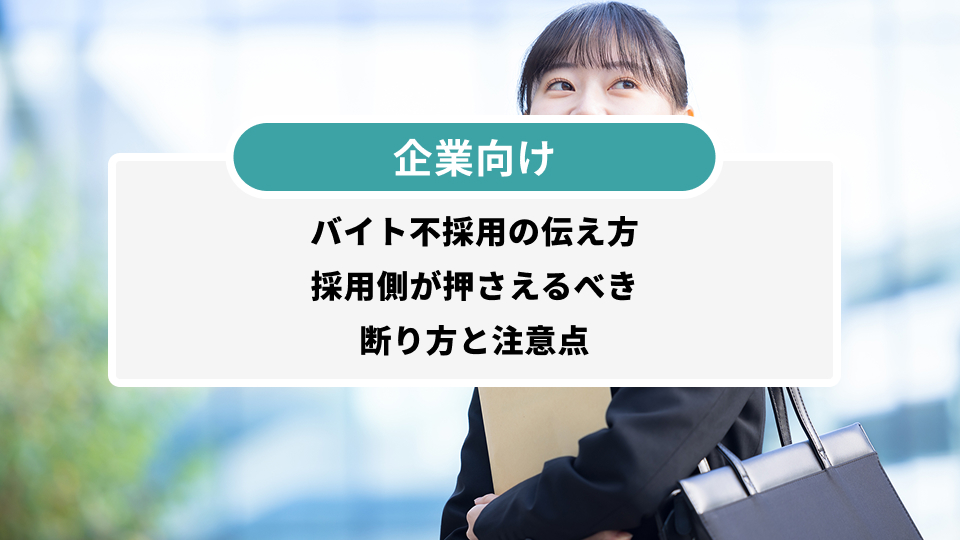
アルバイトの採用活動では、すべての応募者を採用できるわけではありません。不採用の伝え方次第では、応募者とのトラブルや企業イメージの低下につながるリスクもあります。
本記事では、アルバイト応募者への不採用連絡の基本的な考え方や、伝える際のコツ、注意点についてわかりやすく解説します。
バイトの不採用時も連絡しましょう

不採用の連絡はできれば避けたいものですが、採用活動においては欠かせない対応のひとつです。伝え方を工夫することで、企業としての信頼を守ることにもつながります。ここでは、不採用連絡をきちんと行うことがなぜ大切なのか、その理由を見ていきましょう。
企業イメージを大事にする
採用活動の対応ひとつで、企業に対する印象は大きく左右されます。特に不採用の連絡がなかったり、伝え方が雑だったりすると、応募者に「不誠実な会社」という印象を与えてしまいかねません。
特にSNSや口コミサイトが普及した今、不採用の連絡がないことに対する不満や不信感が、思わぬかたちで広められてしまうことも少なくありません。「応募したのに何も連絡がなかった」「対応が雑だった」といった評価がネット上に残れば、それが将来的な応募減や信頼低下につながる可能性もあります。
採用・不採用にかかわらず、丁寧な連絡を心がけることが、結果として企業イメージの維持や向上に直結します。採用担当者の対応一つが、会社全体のイメージにつながることを忘れないようにしましょう。
応募者がお客様になる可能性がある
アルバイトの応募者は、将来の「お客様」や「取引相手」になるかもしれません。とくに販売や接客業では、応募者が自社の商品やサービスのファンであることも多く、不採用時の対応が印象を大きく左右することがあります。「あの会社、対応が丁寧だったな」と感じてもらえれば、仮に不採用だったとしても好意的な気持ちは残ります。
一方で、ぞんざいな扱いをすれば、「もうあの店には行きたくない」と感じる人が出てくることも。採用活動は“選ぶ側”の立場になりがちですが、応募者もまた企業を見ています。不採用を伝えるときこそ、誠意をもって向き合うことが、大切です。
バイト不採用を連絡する際のコツ

不採用の連絡は、応募者にとって残念な知らせであることは間違いありません。しかし、だからこそ伝え方が重要です。ここからは、応募者に不採用を伝えるうえで押さえておきたいポイント・コツを解説します。
早めに連絡する
不採用の連絡は、できるだけ早いタイミングで行うことが大切です。というのも、応募者のなかには結果を待つ間、他の応募を控えている人もおり、判断が長引くことで時間を無駄にしてしまうケースもあります。
明確な期限があるわけではありませんが、書類選考や面接から3日以内、遅くとも1週間以内には連絡を入れるようにしましょう。
ただし、「早ければ早いほど良い」というものでもありません。面接直後や当日の連絡は、「最初から採用するつもりがなかったのでは」といった不信感を与えてしまうおそれもあります。丁寧に選考したうえでの結果であることが伝わるよう、適度な間隔を空けて通知するのが大切です。
また、不採用連絡をしないという対応は絶対に避けましょう。結果がどうであれ、応募してくれたこと自体が企業にとってはありがたい行動であり、その事実に対して誠意をもって対応する必要があります。今後のブランドイメージや再応募の可能性を考慮しても、節度ある丁寧な連絡は欠かせません。
不採用を伝える
不採用の結果を知らせる際は、ただ「今回は見送らせていただきます」とだけ伝えるのでは、応募者の心にモヤモヤが残ることがあります。特に「未経験歓迎」や「大量募集」などの文言を見て応募してきた人にとっては、「なぜ自分が落ちたのか」と疑問を抱きやすく、選考に対する不信感につながることもあるでしょう。
そのため、理由を詳細に説明する必要はないにしても、「想定を上回る応募があり、慎重に選考を進めた結果、今回はご希望に添えない結果となりました」など、選考の背景をうかがわせる言い回しを使うことが大切です。
なお、応募者の言動や見た目など、個人的な要素が不採用の理由だった場合は、たとえ事実であってもそのまま伝えるのは避けましょう。むやみに相手の自尊心を傷つけてしまえば、企業のイメージダウンにもつながりかねません。あくまで配慮ある言葉で、丁寧かつ冷静に伝える姿勢が求められます。
応募への感謝を伝える
不採用通知であっても、応募してくれたことへの感謝は必ず伝えましょう。「このたびはご応募いただき、誠にありがとうございました」という一文を加えるだけでも、応募者の受け取る印象はまったく違います。
選考に時間を使い、履歴書を準備し、面接に足を運んでくれたという労力に対して、敬意を持って対応することは企業としての最低限のマナーです。採用に至らなかったとしても、「対応が丁寧だった会社」として記憶に残れば、将来的に再応募につながることもあれば、お客様としてサービスを利用してもらえるかもしれません。
印象に注意する
不採用を伝えるメールは、たった数行のやりとりであっても、企業の印象を大きく左右するものです。メールの文章には、その企業がどのような価値観で人と向き合っているか、どんな姿勢で採用活動を行っているかが、知らず知らずのうちににじみ出ます。そのため、言葉の選び方や文章のトーンには十分な配慮が求められます。
また、完成した文面は送信前に必ず見直しましょう。語尾がぶっきらぼうになっていないか、読み手に失礼な印象を与える表現が紛れていないかなどはもちろん、テンプレートを活用する場合は宛先の確認も忘れないようにしてください。
応募書類の取り扱いについて伝える
意外と見落とされやすいのが、応募書類の取り扱いに関する対応です。履歴書や職務経歴書には、氏名や住所、連絡先といった個人情報が含まれており、扱いを誤るとプライバシーの侵害や思わぬトラブルにつながるおそれがあります。
そのため、不採用の連絡を行う際には、合否の結果だけでなく、「お預かりした書類は責任を持って当社で破棄いたします」あるいは「ご提出いただいた履歴書は、ご記載のご住所へ返送いたします」といったかたちで、書類の処理方法についてもきちんと伝えることが重要です。
また、こうした説明は面接の時点であらかじめ伝えておくと、応募者にとっても安心感につながります。
バイトの不採用を伝える方法と注意点

不採用の連絡は、電話・メール・郵送などさまざまな方法があります。それぞれの手段には適したタイミングや注意点があり、状況に応じた使い分けが求められます。
ここからは、不採用の伝え方について方法別に注意点を整理し、あわせて実際に使える例文もご紹介していきます。
メールで伝える場合
以前は不採用通知といえば郵送や電話が一般的でしたが、近年はメールを使う企業が増えてきました。手間をかけずに速やかに連絡できるうえ、送信記録を残せる点でも使いやすい方法です。電話のようにその場で理由を問われる心配もありません。
では、メールで不採用を伝える際、どのような点に注意しなければならないのでしょうか。以下で詳しく見ていきましょう。
件名で内容がわかるように
不採用通知をメールで送る際は、件名を見ただけで内容が伝わるように工夫しましょう。一般的には「【アルバイト選考結果のご連絡】株式会社〇〇」のように、選考結果であることと企業名を明記する形式がよく用いられています。
応募者は他社の選考も並行して進めている可能性があり、毎日のように大量のメールを受け取っている人も少なくありません。件名が曖昧だったり、採用と関係ないように見えたりすると、開封されないまま埋もれてしまうこともあります。
通知が届いているにもかかわらず「連絡がない」と誤解される事態を避けるためにも、受け取る側の気持ちを考え、わかりやすさを意識した件名を心がけましょう。
誤送信に注意
不採用通知をメールで送る際にとくに注意したいのが、誤送信です。誤って別の応募者の名前を記載してしまったり、本文に残っていた他人の情報をそのまま送ってしまったりすると、大きなトラブルにつながりかねません。
送信前には宛先・氏名・本文の内容を必ず確認し、テンプレートを使用している場合は書き換え漏れがないかもチェックしましょう。
また、複数の応募者に一斉送信するのは避け、個別に送るのが基本です。個人情報を扱うメールであるという意識を持ち、丁寧に対応することが求められます。
例文
件名:【選考結果のご連絡】〇〇アルバイト募集
本文:
〇〇 〇〇様
株式会社〇〇 採用担当の△△と申します。
このたびは弊社のアルバイト募集にご応募いただき、誠にありがとうございました。
慎重に選考を進めてまいりましたが、今回はご希望に添えない結果となりました。ご応募いただいたにもかかわらず、残念なお知らせとなり恐縮ですが、何卒ご了承いただけますと幸いです。
なお、お預かりした応募書類につきましては、履歴書記載のご住所宛に返送いたしますのでご査収ください。
末筆ながら、今後の〇〇様のご活躍をお祈り申し上げます。
〇〇店/株式会社〇〇
担当:〇〇
電話で伝える場合
電話で不採用を伝える方法は、早く確実に結果を伝えたいときに適しています。応募者本人が電話に出れば、その場で内容を直接伝えられるため、認識のズレも起こりにくいというメリットがあります。
以下では、電話で不採用を伝える際に意識しておきたいポイントと、実際の会話例を見ていきましょう。
会話定型文を準備
電話で不採用を伝える際は、あらかじめ話す内容を整理し、定型のフレーズを準備しておくとスムーズです。話す内容が曖昧だったり、言い回しに迷ったりすると、相手に不信感を与えることがあります。特に冒頭のあいさつや結果の伝え方、感謝の言葉は、ひとつの流れとして決めておくと落ち着いて対応しやすくなります。
また、相手が動揺することも想定し、落ち着いた声のトーンや柔らかい言葉づかいを心がけることも大切です。電話では相手の反応に応じて柔軟な対応が求められるため、想定される質問やリアクションにも備えておきましょう。
不在時は後日こちらより連絡する
電話をかけた際に応募者が不在だった場合は、折り返しを求めるのではなく、あらためてこちらから連絡する旨を伝えるようにしましょう。不採用の結果を留守番電話に残すのはNGです。本人以外がメッセージを再生する可能性があるうえ、一方的に結果だけ伝えるかたちになり、応募者に雑な印象を与えてしまうことがあるため注意してください。
また、電話は記録が残らないため、あとになって「言った言わない」のトラブルに発展する可能性もあります。誤解を防ぐためにも、電話後に同じ内容をメールや郵送で補足しておくことも忘れないようにしましょう。
会話例
不採用の結果を電話で伝える際には、話す順序や言葉づかいが重要です。以下に、基本的な会話の流れを踏まえた例をご紹介します。
【会話例】
〇〇様のお電話でお間違いないでしょうか。わたくし〇〇店の採用担当、△△と申します。ただ今、お時間よろしいでしょうか。
先日はアルバイトのご応募、誠にありがとうございました。その後、社内で選考を進めてまいりましたが、慎重に検討した結果、今回は採用を見送らせていただく結果となりました。せっかくご応募いただいたにもかかわらず、このようなお知らせとなり大変申し訳ございません。
先日お預かりした応募書類につきましては、弊社で責任を持って破棄させていただきますのでご安心ください。お忙しいなか、ご応募いただき本当にありがとうございました。〇〇様の今後のご活躍をお祈りしております。
郵送で伝える場合
郵送による通知は、応募書類を返却するタイミングと合わせて送れる点で便利です。選考結果を急いで伝える必要がない場合には、丁寧な対応として受け取られやすい方法といえるでしょう。メールや電話に比べて手間はかかりますが、その分「最後まで丁寧に対応してくれた」という印象を残しやすくなります。
ここでは、郵送で不採用通知を送る際のマナーや押さえておきたいポイントについて解説します。
不採用通知と応募書類は折らない
応募書類や通知文を送付する際は、折らずに入れられるサイズの封筒を使用しましょう。たとえ提出時に折りたたまれていた書類でも、返送時はまっすぐな状態で送り返すのがマナーです。クリアファイルに入れてから封入すれば、水濡れや折れ曲がりといったトラブルも防ぎやすくなります。
封筒は中身が見えない厚手のものを使い、表には赤字で「親展」と記載しましょう。
送付記録を残す場合は特定書類で送る
不採用通知を確実に届けたい場合は、記録が残る方法での郵送を検討しましょう。たとえば、特定記録郵便であれば配達状況を追跡でき、応募者が不在でも郵便受けに投函されるため、スムーズに受け取ってもらいやすくなります。
一方で、簡易書留は手渡しでの受け渡しが基本となるため、不在時には再配達が必要になる点に注意が必要です。
例文
拝啓
先日はお忙しい中、面接にお越しいただき誠にありがとうございました。
社内で慎重に検討を重ねた結果、誠に残念ではございますが、今回は採用を見送らせていただくこととなりました。ご期待に沿えず恐縮ではございますが、何卒ご了承くださいますようお願い申し上げます。
なお、お預かりしました応募書類につきましては、本状に同封の上ご返却いたしますのでご査収ください。
〇〇様の今後ますますのご活躍を心よりお祈り申し上げます。
敬具
株式会社〇〇
採用担当 〇〇〇〇
まとめ

本記事では、アルバイト応募者への不採用連絡の基本的な考え方や、伝える際のコツ、注意点について詳しく解説してきました。
不採用通知は、採用活動を行ううえで避けて通れない対応のひとつです。それと同時に、企業の印象に関わる大切な連絡でもあります。募集人数が限られている場合は、不採用になる応募者も一定数出てくるため、対応の手間や精神的な負担を感じる場面もあるでしょう。
だからこそ、基本の構成を押さえたうえで、使い回しが可能なフォーマットを準備しておくとスムーズです。「何をどう伝えればいいかわからない」という場合は、記事内で紹介した例文もぜひ参考にしてみてください。