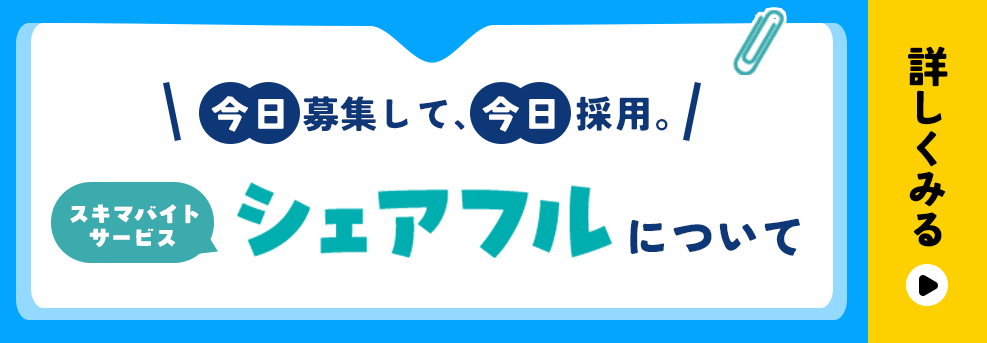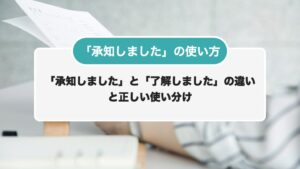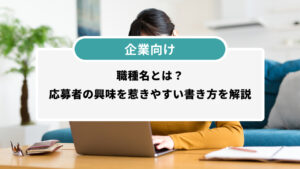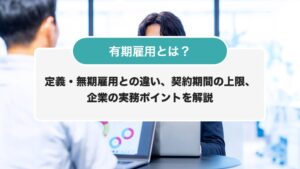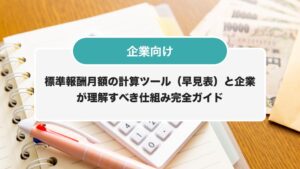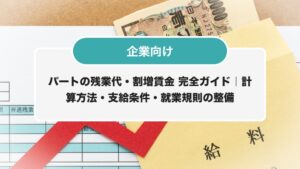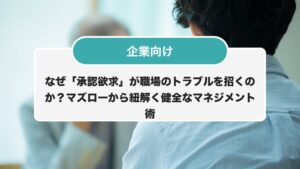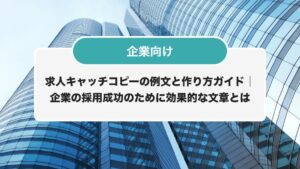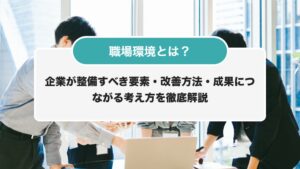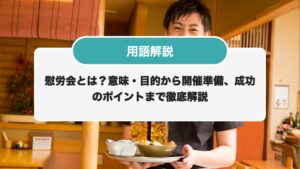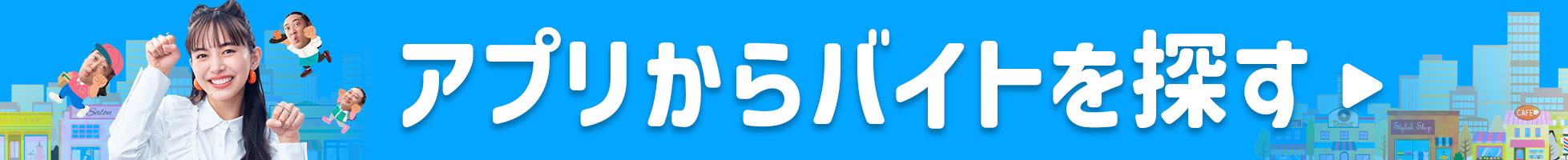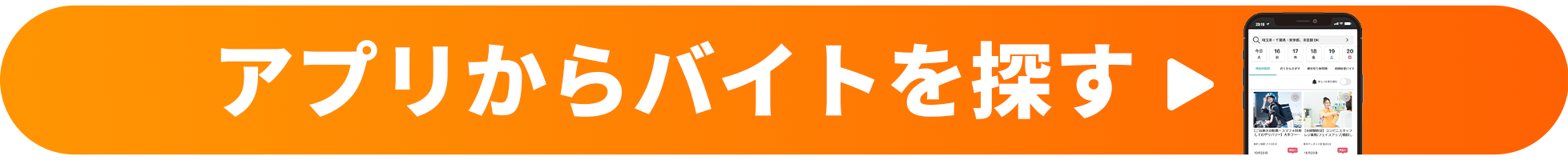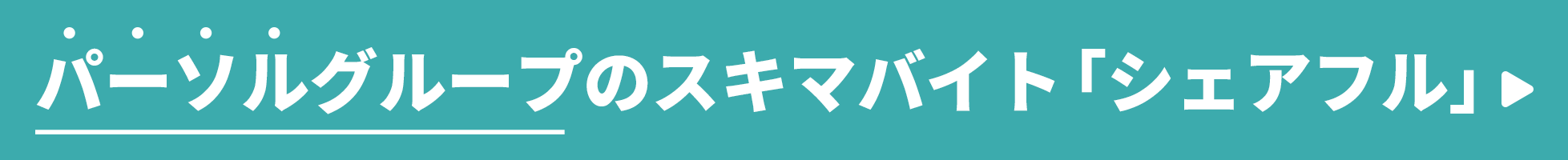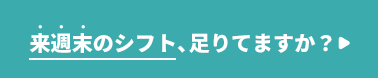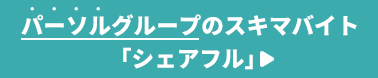内定式はいつ開催すべき?企業が押さえておきたい進行管理方法や必要な準備などを徹底解説!
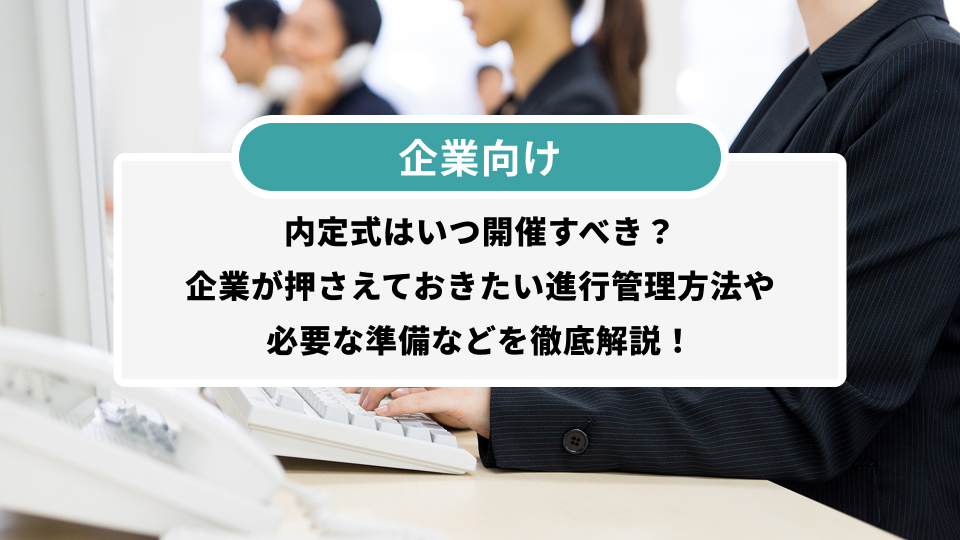
新卒採用に取り組む企業にとって「内定式」は、採用活動の総仕上げともいえる重要なイベントです。採用広報や面接、選考を経てようやく迎えた内定者にとって、企業からの正式な歓迎を受ける最初の場であり、入社へのモチベーションを高める機会でもあります。
一方で、企業側にとっては「いつ開催するのが適切か」「どのようなプログラムを設計すべきか」「準備すべき項目は何か」といった課題がつきまといます。特に近年は採用市場の変化やオンライン開催の増加などもあり、従来の形式をそのまま踏襲するだけでは十分な効果を得られないケースも少なくありません。
本記事では、 「内定式はいつ開催すべきか」という疑問に答えるとともに、開催目的や役割、準備すべき具体的項目、トラブル対応、成功につなげる工夫 までを網羅的に解説します。採用活動に携わる人事担当者や経営層の方にとって、すぐに実務に活用できるノウハウを整理しました。
【結論】内定式の開催時期は一般的に10月1日

内定式は 毎年10月1日 に実施するのが一般的です。これは、一般社団法人 日本経済団体連合会(以下、経団連)が定めていた指針や、企業と内定者双方の事情が背景にあります。
経団連が定めた「採用選考活動に関する指針」による影響
経団連が定めていた「採用選考に関する指針」によると、企業が正式に内定を出せる時期は大学生・大学院生の場合「卒業・修了年度の10月1日以降」とされています。そのため、多くの企業がこの日を基準に内定式を設定し、採用活動全体の区切りとしていました。この指針は2018年10月9日に廃止が決定され、2021年卒以降の採用からは政府がルール作りを主導することになりました。しかしながら、それ以降も正式な内定日は10月1日以降のまま運用がされています。なお、経団連が指針を提示していた頃より、この指針には法的拘束力はないものの、多くの企業が10月1日に内定式を実施しています。
企業と内定者双方にとって合理的である
10月1日は、年間の採用スケジュールを考えた場合にも合理的です。春先に始まった広報活動から夏にかけて面接・選考を経て、秋には内定者が出そろう流れが一般的であり、内定式を通して入社までの準備をスタートさせやすい時期といえます。
採用活動全体における位置づけ
内定式は単なる儀式ではなく、 採用活動の総仕上げかつ、入社までの橋渡し として機能します。企業の側からすれば、内定者が「内定を受けて良かった」と感じるかどうかを左右する重要な場面です。ここでの体験が、翌年4月の入社までのモチベーション維持や、転職活動・他社への応募継続を防ぐ効果にもつながります。
開催時期を決める際の注意点

一般的に10月1日が内定式の標準ですが、すべての企業が必ずその日に実施しなければならないわけではありません。以下のような観点を踏まえ、柔軟にスケジュールを調整する必要があります。
学生の学業や転職活動との関係
内定者の多くは大学4年生や大学院2年生であり、10月は後期授業が始まる時期です。平日昼間に設定すると出席が難しいケースもあるため、午後開催や土日祝日の実施を検討する企業も増えています。また、近年では就職活動の長期化・転職活動との並行もみられるため、内定者の予定調整に配慮することが重要です。
職種別・業種別のスケジュール調整
例えば、 営業職や販売職 を中心に採用している企業では、繁忙期と重ならないように配慮する必要があります。小売業やサービス業は年末に向けて繁忙化するため、10月初旬に早めに実施するのが望ましいケースもあります。一方、 技術系や製造業 の企業では研究・開発スケジュールに影響されるため、部署単位での柔軟な対応が求められる場合もあります。
複数拠点を持つ企業の調整ポイント
支店や工場など複数拠点を持つ企業では、全体を集約した「本社開催」と、拠点ごとに分けた「分散開催」の選択が必要です。本社でまとめる場合は大規模なイベントホールやホテル会場を押さえる必要があり、分散開催の場合は運営負担が分かれる一方で統一感に欠けるリスクがあります。いずれの場合も、管理システムを活用したスケジュール共有が欠かせません。
内定式までのスケジュール例

実際に内定通知から内定式までの流れを整理すると、以下のようなステップが一般的です。
- 内定通知の送付(8〜9月)
内定者への正式な通知を行い、求人情報や求人広告で示した条件と齟齬がないかを確認。 - 書類準備(9月中旬)
履歴書や提出書類、内定証書の作成。求人管理システムと連携し、誤記載や表記揺れがないかチェック。 - 会場選定・案内送付(9月下旬)
開催会場やオンラインツールの選択。案内メールや電話で内定者へ通知。 - 内定式実施(10月1日前後)
基本プログラムの進行。スタッフ配置や役割分担を明確化。 - フォローアップ(実施後1週間以内)
内定者へのお礼メール送信、アンケート回収、改善点の記録。
このように、内定式の開催は採用活動の延長線上にあるものであり、求人情報や業務内容との整合性を意識しながら進めることが成功のポイントです。
そもそも内定式とは?採用活動における意味と役割
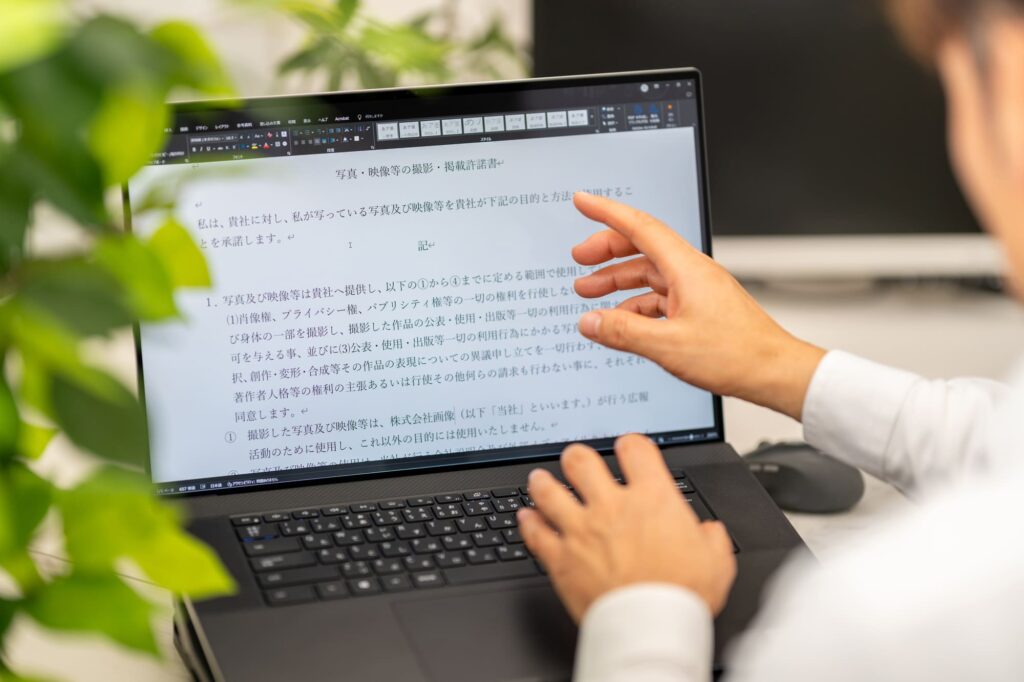
内定式とは、企業が正式に内定者を迎え入れるために行う式典であり、採用活動における重要な節目となります。入社前に内定者を対象としたイベントを設けることで、企業としての姿勢を示し、内定者の入社意欲を高める効果が期待できます。
企業が内定式を行う最大の意義は、 「信頼関係の構築」 と 「不安解消」 にあります。内定者にとっては「本当に自分はこの会社に受け入れられているのか」という漠然とした不安がつきものです。ここでしっかりと受け入れ姿勢を表現することで、安心感を持たせられます。
また、企業側にとっても、内定式を通じて 自社理解を深めてもらい、採用活動の改善につなげる という役割があります。単なる形式的なイベントではなく、入社までの準備を円滑に進めるための起点と位置づけるべきです。
内定式を開催する目的
内定式には複数の目的が存在します。以下は代表的なものです。
内定者に会社理解を深めてもらう
求人情報や採用面接だけでは伝えきれない、企業の理念・事業内容・業務の具体的な流れを説明する場として活用できます。例えば営業職・事務職・技術系職種など、異なる職種ごとの役割や業務内容を解説することで、内定者の理解を促進できます。
内定者の不安や疑問を解消してもらう
内定者は「勤務地は希望通りか」「残業や休日はどうか」「配属部署はどのように決まるのか」といった疑問を抱きやすいものです。事務連絡や担当者からの説明を通して不安を取り除くことが可能です。
内定者と既存社員の交流を深めてもらう
懇親会や座談会を実施することで、内定者同士や現場の先輩社員との関係構築を促進します。特に販売職や接客業など、協働が重視される業種では交流の機会が入社後のスムーズな業務推進に直結します。
内定式と入社式の違い
「内定式」と「入社式」は混同されがちですが、両者の役割や目的は大きく異なります。以下の表で整理します。
| 項目 | 内定式 | 入社式 |
| 開催時期 | 主に入社前年の10月1日 | 入社年の4月1日 |
| 対象者 | 内定者 | 新入社員 |
| 目的 | 内定通知の正式化、会社理解の促進、不安解消 | 入社の正式受け入れ、社会人としてのスタート |
| プログラム例 | 内定証書授与、事務連絡、懇親会 | 辞令交付、役員挨拶、研修開始 |
| 採用活動との関係 | 採用活動の最終ステップ | 就業開始の初日 |
このように、内定式は採用活動における「まとめ」としての位置づけであり、入社式は雇用契約に基づいた「スタート」のイベントです。
内定式では何をする?基本的な流れと内容

それでは、具体的に内定式当日にどのようなプログラムを実施すべきかを見ていきましょう。企業の業界や規模によって異なりますが、一般的には以下のような流れが基本です。
基本プログラムの構成
社長・役員の講話
企業のトップが直接メッセージを伝えることで、内定者に対して強い印象を与えられます。会社の将来ビジョンや事業戦略を語ることで、内定者の興味をさらに高め、入社意欲を強化する効果があります。
内定証書授与
内定を公式に証明するための重要なプロセスです。形式ばらずとも構いませんが、書類の表記や表現に誤りがないかを必ず確認しましょう。
内定者自己紹介
内定者同士の交流を促進するための機会です。氏名や出身大学だけでなく、将来やりたい仕事や希望職種を話してもらうと良いでしょう。
事務連絡
入社までに必要な書類(履歴書の最終版、健康診断書など)の提出期限や、研修日程の案内を行います。また、管理システムやメール・電話を通じた連絡方法を周知することも重要です。
懇親会
軽食を交えた座談会や交流会を設けることで、企業文化や社内の雰囲気を感じてもらえます。とくにサービス業や営業職では、コミュニケーション力を磨く場としても有効です。
入社意欲を高めるプログラム例
基本的な式典に加え、以下のような工夫が内定者のモチベーションを高めます。
- 座談会:現場社員が参加し、仕事内容やキャリアの実例を紹介。
- 職場見学:工場・事務所・店舗などを案内し、仕事内容の具体的なイメージを持たせる。
- 懇親会:複数の社員と交流し、社風への理解を深める。
これらの工夫によって、内定者は「自分がこの会社ではたらく姿」をより具体的に描けるようになります。
内定式の会場選びと開催方法

内定式を実施する際、会場の選択は成功に直結する重要な要素です。単に「人数が入れば良い」という判断ではなく、内定者の心理的な印象や運営のしやすさまで考慮する必要があります。
会場の種類と特徴
- イベントホール・貸会議室
交通アクセスが良く、必要な設備(マイク、スクリーン、机など)が揃っています。規模に応じた会場を柔軟に選べる点がメリットです。 - ホテルの宴会場
フォーマル感を演出したい場合に適しています。懇親会まで一括で開催でき、飲食の提供もスムーズです。 - 自社オフィスや会議室
コストを抑えながら実施できるため、中小企業や採用人数が少ない場合に有効です。業務内容に直結する現場を見せられる点も魅力的です。
オンライン開催のケース
近年はオンラインでの開催も増えています。Web会議ツールを用いることで全国の内定者を一度に集めることが可能です。ただし、画面越しでは表情や雰囲気が伝わりにくいため、プレゼン資料や動画を活用した工夫が欠かせません。通信トラブルに備えたリハーサルも必須です。
会場選定の基準
- アクセス(駅から近いかどうか・遠方在住の内定者が来場しやすいか)
- 必要設備の有無(音響・映像機材、Wi-Fi)
- 予算(会場費+運営費)
- 感染症対策や安全面
これらを総合的に判断し、内定者にとって「安心して参加できる場」となるよう工夫しましょう。
内定式の準備チェックリスト

内定式は事前準備の質によって成功が左右されます。以下のチェックリストを活用すると、抜け漏れを防げます。
必要書類・資料
- 内定証書(正確な表記・印字チェックが必要)
- 求人情報との整合性確認資料(条件や業務内容が一致しているか)
- 配布資料(会社概要、事業説明、福利厚生ガイド)
- 進行表(タイムスケジュール、役割分担の明記)
連絡・案内
- 内定者への案内メール送付(開催日時・会場・服装・持ち物)
- 案内電話での確認(未返信者や不明点の解消)
- 管理システムでの出欠確認
備品
- 名札、筆記用具、資料フォルダー
- プロジェクターやスクリーン
- 懇親会用の飲食物(実施する場合)
担当スタッフ
- 司会担当
- 受付・案内係
- 進行管理担当
- 懇親会運営スタッフ
内定式当日の進行管理のコツ

タイムスケジュール作成
あらかじめ 時間ごとに区切った進行表 を作成し、誰がどの役割を担うのかを明確にしましょう。開始から終了までの所要時間は、一般的に 2〜3時間 が目安です。
既存社員の役割分担
受付や誘導、式典進行、事務連絡などを複数人で担当するのが理想です。特に複数部門(営業、人事、事務系スタッフなど)が関わる場合は、事前にリハーサルを行い連携を強化しておくことが重要です。
進行中の注意点
- 内定者の緊張をほぐすため、冒頭で笑顔や軽いアイスブレイクを取り入れる
- 専門用語や業界用語は丁寧に解説する
- 残業や休日、勤務地など条件に関する質問が出た場合には誠実に回答する
こうした配慮が、内定者の安心感や信頼感につながります。
よくあるトラブルと対応方法

内定式は参加人数が多く、複数の要素が絡むためトラブルも起こりがちです。事前に想定しておくことでスムーズな対応が可能です。
機器トラブル
プロジェクターやマイクが作動しないケースはよくあります。必ず 予備機材や代替方法(紙資料の配布など) を用意しておきましょう。
内定者の欠席
体調不良や学業の都合で欠席するケースがあります。後日フォローメールや資料送付を行い、録画映像を共有するなどの対応が有効です。
天候による中止リスク
台風や大雪など、移動が困難な場合に備えて オンライン開催への切り替え案 を事前に周知しておくと安心です。
内定者からの質問対応
給与、年収、転勤の可能性などに関する質問はデリケートです。ガイドラインや募集要項をもとに一貫性を持った説明を心がけましょう。回答に迷う場合は「担当部署から改めて連絡します」と保留し、誤った表現を避けることが大切です。
内定式の成功につなげる工夫

内定式は単なる式典ではなく、採用活動の集大成として位置づけられるべきイベントです。そのため、以下のような工夫を取り入れることで、より効果的に運営できます。
求人情報や業務内容との一貫性を示す
内定者は求人サイトや求人広告で見た情報をもとに入社を決めています。内定式で伝える条件や仕事内容がそれと異なれば、不信感を与える可能性があります。求人票や募集要項と整合性を持たせ、言葉や表現の使い方にも注意しましょう。
専門用語の丁寧な解説
製造業やエンジニア職、技術系の職種では、専門用語や業界特有の言葉が多く登場します。内定式では、一般的な理解を前提に かみ砕いた解説 をすることが重要です。理解度チェックや具体例を交えた説明を取り入れると効果的です。
業界ならではの具体例を紹介
営業職なら顧客対応の場面、事務系なら管理システムを使った業務のイメージ、製造業なら作業員や工場の工程などを具体例として提示すると、内定者は将来の姿を明確に描けます。
コミュニケーション施策を導入
懇親会やグループワークだけでなく、オンライン上での自己紹介動画やアンケートを活用すると、複数拠点の内定者同士もつながりやすくなります。これにより、入社前から人材同士の関係性が築かれやすくなります。
内定式後に行うべきフォロー

フォローメールの送信
式典直後に「ご参加ありがとうございました」という旨のメッセージをメールで送ると、内定者は安心します。タイムリーな連絡は信頼感を高める効果があります。
アンケート回収
内定式の満足度や改善点をアンケートで収集し、今後の採用活動に役立てましょう。質問項目は「内容の理解度」「雰囲気」「不安点」などに絞ると回答率が高まります。
求人管理システムへの登録・分析
内定者の情報やアンケート結果を管理システムに登録し、今後の採用活動に活用します。傾向を把握することで、求人広告や募集原稿の改善につなげることができます。
内定者インターン・課題の案内
入社までの半年間で意欲を維持するために、インターンや課題を設定するケースもあります。たとえば 事務職向けの資料作成練習、営業職向けの顧客対応ロールプレイ など、業務理解を深める取り組みは有効です。
内定式に関してよくある質問

内定式はなぜ10月1日の実施が一般的?
経団連の指針により、正式な内定通知は卒業年度の10月1日以降とされていたためです。(2021年卒から廃止となり、政府主導でルールを設定しています。なお現在も、同様の日程が指定されています。)これを受けて、多くの企業がこの日を基準に設定しています。
内定式は必ず10月1日に実施しなければならない?
必ずしもそうではありません。業種や職種によっては10月1日以外の日に実施しても問題ありません。大切なのは、内定者が参加しやすく、採用活動の流れに合致した日程を選ぶことです。
内定式を実施しない企業もあるの?
はい、存在します。特に採用人数が少ない企業やベンチャー企業では、内定式を省略して個別面談や食事会で代替するケースもあります。ただし、その場合でも 内定者に安心感を与える場を設けること が重要です。
まとめ:内定式を「いつ」開催するかは採用成功の第一歩

本記事では「内定式 いつ」という疑問に答えつつ、企業が押さえておくべきポイントを解説しました。
- 内定式の開催時期は 一般的に10月1日 が標準。
- ただし職種・業種・拠点の状況に応じて柔軟な調整が必要。
- 内定式は採用活動における 総仕上げ であり、信頼関係の構築や不安解消の場となる。
- 当日のプログラムは、内定証書授与・講話・自己紹介・事務連絡・懇親会などが基本。
- 成功のためには 求人情報との一貫性、専門用語の丁寧な解説、フォローアップ施策 が欠かせない。
企業にとって内定式は、採用活動の単なる締めくくりではなく、内定者を「未来の人材」として迎え入れる最初の大切なイベントです。自社に合った時期と方法を選び、戦略的に実施することが、採用成功の大きな一歩となります。