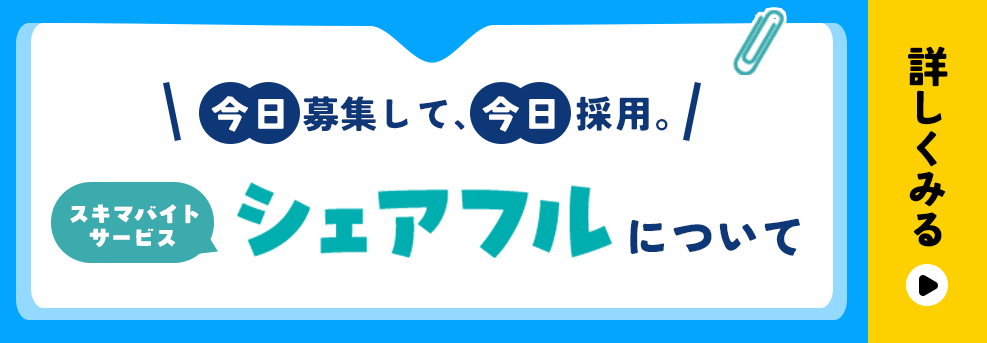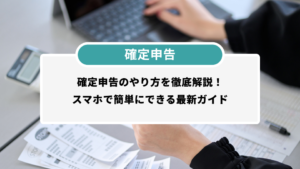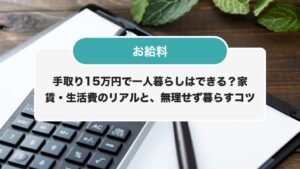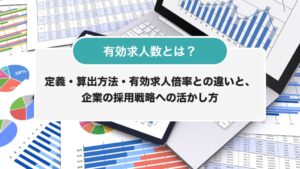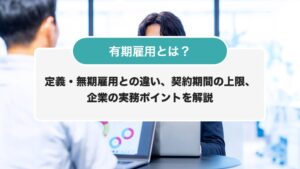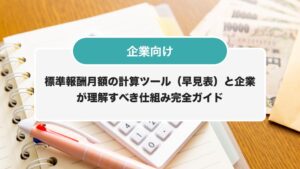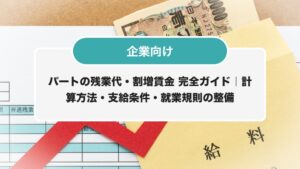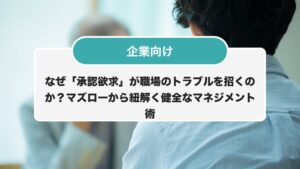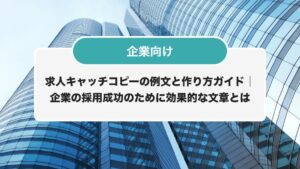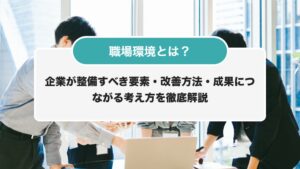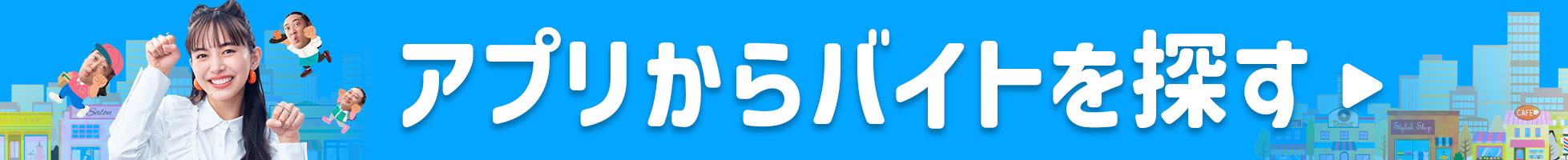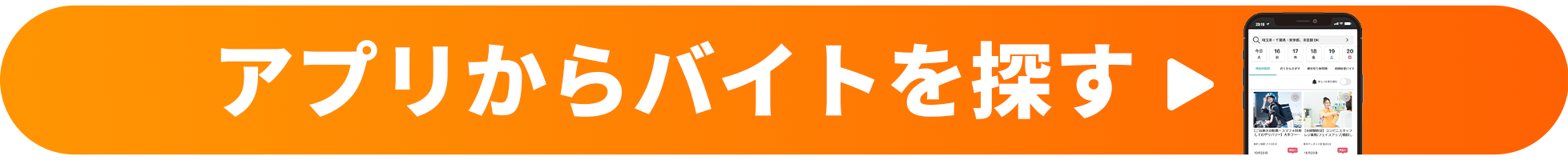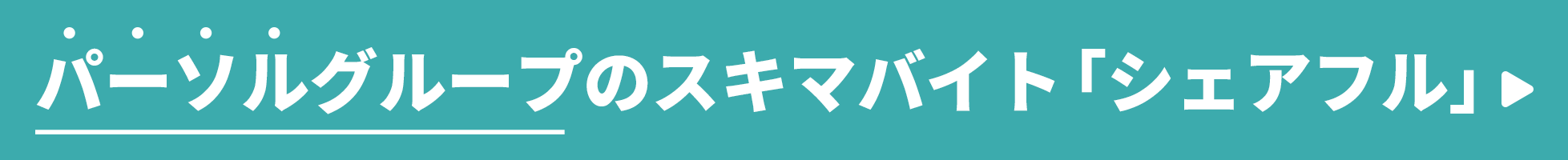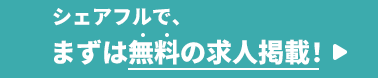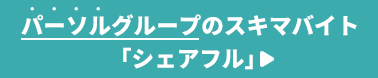【2025年最新】求人掲載におすすめの10選!|採用成功のポイントや媒体の選び方も解説
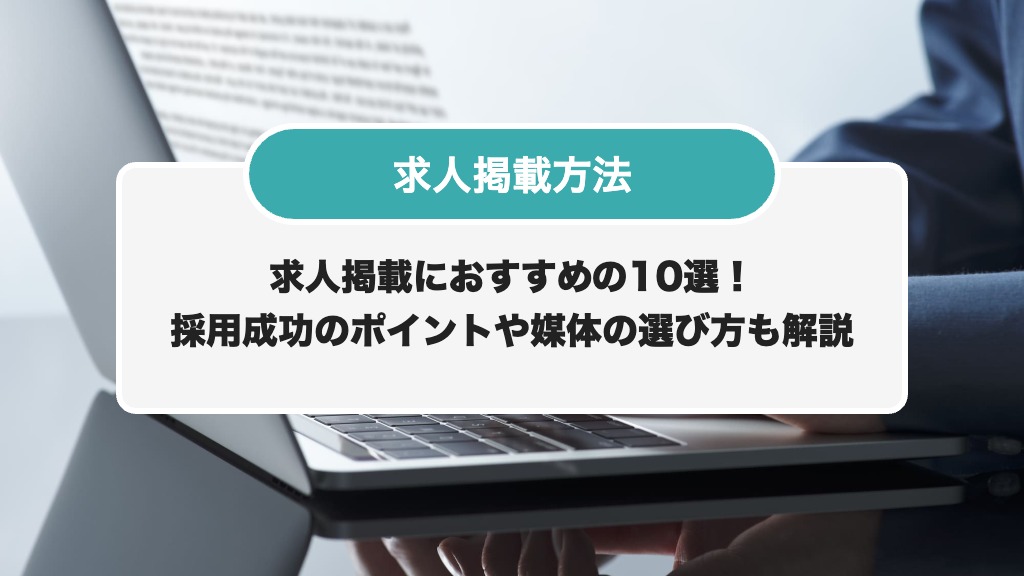
「求人を出しても応募が来ない」「どの媒体を選べば良いかわからない」と悩む採用担当者も多いのではないでしょうか。求人媒体にはそれぞれ得意分野や掲載形式があり、自社に合った選定が成果を大きく左右します。本記事では目的や採用ニーズに応じたおすすめの求人媒体を分かりやすくご紹介します。媒体選びのコツや採用活動を成功させるためのポイントも詳しく解説しますので、ぜひ参考にしてください。
自社に合った掲載先を見極める5つのポイント

求人媒体はどれも同じように見えて、それぞれに特徴があります。採用活動をスムーズに進めるためには、自社の目的や状況に合った媒体を選ぶことが大切です。媒体選びを誤ると、時間も費用も無駄になりかねないため注意しましょう。
ここでは、求人媒体を選ぶうえで確認すべき5つのポイントを解説します。
1.求人媒体の特性は自社に合っているか
求人媒体には、それぞれ得意な領域があります。例えば、アルバイトやパート募集に強い媒体もあれば、正社員やIT職に特化している媒体もあります。そのため「なんとなく有名だから」「無料だから」といった理由だけで選んでしまうのは危険です。
大切なのは、自社が求めている人材と媒体の特性がマッチしているかどうか。掲載前に、どの職種に強いのか、どんなユーザー層が多いのかを確認しておくことで、ミスマッチを避けることができます。まずは、自社の採用目的に合ったフィールドを見極めるところから始めましょう。
2.現在の自社の採用課題を解決できるか
求人媒体を選ぶ際は、単に応募者数を増やすことだけを目的にせず、今の採用課題をどう解消できるかを軸に考えてみましょう。例えば、「求人を出しても反応が少ない」「応募は来るが定着しない」「母集団は集まるが求める人材とズレている」など、企業ごとに悩みはさまざまです。
媒体によっては、応募前に求職者とやり取りできる機能があったり、動画で職場の雰囲気を伝えられたりと、課題に応じた工夫がしやすいサービスもあります。自社の現状を正しく把握し、その課題に対応できる機能や仕組みがあるかを確認しておくことで、より効果的に採用活動を進めることができるでしょう。
3.自社の採用ターゲットが多く登録しているか
どれだけ魅力的な原稿を掲載しても、その媒体に求める人材がいなければ、応募にはつながりません。だからこそ、自社が採用したい人物像と、求人媒体に登録しているユーザー層が一致しているかどうかも必ず確認しておく必要があります。
例えば、高校生や大学生をアルバイトとして募集する場合、若年層が多く利用しているアプリやスマホ特化型の求人サイトが効果的です。一方で、専門職や中途正社員の採用であれば、経験者が集まる転職サイトや業界特化型の求人媒体を検討すべきでしょう。
登録者の年代、職歴、地域、はたらき方の志向など、詳細なデータを確認し、自社のニーズとズレがないかを見極めることで、ムダな掲載を防ぎ、成果の出やすい採用活動につながります。
4.費用対効果は良いか
求人媒体を選ぶ際、掲載費用が高いほど効果があると考えがちですが、必ずしもそうとは限りません。たとえば、高額な求人広告を掲載しても、ターゲット層に届かなければ、費用が無駄になってしまいます。
重要なのは、費用に対してどれだけの成果を得られるか、つまり「費用対効果」です。採用コストを抑えながら質の高い人材を効率的に集めるためには、掲載費用だけでなく、掲載内容やターゲット層とのマッチング精度も大きなポイントとなります。自社の採用ニーズに合った求人媒体を選び、費用を無駄にしないよう慎重に検討しましょう。
なお、場合によっては、無料の求人媒体や低予算で利用できるサービスでも十分な効果を得られることがあります。
5.必要な付属機能が揃っているか
求人媒体を選定する際は、掲載プランや料金だけでなく、各媒体が提供している機能面もしっかりとチェックしておきましょう。特に、スカウト配信や応募者管理、原稿の修正サポート、面接日程の調整機能などが備わっていると、採用業務の負担を大きく軽減できます。
例えば、スカウト機能がある媒体であれば、企業側から条件に合う人材へ直接アプローチが可能になり、応募を待つだけでなく、能動的な採用活動が行えます。また、応募管理機能によって応募者の選考状況を一元管理することで、対応漏れや連絡の遅れを防ぐとともに、スピーディーな選考を進めやすくなります。
このように、備わっている機能の違いによって、採用活動のスピードや質にも差が出ます。自社の採用体制や課題に応じて、必要な機能がそろった媒体を選ぶよう意識しましょう。
アルバイト・単発バイトにおすすめの求人媒体7選

短期スタッフや即戦力をできるだけ早く確保したい場面では、アルバイト・単発バイトに特化した求人媒体の活用が効果的です。長期雇用を前提とした媒体とは異なり、「空いた時間にはたらきたい」「短期間だけはたらきたい」というニーズを持つ人材が多く集まるため、スピーディーな人材確保が期待できます。
ここでは、短期バイトや単発バイトに強みを持つ、おすすめの求人媒体を厳選してご紹介します。
1.シェアフル
シェアフルは、スキマ時間にはたらきたい個人と、今すぐに人手が欲しい企業をつなぐ新しいスタイルの求人サービスです。Webから即時に1日単位で求人掲載が可能で、掲載料は無料。勤務が発生した場合のみ料金がかかる成果報酬型のシステムを採用しているため、無駄なコストを抑えつつ、必要なタイミングで柔軟に人材を確保できます。
また、掲載後24時間以内の応募率は87%と非常に高く、登録者数は650万人以上。条件に合った人材を高確率で見つけられるのが大きなポイントです。
なお、掲載無料求人サービスにありがちな「原稿作成は自社で対応しなければならない」といったこともなく、希望すれば代理作成してもらえるため、求人掲載が初めての会社でも安心です。
2.タウンワーク
タウンワークは、株式会社リクルートが運営するアルバイト・パート求人に特化した媒体で、業界でもトップクラスの知名度を誇ります。フリーペーパーとWebの両方で求人情報を発信しており、全国展開しながらも地域密着型の採用活動を展開しやすい点が特長です。
特に、フリーペーパーは駅やコンビニなど生活圏内で手に取れるため、幅広い年齢層の求職者にアプローチが可能です。一方、Web版では勤務地や路線・駅、職種など、複数の条件で絞り込み検索が可能なため、求職者自身が自分に合った仕事を見つけやすい仕様となっています。
営業担当者によるサポートが受けられるプランもあり、採用ニーズに応じた最適なプランや原稿内容の提案を受けることができます。
3.バイトル
バイトルは、ディップ株式会社が運営するアルバイト・パート求人に特化した求人サイトです。10代・20代を中心とした若年層に強く、登録者の約7割がこの年代にあたると言われています。そのため、若いスタッフを求めている業種や店舗にとっては、特に相性の良い媒体といえるでしょう。
急募案件にも対応しやすく、申し込み当日の掲載も可能。掲載期間中は何度でも求人原稿の修正ができるため、採用状況や仕事内容の変化に柔軟に対応できます。また、動画や写真を使った求人情報の掲載にも力を入れており、職場の雰囲気や実際の作業内容を視覚的に伝えることで、求職者とのミスマッチを減らす効果が期待できます。
4.タイミー
タイミーは、企業の「はたらいてほしい時間」と求職者の「はたらきたい時間」をマッチングするスキマバイト募集サービスです。1日単位や数時間単位の超短期求人にも対応しており、急な人手不足や繁忙期の人材確保に適しています。
求人の掲載は最短1分で完了し、スピード感ある運用が最大の特長。公開から24時間以内に70%以上の求人がマッチングしているという実績もあり、急な欠員や繁忙期の補強にも対応しやすい点が評価されています。また、登録ワーカーは700万人を超えており、マッチング成功率は90%以上。企業のニーズに合った人材を高確率で確保できます。
5.Indeed
世界的な認知度を誇る求人検索エンジン「Indeed(インディード)」は、多種多様な求人を一括検索できるプラットフォームです。求職者は職種やエリアなどをキーワードで絞り込み、自分に合った求人を効率よく見つけられるのが特徴です。
企業側にとっての魅力は、基本的に無料で掲載できる点。一般的な求人サイトでは職種ごとに料金が発生することが多いですが、Indeedならその心配はありません。職種数や掲載期間に制限がないため、複数ポジションを同時に募集したい場合でも、予算を気にせず運用できます。
また、有料オプションの「スポンサー求人」を利用することで、求人情報の表示頻度を高め、求職者の目に留まりやすくすることが可能です。
6.Wantedly
Wantedly(ウォンテッドリー)は、企業と求職者をつなぐビジネスSNS型の採用プラットフォームです。企業は自社のビジョンやカルチャーを前面に押し出した採用ページを作成でき、求職者はその想いに共感して応募する仕組みとなっています。特に20代から30代の若手人材が多く登録しており、エンジニアやデザイナー、セールス、マーケティングなどの職種に強みを持っています。
また、募集記事だけでなく、ブログ形式で企業の魅力や社員のはたらき方を発信できる「ストーリー」機能も備わっており、採用広報としての活用もOK。ダイレクトスカウト機能を利用すれば、企業から積極的に求職者へアプローチができ、採用活動の幅を広げることができます。
7.メルカリ ハロ
メルカリ ハロは、株式会社メルカリが運営するスキマ時間を活用した単発・短時間の求人プラットフォームです。2024年初春にサービスを開始し、首都圏の一部エリアから順次全国へ展開しています。初期費用や掲載費用が無料で、成果報酬型の料金体系を採用しているため、コストを抑えた採用活動が可能です。
また、月間2,260万人のメルカリユーザー基盤を活用し、幅広い層の求職者にアプローチが可能。メルカリの本人確認済みアカウントを活用することで、求職者は新たな情報入力なしに応募が可能となり、企業側もスムーズなマッチングが期待できます。
転職の求人掲載におすすめの求人媒体や求人広告
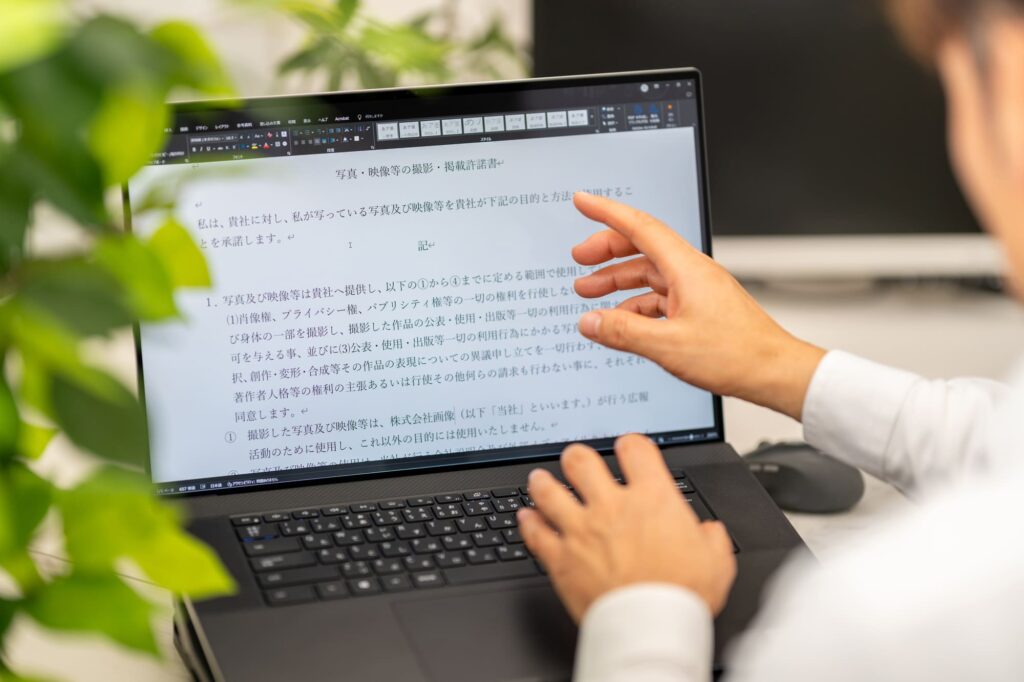
正社員やキャリア人材の採用を考えるなら、転職者向けの求人媒体を選ぶことが重要です。ここでは、経験者採用やキャリア人材の獲得を目指す企業におすすめの転職系求人媒体を、特徴や強みとあわせてご紹介します。
マイナビ転職
「マイナビ転職」は、全国規模で求人情報を発信する国内有数の総合転職サイトです。登録会員数は850万人を超えており、特に20代〜30代の若手社会人層に強く支持されています。
掲載プランは、MT-S・MT-A・MT-B・MT-C・MT-Dの5種類から選べ、4週間の掲載で20万円から120万円まで幅広い価格帯が用意されています。
また、求職者をセグメントして配信できる「スカウトメール」や「DM」のほか、ビッグデータを活用したレコメンドエンジンが1日最大20名のスカウト会員を自動推薦する「コンタクトメール」も利用できます。
エン転職
「エン転職」は、エン・ジャパン株式会社が運営する転職情報サイトで、会員数は1,100万人を超えています。利用者の約7割が35歳以下の若年層で構成されており、毎月約7万人が新規登録している点も特徴的です。
どのプランでも、A4サイズ4枚分に相当する原稿スペースがあり、職場の写真、動画、口コミ情報、さらには取材担当者によるコメントなど、求職者が知りたい情報を多角的に伝えられます。また、「オネストリクルーティング」という方針のもと、企業側には誠実な情報開示を促しており、その結果として入社後のミスマッチを最小限に抑え、1年以内の離職率は他媒体の約半分にとどまっています。
こうした実績が評価され、2018年から2024年まで7年連続でオリコン顧客満足度No.1に選ばれています。
doda
doda(デューダ)は、パーソルキャリア株式会社が運営する総合転職支援サービスで、求人情報と人材紹介を同ブランドで提供しています。2024年9月時点での登録会員数は896万人を超えており、20代〜30代半ばの若手・中堅層が中心です。
求人掲載サービスは複数のプランがあり、掲載順位や表示サイズに応じて選べる仕様になっています。また、希望する求職者層に直接情報を届けられるダイレクトメールや、サイト内に表示されるバナー広告など、採用の打ち出し方を工夫できるオプション機能も充実。
幅広い業種・職種に対応できる柔軟性の高いサービス構成と、ターゲットに直接アプローチできる仕組みによって、スピード感のある採用活動を展開したい企業にぴったりの求人媒体といえるでしょう。
type
type(タイプ)は、株式会社キャリアデザインセンターが運営する転職サイトで、特にITエンジニアや技術系エンジニアの採用に強みを持っています。全会員数は約360万人で、そのうちスカウト会員数が約295万人以上と、充実したスカウト機能を活用することで採用成功率を高めることが可能です。
掲載プランはtype-Aからtype-Dまでの4種類があり、4週間の掲載料金は35万円から100万円となっています。また、1回の掲載料金で2職種(2原稿)まで掲載できるため、複数職種の同時募集や、同一職種でもターゲットに合わせた訴求が可能です。
求人媒体で採用を成功させる5つのポイント

ここからは、求人媒体で採用を成功させるために押さえておきたい5つのポイントをご紹介します。
採用ターゲットを明確に
採用活動を成功させるうえで、まず欠かせないのが「誰を採用したいのか」をはっきりさせることです。年齢層、経験年数、スキル、性格傾向、はたらき方の希望など、具体的な人物像を描いておくことで、求人原稿の内容にも一貫性が生まれます。
例えば、「若手のフルタイムスタッフを採用したい」のか、「短時間でも即戦力になる人材が欲しい」のかによって、適した媒体や訴求の仕方も大きく変わってきます。
ターゲット像が曖昧なまま求人を出してしまうと、応募はあってもミスマッチが起きやすく、採用活動全体にムダが出てしまうこともあるため注意しなければなりません。まずは採用ターゲットを明確に設定し、それに沿った戦略を立てていきましょう。
自社のアピールポイントが伝わるように発信
求人原稿においては、給与や勤務条件だけでなく、「この会社ではたらいてみたい」と思ってもらえるようなアピールが重要です。とはいえ、単に良い面を並べるだけでは求職者の心には響きません。
大切なのは、自社の魅力ではなく“実態”を具体的に伝えることです。例えば、どんな人が活躍しているのか、どんな雰囲気の職場なのか、仕事のやりがいはどこにあるのかといったリアルな情報があると、応募意欲につながりやすくなります。
また、ターゲットとする人材が関心を持ちそうなキーワードやエピソードを取り入れるのも効果的です。発信内容に「共感」や「安心感」を持ってもらうことで、応募の質が高まり、採用の成功率も上がっていくでしょう。
自社の求人を多くの人に見てもらう工夫をする
どれだけ内容の良い求人を作っても、そもそも見てもらえなければ応募にはつながりません。そのため、求人を広く届けるための工夫が欠かせません。例えば、複数の求人媒体を併用することで接点を増やしたり、検索されやすいキーワードを原稿内に盛り込んだりすることが有効です。また、タイミングも重要です。
特定の業種や職種では、月末や連休明けなどに応募が集中しやすい傾向があるため、掲載開始日を調整することで閲覧数を伸ばすことができます。応募数を増やすためには、まず「見つけてもらう」ことを意識しましょう。
求人媒体は現在の採用状況に合わせて選ぶ
求人媒体は、企業の採用状況や目的によって選び方を変えることが大切です。たとえば、急ぎで人材を確保したいときには即日掲載・即日応募が期待できるスキマバイト系の媒体が有効です。
一方で、中長期的にじっくりと人材を見極めたい場合は、スカウト機能や職場情報の発信に強い媒体が適しています。また、予算に余裕がないときは無料掲載が可能なサービスを活用し、限られたコストでも成果を出せる方法を検討しましょう。このように、自社の採用の緊急度、必要な人材のタイプ、使える予算などを総合的に判断して、媒体を使い分けることが、効率的な採用活動につながります。
入社日から逆算したスケジューリング
採用活動では「いつまでに入社してもらいたいか」を明確にし、その日から逆算してスケジュールを組むことが重要です。求人掲載から応募、書類選考、面接、内定、入社手続きといった一連の流れには、思った以上に時間がかかることも少なくありません。
例えば、応募が集まるまでに1〜2週間、そこから面接日程の調整や内定通知、入社準備までを含めると、最低でも1ヶ月は見ておく必要があります。余裕を持ったスケジュールを組むことで、焦って採用条件を緩めたり、対応が遅れて候補者を逃したりするリスクを避けられます。特に繁忙期や欠員補充が急務の場合でも、逆算思考で計画的に動くことが、安定した採用につながります。
まとめ
本記事では、求人掲載におすすめの媒体や選び方、採用成功のためのポイントについてご紹介しました。
求人媒体は、それぞれ特徴や得意分野が異なるため、自社の採用ターゲットや採用課題に合ったものを選ぶことが大切です。媒体選びだけでなく、発信内容やスケジューリングなど運用面も工夫することで、より効果的な採用活動が実現できます。ぜひ本記事の内容を参考に、自社にとって最適な求人媒体を見つけてください。