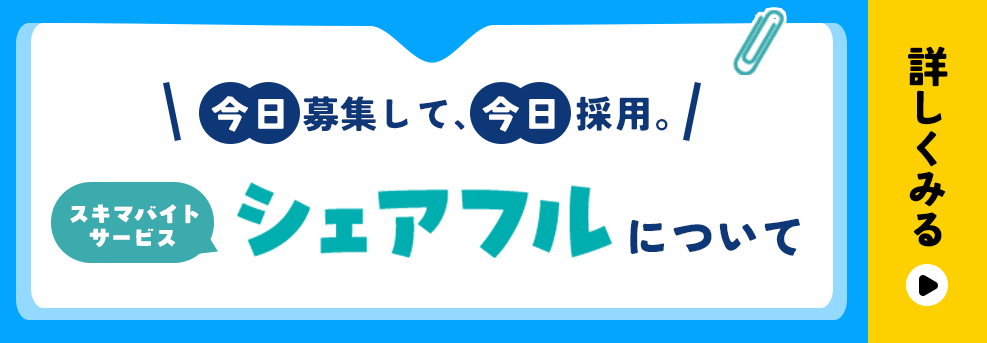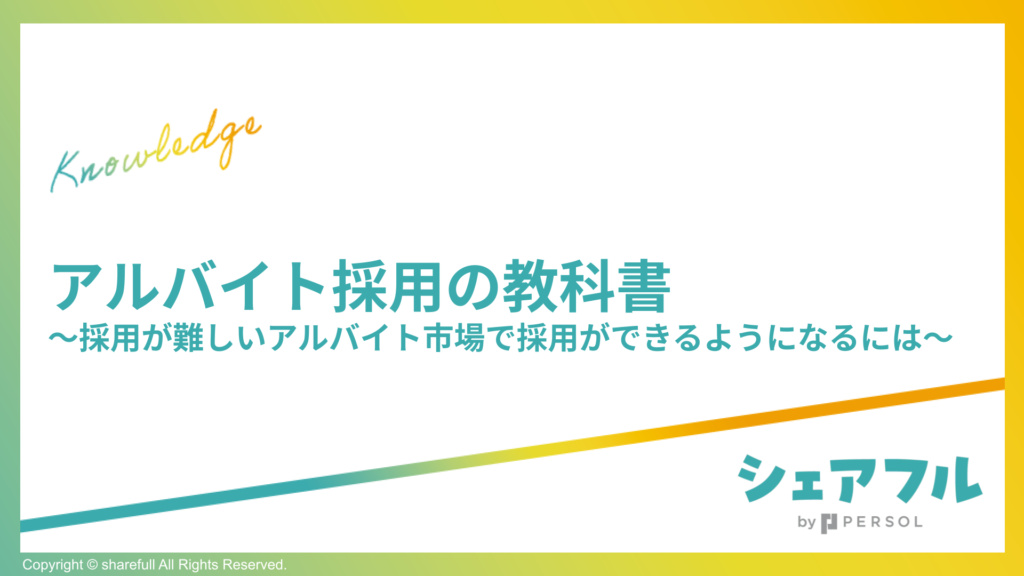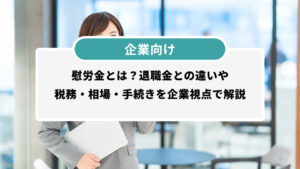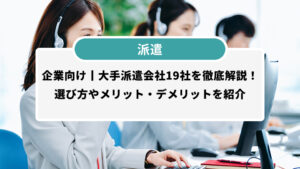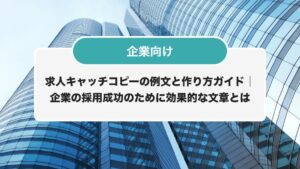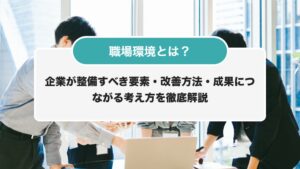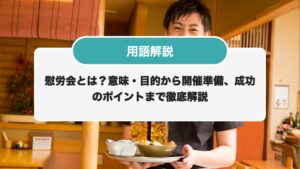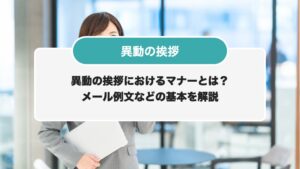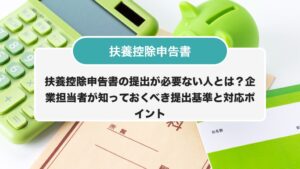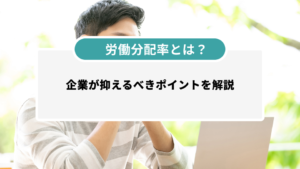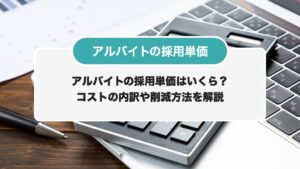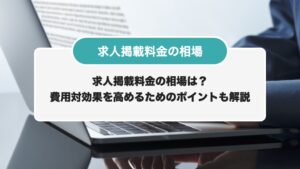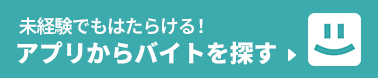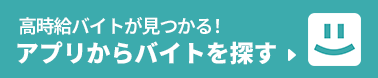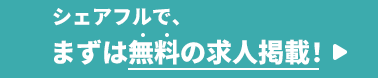【2025年最新版】日雇い雇用者も源泉徴収が必要?令和7年の源泉徴収額と記載方法を解説
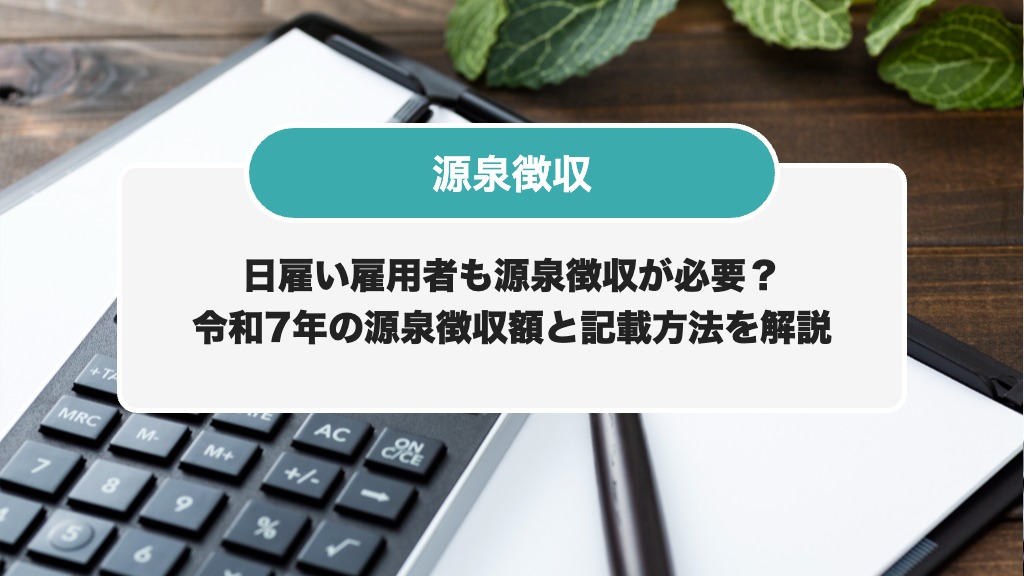
源泉徴収とは、給与などの支払い時に所得税などをあらかじめ差し引いて納税する仕組みです。正社員やパートだけでなく、日雇い労働者を雇用する際にも原則として源泉徴収が必要です。
しかし、「単発・日雇いのアルバイトを雇用する場合は源泉徴収が必要なのか」「税額の計算方法がよくわからない」と感じている方も多いのではないでしょうか。
この記事では、日雇い雇用における源泉徴収の必要性、計算のルール、記載・発行の注意点など、令和7年版の最新情報を基にわかりやすく解説します。
「アルバイト採用を始めたい」「アルバイト採用をしているが、今の方法が正しいか不安」とお考えの方は少なくありません。
レポートでは、「アルバイトとパートの違い」「採用までの流れ」「採用手法」の他、「アルバイト採用コストを下げる方法」などをまとめています。アルバイト採用にお困りの方はぜひご活用ください。
日雇い雇用者も原則源泉徴収が必要
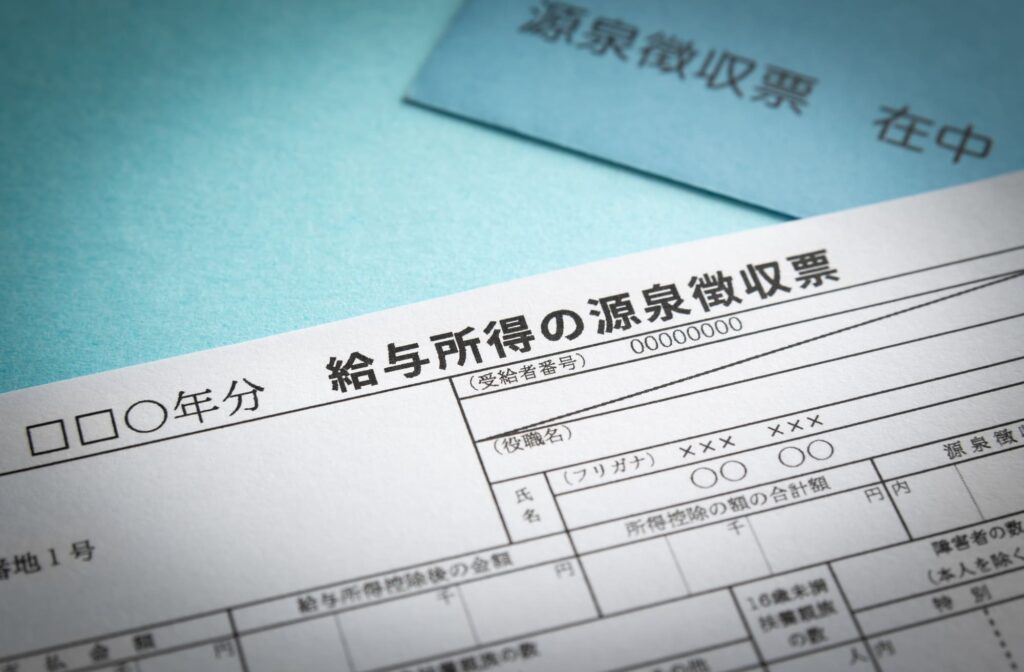
日雇いや単発のアルバイトを雇用する場合、原則として源泉徴収を行う必要があります。
源泉徴収とは、企業が従業員に支払う給料から税金をあらかじめ差し引き、その税金を企業が代わりに税務署に納める仕組みです。役員や正社員、パート、アルバイトなど、全ての労働者に適用されます。
年収103万円以下のパート・アルバイトは所得税がかからないので、源泉徴収票の発行は不要と誤解している人も少なくありません。しかし、所得税がかからない場合でも、他の収入と合算すると課税所得が発生する場合があるため、手続きは必要です。
<日雇い・単発バイトで源泉徴収が必要になる条件>
| 1日の給与が9,300円以上である(交通費を除く)雇用契約の期間が2か月以内であること労働日または労働時間によって給与が算出され、労働日ごとに支払いを受ける |
日雇い労働者は給与の受け取り方法が現金手渡しであることも多く、源泉徴収が適切に行われていない可能性もあるでしょう。
しかし、税務署の指導のもとでは、現金手渡しでの給与支払いの場合でも、源泉徴収を行い必要な書類を発行しなければなりません。適切な手続きをしなければ、税務調査で指摘を受ける可能性があるため、注意が必要です。
日雇いの源泉徴収は通常と異なる
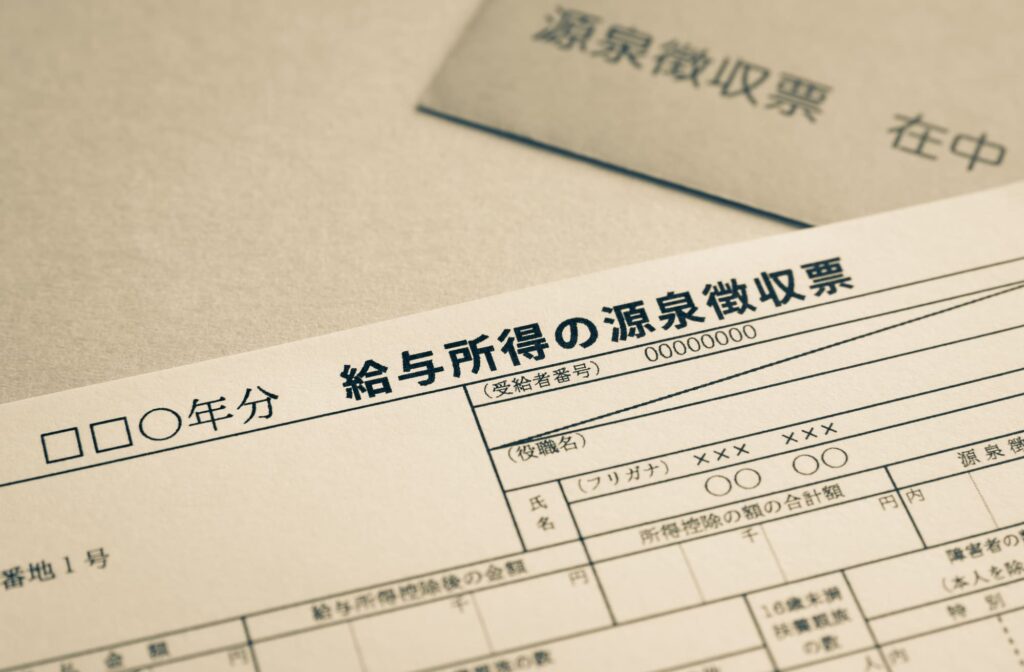
日雇い労働者は、「雇用期間が2カ月以内の労働者」と定義されています。給与の支払いは「日払い」に限らず、月末払いや翌月末支払いであっても、日雇い労働者に該当します。
日雇い労働者の源泉徴収は、一般的な給与所得者と異なるルールが適用されるので、把握しておきましょう。
日額から源泉徴収額を算出
日雇い労働者の源泉徴収は、国税庁の「源泉徴収税額表」に基づいて「所得税及び復興特別所得税」の額を算出する仕組みです。
正社員など、給与所得者の源泉徴収額は月単位で計算しますが、日雇い労働者の場合は、日額の給与に応じて算出されます。
日額表は、下記に該当する給与を支払うときに利用します。
- 毎日支給
- 毎週支給
- 日割り支給
- 日雇い支給
源泉徴収の「甲・乙・丙」
給与所得者の源泉徴収区分には、「甲」「乙」「丙」の3種類があります。これらの区分は、納税者が提出する「扶養控除等申告書」の有無や雇用形態によって決まります。
| 甲欄 | 扶養控除等申告書を提出している場合に適用される |
| 乙欄 | 扶養控除等申告書を提出していない場合に適用される |
| 丙欄 | 日雇い労働者や短期雇用者に適用される |
日雇い労働者は基本的に「丙欄」が適用され、通常の給与所得者とは異なる源泉徴収の方法が用いられます。
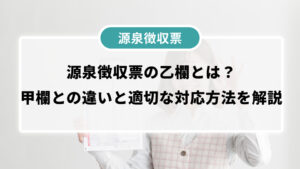
日雇い雇用者が「丙」に該当する条件
日雇い労働者は、ほとんどの場合「丙欄」が適用されると考えて問題ありません。丙に該当する条件は以下のとおりです。
| あらかじめ定められている雇用契約の期間が2か月以内であること。日々雇い入れている場合には、継続して2か月を超えて支払をしないこと。 |
もし最初の契約期間が2カ月以内であっても、雇用契約の期間延長や再雇用によって2カ月を超えた場合は「丙欄」を適用できません。
契約期間が2カ月を超えた日から「甲欄」または「乙欄」に区分され、通常の給与所得者と同じ税率で課税されます。
日雇いの源泉徴収額
日雇い労働者の源泉徴収額は、1日ごとの給与額に基づいて決まります。
具体的には、国税庁が公表する「源泉徴収税額表(日額表)」に基づいて、給与から所得税を差し引きます。給与等の金額には、交通費は含まれません。
日額9300円以上で源泉徴収が発生
日雇い労働者の給与が、日額9,300円以上の場合、源泉徴収の対象になります。
最初から雇用期間が2カ月以内と決まっており、日給や時給計算による給与であれば、9,300円未満までは源泉徴収が不要です。
また、月払いであっても、雇用契約が2カ月以内であり、実際に日雇いの形態ではたらいた場合、合計日給が9,300円未満であれば、源泉徴収は不要になります。
令和7年の日額源泉徴収税額表
日雇い労働者の源泉徴収額を計算する際は、国税庁が公表する「源泉徴収税額表(日額表)」を確認しましょう。
令和7年度の日額源泉徴収税額表は、こちらからご確認いただけます。
なお、適用される税額表は毎年更新されるので、最新の情報を確認してください。
日雇いの場合の源泉徴収票について

日雇い労働者に対して、雇用主側は源泉徴収票を発行する義務があります。
源泉徴収票とは、支払った給与や差し引かれた所得税の額を記載した書類で、労働者の確定申告や年末調整の際に必要不可欠なものです。
ここでは、日雇い労働者を雇用した場合の源泉徴収票について解説します。
日雇い・単発雇用の場合も源泉徴収票の発行が必要です
日雇いや単発雇用であっても、所得税を源泉徴収した場合は、源泉徴収票を発行しなければなりません。
日雇い労働者は複数の雇用先ではたらくことが多いため、それぞれの雇用主が支払った給与と源泉徴収額を記載した源泉徴収票を用意する必要があります。
源泉徴収票の発行要求に応じない場合、1年以下の懲役または50万円以下の罰金が課される恐れがあるので、必ず対応しましょう。
源泉徴収票の発行期限は、従業員に給与を支払った翌年の1月31日までです。たとえば、2025年1月から12月までの源泉徴収票は、2026年1月31日までに発行しなければなりません。
年の中途で退職した従業員に対しては、退職日から1カ月以内に交付しなければなりません。日雇いの場合は、年の中途で退職となるケースが大半です。退職日より1カ月以内を期限として適用されると考えておきましょう。
参照:No.7411 「給与所得の源泉徴収票」の提出範囲と提出枚数等|国税庁
スムーズに源泉徴収票を発行するために
源泉徴収票を発行するには、労働者のマイナンバーや住所を記載する必要があります。スムーズに源泉徴収票を発行するために、以下の情報を確認しておきましょう。
| 住所マイナンバー自社がメインではたらいている場合、他の職場の源泉徴収票 |
源泉徴収票に記載する住所は「住民票に記載されている住所」であるかを確認しましょう。従業員の手元に源泉徴収票が届かなければならないので、発行時点で引越しの予定があるかも合わせて確認しておくのがベストです。
マイナンバーは、雇用主側が税務署に源泉徴収票を提出する際に必要です。
また、複数の勤務先で日雇いバイトをしている場合、メインの勤務先で年末調整が行われます。その他の勤務先の収入は、源泉徴収票を基に確定申告を行う必要があります。
給与明細の発行も忘れてはいけません。給与明細には、支払額と源泉徴収額を明記し、労働者が自分の所得を確認できるようにしましょう。また、マイナンバーの取り扱いは厳格に行う必要があります。マイナンバーは従業員本人からの提供を受けたうえで、適切に管理し、外部流出がないように対策を講じることが求められます。マイナンバーは給与支払報告書の作成や税務署への提出時にも使用されるため、必ず正確な情報を確認してください。
日雇いの源泉徴収に関するよくある質問

ここからは、日雇いの源泉徴収に関するよくある質問に回答します。
雇用が2カ月を超えた場合どうすればいい
日雇い労働者としてはたらいていた場合でも、同じ雇用主のもとで2カ月を超えて継続して雇用されると、源泉徴収の区分が変わります。
具体的には、雇用開始から2カ月を超えた日以降、「丙欄」ではなく「甲欄」または「乙欄」が適用されます。
「甲欄」は、扶養控除等申告書を提出することで適用され、税額が軽減されるのが特徴です。一方、「乙欄」は申告書を提出しない場合に適用され、税率が高くなります。
日雇い労働者は基本的に扶養控除申告書を提出しないケースが多いため、2カ月を超えると「乙欄」として扱われ、税負担が増える可能性があります。
また、雇用形態が変わることで、社会保険の加入義務が発生するケースもあるでしょう。一定の勤務日数や労働時間を満たすと、雇用保険や健康保険、厚生年金の加入対象になる場合があるので、十分に確認しておきましょう。
発行しなかった場合どうなる?
万が一、源泉徴収票を発行しなかった場合、税務署から雇用主に対して指導や是正勧告が行われることがあります。従業員が退職した場合でも、求められれば速やかに発行しなければなりません。
また、税務署だけでなく、労働基準監督署からも指導を受ける場合があります。悪質な場合は、罰則が科される可能性もあるので注意が必要です。
源泉徴収票は、原則として給与の支払いが完了した翌年の1月31日までに発行する義務があります。企業としての信用を守るためにも、適切な手続きを行いましょう。
日雇いで給料が手渡しの場合は?
給与を手渡しで支払う場合でも、源泉徴収は必ず行う必要があります。
銀行振込ではなく現金払いであっても、税金の控除を省略することは認められていません。給与の支払い時に適切な税額を差し引き、決められた期限までに税務署へ納付しましょう。
また、税務調査などの際に架空の人件費であると疑われるケースも考えられます。
丙欄適用で、手渡しで給与を支払ったときは、支払いが実在するものであると証明できるよう、給与明細書を発行し、源泉徴収額を明記しておくことが重要です。
適切な手続きが行われていないと判断されると、追徴課税の対象となる恐れもあるので注意しましょう。
日雇い労働者の源泉徴収が不要なケースとは?
日雇い労働者に対する源泉徴収は原則必要ですが、すべてのケースで義務が発生するわけではありません。
たとえば、雇用契約ではなく業務委託契約を結ぶ場合には扱いが異なります。法人同士の取引においては、報酬を支払う際に源泉徴収の義務は原則として発生しません。
しかし、法人が個人と業務委託契約を結ぶ場合には、所得税法に基づき報酬に対して源泉徴収を行う必要があります。
また、外国人労働者を雇用する場合も注意が必要です。外国人留学生がアルバイトとしてはたらく場合は、他の居住者と同様に源泉徴収の対象となります。一方、短期滞在中の外国人など、税法上の「非居住者」に該当する場合には、20.42%という一律の源泉徴収率が適用されます。
なお、「居住者」とは日本国内に1年以上住んでいる、もしくは生活の拠点がある個人を指します。反対に、「非居住者」は日本に住所も住居も持たず、滞在期間が短期に限られる個人のことです。
居住区分によって税率や処理方法が変わるため、事前に確認しておくことが大切です。
日払い・週払い・月払いによる源泉徴収の違いは?
給与の支払い方法が日払い・週払い・月払いのいずれであっても、源泉徴収の義務は変わりませんが、計算方法には違いがあります。
日払いの場合は、支払うたびにその都度日額に基づいて源泉徴収額を計算しなければなりません。給与を渡すたびに税額表を参照し、適用される税率で差し引く必要があります。
一方、週払いや月払いの場合は、一定期間分の合計給与額に対して一括で源泉徴収を行います。たとえば1週間分の給与をまとめて支払う際は、その合計額を基に税額を計算します。
また、電子マネーや銀行振込で給与を支払う場合も、現金払いと同様に源泉徴収を行う必要があります。給与支払いの手段が変わっても、税務処理の義務は免除されません。
電子マネーでの支払い時には、給与明細書に源泉徴収額を明記し、所得税として正確に納付する体制を整えることが重要です。
源泉徴収を怠った場合どうなる?
日雇い労働者に対して源泉徴収を行わなかった場合、雇用主にはさまざまなリスクが発生します。まず考えられるのが、税務調査による指摘と追徴課税です。
源泉徴収漏れが発覚すると、本来支払うべき税額に加えて、延滞税や加算税が課されます。特に、故意に納税義務を怠ったと見なされれば、重加算税という厳しい処分が科されることもあります。
また、源泉徴収税は法定納期限までに納付しなければなりません。期限を過ぎた場合、翌日から納付までの日数に応じて延滞税が発生します。
一方で、源泉徴収額を誤って多く納付していた場合でも、税務署から指摘されることはほとんどありません。
雇用主自身が気づき、所定の手続きを行わなければ過剰納付分の還付は受けられない点も押さえておきたいポイントです。
「アルバイト採用を始めたい」「アルバイト採用をしているが、今の方法が正しいか不安」とお考えの方は少なくありません。
レポートでは、「アルバイトとパートの違い」「採用までの流れ」「採用手法」の他、「アルバイト採用コストを下げる方法」などをまとめています。アルバイト採用にお困りの方はぜひご活用ください。
まとめ
日雇い労働者への源泉徴収は、一般的な雇用とは異なるルールがあるため、正しい知識と対応が求められます。特に計算や書類の発行を誤ると、ペナルティが課されたり、企業としての信頼性の低下につながるおそれもあります。
迷ったときや判断に不安があるときは、税理士など専門家のサポートを受けるのもひとつの方法です。
本記事の内容で事前に制度を理解しておくことで、トラブルを避け、安心して単発・日雇いバイトを雇用できる環境を整えましょう。
※令和7年度(2025年度)の税制改正により、所得税の基礎控除の見直し等が行われました。
国税庁「令和7年度税制改正による所得税の基礎控除の見直し等について」https://www.nta.go.jp/users/gensen/2025kiso/index.htm