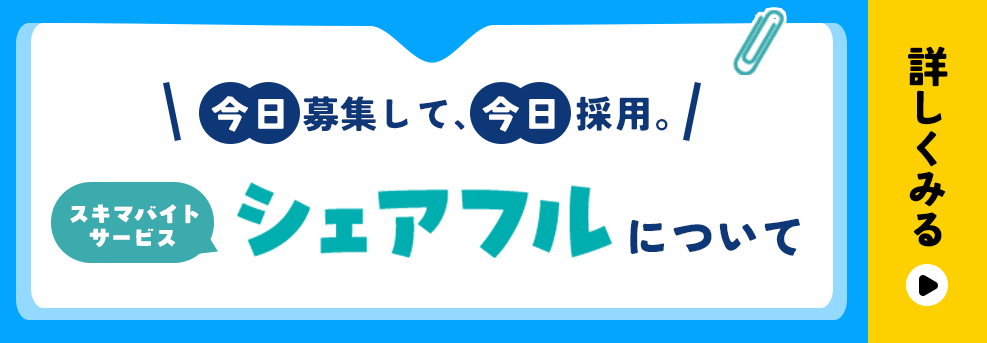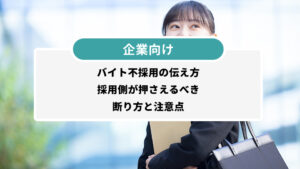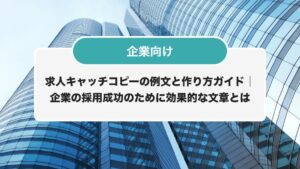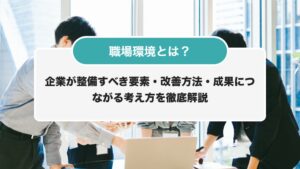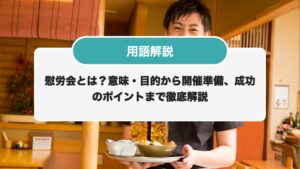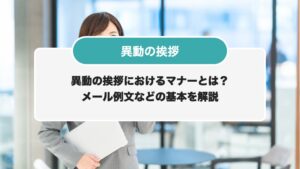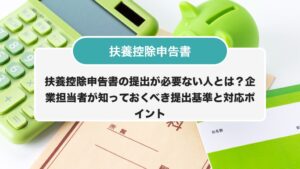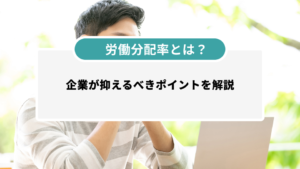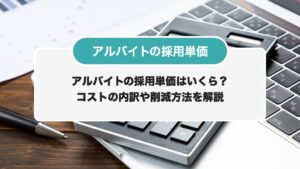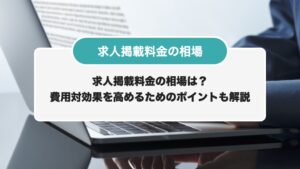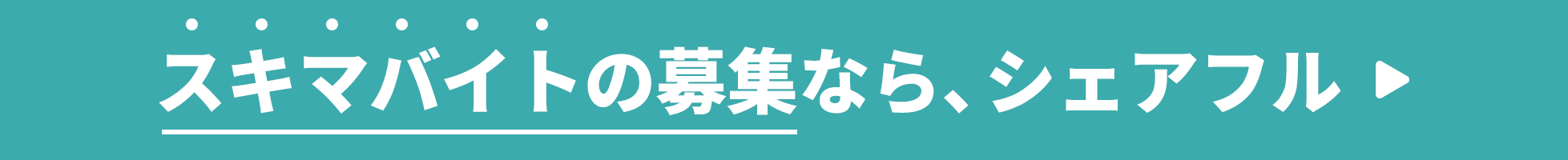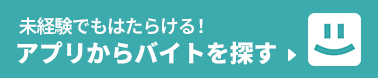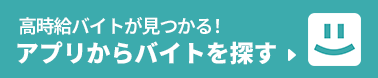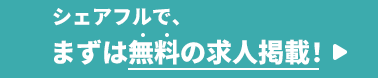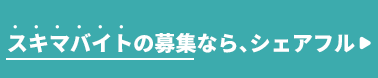バイトに試用期間を設けたほうがよい?メリットや注意点を解説
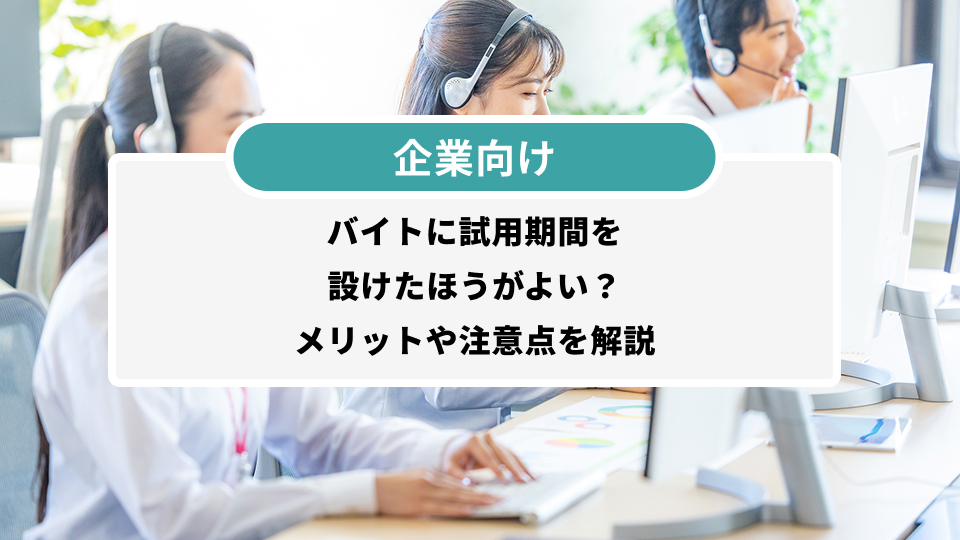
「採用してもすぐ辞められる」「人柄や仕事ぶりが合わない」など、アルバイトの採用後に起きるこうしたミスマッチを減らすため、試用期間を導入している企業も少なくありません。ただし、試用期間の法的な取り扱いや注意点を正しく理解しておかないと、思わぬトラブルに発展する恐れがあります。
本記事では、バイトの試用期間に関する基礎知識から、制度を設けるメリットや注意点まで、企業側が押さえておきたいポイントを分かりやすく解説します。
試用期間中の給与や労働条件、解雇のルールについても触れていきますので、制度の導入を検討している企業担当者はぜひ参考にしてください。
バイトの試用期間について
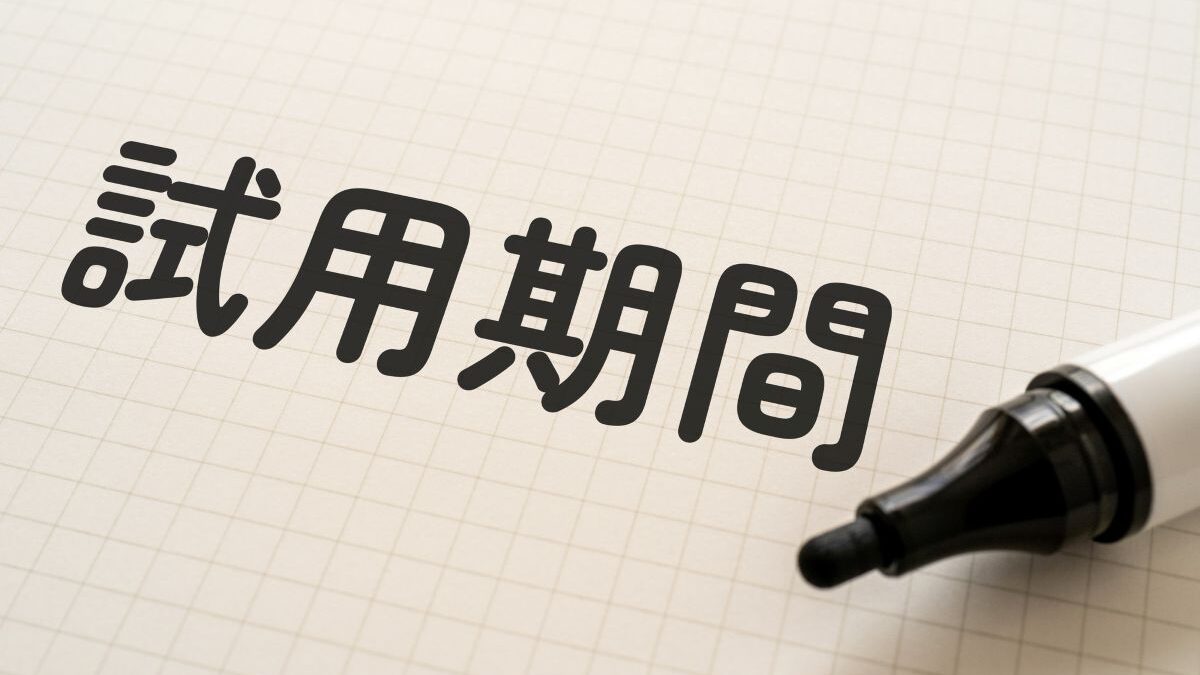
バイトにも試用期間を設ける企業は少なくありませんが、制度としての理解があいまいなまま運用されていることもあります。
ここではまず、「試用期間とは何か」について基本的な考え方を整理したうえで、正社員との違いや法的な位置づけについて詳しく見ていきましょう。
試用期間とは
試用期間とは、採用した労働者が自社の業務に適しているかどうかを見極めるために設けることができる期間です。
企業は採用時に履歴書や面接を通じて応募者の能力や人柄を判断しますが、限られた時間の中では本当の適性まで見抜くのは困難です。実際、採用時点では問題なく思えても、実際に働き始めてからギャップが生じるケースは少なくありません。
そこで、実際の勤務を通して仕事ぶりや職場との相性を確認し、「本採用に進めるかどうか」を改めて判断するのが試用期間の目的です。
なお、試用期間中であっても労働契約はすでに成立しており、労働者としての基本的な権利は守られます。そのため「お試し期間」のような軽い扱いではなく、法的な意味を含んだ正式な雇用関係のもとで運用する必要があります。
試用期間に関する明確な規定はない
労働基準法などの法律には、「試用期間」という言葉の定義や運用ルールが明確に定められているわけではありません。そのため、バイトに試用期間を設けるかどうか、またその期間をどの程度にするかは、企業の判断に委ねられています。ただし、注意しなければならないのが、法的にはすでに労働契約が成立している状態として扱われるということ。試用期間中だからといって一方的な解雇や不当な待遇が許されるわけではなく、通常の労働契約と同様の責任が発生します。
期間については、一般的には3カ月から6カ月程度を設定している企業が多いものの、中には1カ月のみとするケースや、1年近く試用期間を設けている企業も存在します。
試用期間は解約権留保付労働契約にあたる
試用期間は、法的には「解約権留保付労働契約」として扱われます。これは、労働契約を締結しつつも、企業側が一定期間内に労働者の適性を見極めたうえで、契約を継続するかどうかを最終判断できるという性質を持つものです。
ただし、これにより自由に解雇できるわけではなく、解雇にあたっては客観的に合理的な理由と社会通念上の相当性が求められます。試用期間中とはいえ、解雇のハードルが低くなるわけではない点には注意が必要です。
バイトと正社員で試用期間に違いはない
試用期間に関する法律上の取り扱いは、正社員かアルバイトかを問わず基本的に同じです。雇用形態にかかわらず、労働契約が成立している以上、労働者には権利があり、企業には義務が生じます。
そのため、アルバイトであっても試用期間中の解雇には合理的な理由が必要ですし、労働条件や待遇についても不当な差別は許されません。試用期間の目的は、あくまでも採用した労働者の能力や適性を確認すること。この点において、アルバイトと正社員の間に本質的な違いはないといえるでしょう。
ただし、試用期間の設定や運用に関しては、企業の裁量に委ねられており、アルバイトと正社員で異なる試用期間を設けることも可能です。
バイトに試用期間を設けるメリット

アルバイトの採用では、履歴書や面接だけで応募者のすべてを把握するのは難しく、実際に働いてもらわなければ分からない部分も多々あります。そこで有効なのが「試用期間」を設けることです。
ここでは、試用期間を設けることによって得られる企業側のメリットを、4つの視点から見ていきましょう。
労働条件を守れるか確認できる
試用期間を設けるメリットのひとつは、応募者が労働条件や職場ルールをしっかり守って働けるかを、実際の勤務を通じて確認できる点です。例えば、出勤時間やシフトをきちんと守っているか、急な欠勤や遅刻がないか、服装や言葉遣いなど基本的なルールを理解して行動できているかなどは、現場に入ってみないと分からないものです。
面接では「大丈夫です」と答えていたとしても、実際に勤務が始まってみると、時間にルーズだったり、連絡なしで欠勤したりといったケースも少なくありません。こうしたルール遵守の姿勢は、職場の信頼関係やチームワークに直結するため、採用後のトラブル防止の意味でも早い段階でのチェックが欠かせません。
人間性を確認できる
仕事のスキルと同じくらい、あるいはそれ以上に重要なのが「人間性」です。試用期間を設けることで、先輩や上司への接し方、チーム内での立ち居振る舞い、職場の雰囲気へのなじみ具合など、実際にはたらく中でしか見えない“人となり”を確認することができます。
「採用の段階では良い印象だったのに、入ってみると態度がまるで違った」ということもあるため、こうした点を確認できるというのは、試用期間を設ける大きなメリットといえるでしょう。
業務内容に合っているか確認できる
どれだけやる気があっても、業務に適性を持っているかどうかは、実際に働いてみないと分かりません。一見問題なさそうに見える応募者でも、実際に業務にあたってもらうと「思っていたよりも手順が覚えられない」「作業スピードが極端に遅い」「体力的に厳しそう」など、現場との相性にズレが生じることもあります。
試用期間を設ければ、そうした適性の有無を実務を通じて確認することができ、ミスマッチによる早期離職を防ぐことにもつながります。アルバイト本人にとっても、「自分に合った仕事なのか」を確かめられる機会になりますので、採用する側・される側の双方にとってメリットといえます。
本採用の際の課題を確認できる
試用期間中に勤務態度や業務スキルを観察することで、「この人を本採用するなら、今後ここを強化すべきだな」といった課題や育成ポイントが見えてきます。
例えば「接客態度は申し分ないけれど、レジ操作に不安がある」「丁寧に仕事をするが、やや報告・連絡・相談が少ない」など、具体的な改善点が見えてくることで、本採用後の教育やサポートの方向性が明確になります。本採用後に「期待外れだった」と感じる事態を避けるためにも、あらかじめ必要なサポートを明確にしておくことで、早期戦力化にもつながるでしょう。
バイトの試用期間で定めるべき条件や給与

では、実際にアルバイトの試用期間を導入するとなった場合、企業側はどのような点を事前に決めておくべきなのでしょうか。この部分が曖昧なまま運用すると、後々トラブルにつながる可能性もあるため注意が必要です。
ここからは、試用期間を設ける際に押さえておきたい基本的な条件や給与面について、順を追って解説していきます。
試用期間の設定
試用期間を導入する際には、その期間や評価の基準を事前に明確にしておくことが大切です。雇用契約書や労働条件通知書には「試用期間あり」と明記し、開始日・終了日・期間の長さを具体的に記載しましょう。
一般的には6カ月以内で設定されることが多いですが、法的な上限は設けられていません。とはいえ、過度に長い試用期間はトラブルの元になりやすく、実際に民法第90条の公序良俗違反にあたり無効とされた判例もあります。試用期間中は労働者が不安定な立場に置かれるため、業務適性などを見極めるために「必要かつ合理的な範囲内」に収めることが求められます。
試用期間の延長について
試用期間中に病気やケガで出勤日数が少なかったり、指導を重ねても勤務態度が改善されなかったりする場合、当初の試用期間内では適性の判断が難しいこともあります。こうしたケースでは、試用期間を延長することが可能です。
ただし、無条件に延長できるわけではなく、次の3つの要件すべてを満たす必要があります。
- 就業規則や雇用契約書に延長の可能性が明記されていること(判例:東京地方裁判所決定昭和63年12月5日・サッスーン東京事務所解雇事件)
- 延長に合理的な理由があること(判例:長野地裁諏訪支判昭和48年5月31日・上原製作所事件)
- 延長期間が社会通念上妥当な範囲内であること(判例:東京地判平成12年3月22日・中田建材事件)
合理的な理由というのは、例えば「無断欠勤が多い」「経歴詐称が発覚した」「病気などにより勤務日数が少ない」などが挙げられます。逆に、「業務の習得が遅い」「ミスが多い」といった理由は、試用期間中であれば想定内と判断され、合理的な理由として認められないケースがほとんどでしょう。
アルバイトの試用期間において、延長の可能性がある場合には、雇用契約書や労働条件通知書にその旨を明記し、事前に説明しておくことが大切です。
試用期間の給料
試用期間中のアルバイトであっても、企業には当然、賃金を支払う義務があります。「試用期間中だから」といって無給にしたり、著しく低い時給を設定したりすることは許されません。
給与額は企業側の裁量で決めることができますが、最低賃金を下回ってはならないというルールは、本採用時と同様に適用されます。例えば、最低賃金が1,100円の地域で「試用期間中は1,100円、本採用後は1,200円」という設定であれば問題はありません。一方で、本採用時の時給がすでに最低賃金の場合は、試用期間中でも給与を下げることはできないため注意が必要です。
また、残業や深夜労働が発生した場合には、法定通りの割増賃金を支払う必要があります。 試用期間中かどうかに関係なく、労働基準法に基づく賃金ルールは一貫して守らなければなりません。
試用期間中も保険は加入が必要
試用期間中であっても、一定の条件を満たすアルバイトには社会保険の加入義務が発生します。「試用期間が終わってから加入すればよい」と考える企業もいますが、これは誤解です。
具体的には、週の所定労働時間が正社員の4分の3以上(75%以上)である場合は、試用期間中であっても健康保険や厚生年金に加入しなければなりません。雇用保険についても、31日以上の雇用見込みがある場合は原則として初日から適用されます。
「試用期間だから」という理由で加入を免れる・先延ばしにすることはできないため、早めに適切な手続きを行いましょう。
バイトの試用期間に関する注意点

ここまでで、アルバイトに試用期間を設けるメリットや基本的なルールは理解できたかと思います。では、実際に運用する際には、どのような点に気をつければよいのでしょうか。
ここからは、企業側が押さえておきたい4つの注意点について、詳しく解説していきます。
雇用条件に期間を明記する
試用期間を設ける場合は、その有無や期間を労働者にしっかり伝えることが重要です。曖昧なままにしてしまうと、「そんな説明は受けていない」といった認識のズレが生じ、後のトラブルにつながりかねません。
雇用契約書や労働条件通知書には、「試用期間あり」と明記し、期間の長さや開始日・終了日を具体的に記載しておきましょう。また、試用期間中の労働条件(給与・勤務時間・待遇など)が本採用後と異なる場合には、その違いもはっきりと示す必要があります。
不当に給与を低くしない
試用期間中のアルバイトに対する給与設定は、企業の裁量で本採用時より低く設定することも可能です。しかし、その際には各都道府県で定められた最低賃金を下回らないよう注意が必要です。最低賃金を下回る給与設定は、試用期間中であっても法律違反となります。
また、試用期間中の労働内容が本採用時と同等であるにもかかわらず、給与差を設けた場合、同一労働同一賃金の原則に基づき不適切と判断される可能性があります。
給与面での不信感は離職の原因にもなりかねません。適正かつ納得のいく給与設定を心がけましょう。
合理性の無い解雇は無効になる
試用期間中の労働契約は、解約権留保付労働契約と解され、企業は労働者の適性や能力を見極めるための解約権を留保しています。しかし、この解約権の行使は無制限に認められているわけではありません。
入社日から14日以内は解雇予告は不要
労働基準法第21条では、試用期間の開始から14日以内であれば、解雇予告や解雇予告手当が不要と定められています。つまり、勤務初日から2週間以内であれば、即日解雇しても法律上のペナルティは発生しません。
とはいえ、何の説明もなく突然解雇するような対応は、信頼関係を損ない、後々の火種にもなりかねません。また、あくまで解雇予告や解雇予告手当が不要ということに過ぎず、「解雇しやすい」という意味ではない点にも注意が必要です。入社日から14日以内の解雇も、他の場面と同様、客観的に合理的な理由が必要となります。
14日以降は解雇予告が必要
入社から14日を過ぎると、たとえ試用期間中であっても労働基準法上の「解雇予告制度」が適用されます。これにより、使用者は30日前に解雇予告を行うか、または30日分以上の平均賃金を支払う「解雇予告手当」が必要になります。これは正社員・アルバイトを問わず、すべての労働者に共通して適用されるルールです。
「試用期間だから」という理由で、手続きなしに突然解雇することは認められていません。不当な解雇としてトラブルにつながるリスクもあるため、14日を超えるタイミングでの解雇については、法的義務と適切な対応をしっかり理解しておく必要があります。
試用期間も有給休暇は発生する
試用期間中であっても、有給休暇の発生条件は通常と変わりません。労働基準法では、「雇い入れ日から6か月間継続勤務し、その間の出勤率が8割以上」であれば、年次有給休暇が10日間付与されると定められています。
この「雇入れ日」は試用期間開始日を指すため、試用期間中も有給休暇の取得要件を満たす期間としてカウントされます。したがって、試用期間中のアルバイトにも、条件を満たした場合には適切に有給休暇を与えなければなりません。
まとめ

本記事では、アルバイトに試用期間を設ける際の基本的な考え方から、実務で押さえておきたい注意点までを解説してきました。
試用期間は、企業側がアルバイトの適性や勤務態度を見極める期間であると同時に、はたらく側にとっても職場環境や仕事内容が自分に合っているかを見極める期間になります。双方が納得のうえで本採用に進むことで、早期離職やミスマッチのリスクを抑えることができるでしょう。
なお、試用期間中であっても雇用契約は成立しているため、本採用を見送る際には法的な配慮も欠かせません。適切に制度を運用し、安定した人材確保につなげていきましょう。