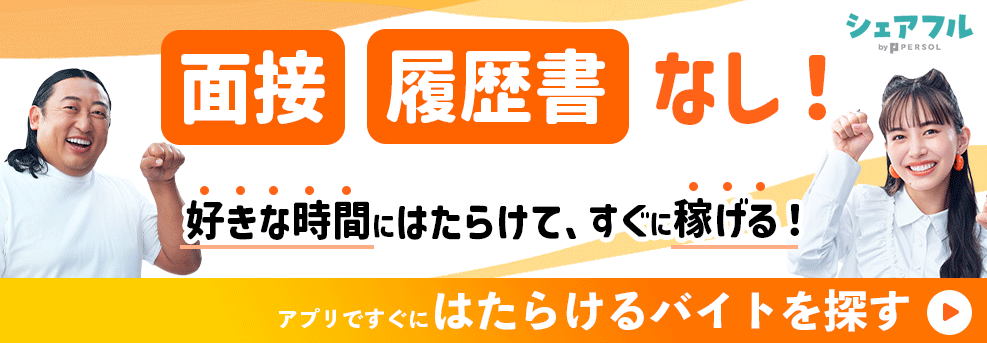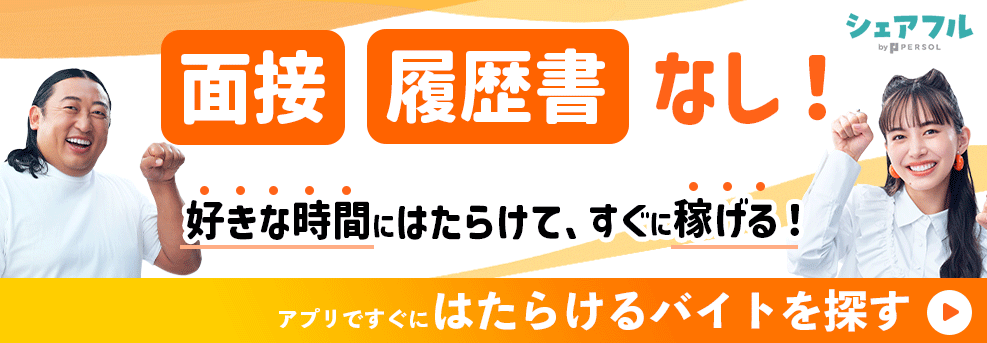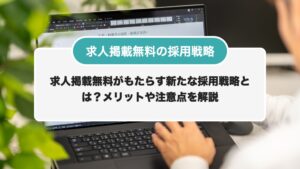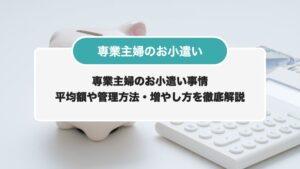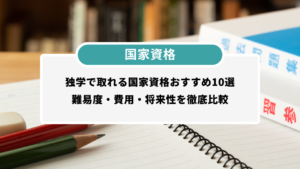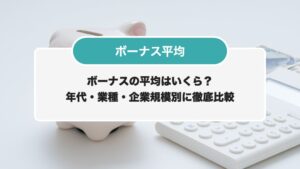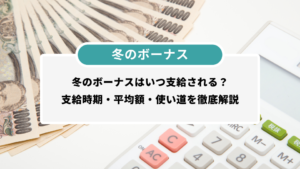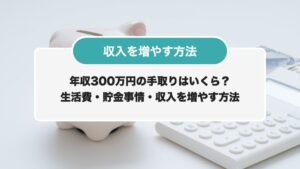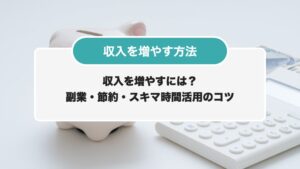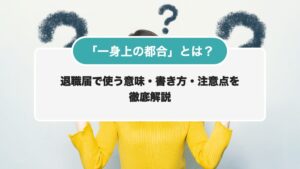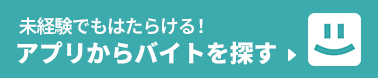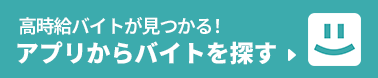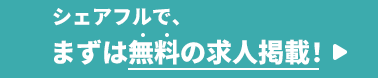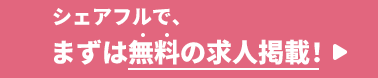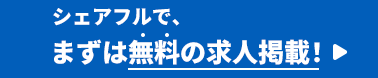【早見表付き!】「満何歳」とは?意味・正しい使い方・年齢の数え方をわかりやすく解説
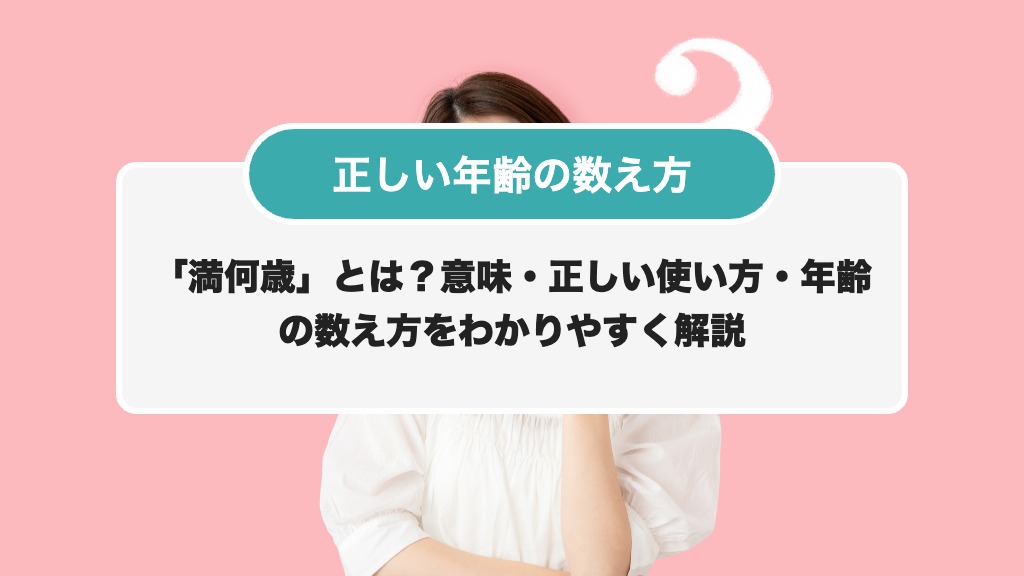
履歴書や申請書で出てくる「満何歳」。ふだん友だち同士では「何歳?」と聞きますが、正式な書類だと「満何歳」が指定されることが多く、誕生日が来る前後で何歳と書くべきか迷う人も多いはず。
この記事では、「満何歳」の意味・“数え年”との違い・法律上の扱い(※重要:年齢は誕生日“前日”に加算)・計算方法・履歴書での正しい書き方まで、整理します。最後に西暦/和暦/年齢の早見表も用意。この記事ひとつで迷いがゼロになります。
「満何歳」の意味とは?

「満」とは何を意味するのか
「満」は「誕生日を基準に、そこから“満ちた”年数」という意味です。たとえば2000年4月1日生まれの人は、その年の“誕生日の前日が終わった時点”で25年が満ち、法的に25歳になります(※“当日”ではなく“前日満了”に注意)。日常会話では「誕生日になったら◯歳」と言うこともありますが、制度や手続きでは前日ルールで判断されます。
「満何歳」と「数え年」との違い
- 満年齢(満何歳)…誕生日を基準に、前日満了で年齢が増える現行の数え方。
- 数え年…生まれた瞬間を1歳とし、元日(1/1)に全員が一斉に+1歳する昔の数え方。
現在の公的手続き・契約・資格要件などは満年齢で統一されています。伝統行事(厄年など)では今も「数え年」が使われる場面がありますが、地域や寺社の運用で異なるため、指示に合わせましょう。
履歴書・申請書などで「満何歳」と書かれる理由
年齢は契約や資格の適用条件に直結する重要情報です。そのため法律に基づく満年齢を用いるのが原則。履歴書の年齢欄は、指定された基準日(記入日/提出日/所定日)現在の満年齢で記入します。”指示がない場合は「記入日現在」”で問題ありません。
「満年齢」と「数え年」の違い

満年齢(誕生日を迎えた時点で加算する考え方)
わかりやすく言うと「誕生日が来たら年をとる」ですが、法的には“前日が終わった瞬間”に加算されます。根拠は以下の二本柱です。
数え年(生まれた年を1歳とする昔の数え方)
数え年は「生まれた瞬間に1歳」「毎年1/1に全員+1歳」というシンプルな仕組み。かつてはお正月に一斉に年を取る文化が背景にありました。現在は公的な基準ではないものの、厄年・七五三などで慣習的に使われることがあります。
現在はどちらが使われているのか(公的書類・ビジネスでのルール)
日本では**「年齢のとなえ方に関する法律」(昭和24年法律第96号)により、公的には満年齢が採用されています。公布は1949年**、施行は1950年1月1日。履歴書・契約書・試験要項など、制度に関わる年齢は満年齢で統一されています。
「満何歳」の計算方法

誕生日ベースの計算ルール
- 生年月日を基準にする
- 今年の誕生日を迎えたかで分岐
- 迎えた(=前日満了を経過)→ 生年からの差がその年齢
- 迎えていない → 上の年齢から**−1**
「誕生日の“当日”では?」と迷ったら、**厳密には“前日満了”**と覚えておくと、申請や資格条件での取り違えを防げます。
計算例
例1:2000年4月1日生まれの場合
- 2025年3月31日までは満24歳
- 2025年4月1日の“前日満了(3/31のおわり)”で満25歳
日常会話では「4/1に25歳」と言っても差し支えない場面は多いものの、制度の線引きは前日で行われます。
例2:1995年12月31日生まれの場合
- 2025年12月30日までは満29歳
- 2025年12月31日の“前日満了(12/30の24時)”で満30歳
年末またぎはミスが出やすいので、誕生日前の提出物は特に注意しましょう。
履歴書・申込書で記入する際の注意点
- 記入日現在の満年齢を書く(誕生日が近くても見込みで増やさない)
- 西暦/和暦はどちらかに統一(指定があれば指示に従う)
- 年齢要件のある応募や試験では、前日満了が判定に効くケースがある(例:学齢・年金の起算月など)
- 迷ったら要項・募集要領を必ず再確認する
履歴書の一般的なガイドでも満年齢で記入が明記されています。
「満何歳早見表」で簡単に確認

西暦・和暦から年齢を確認する早見表
前提:2025年の“その人の誕生日を迎えた後”の満年齢
※提出日が誕生日前なら「−1歳」(法的には前日満了)。
| 西暦 | 和暦 | 満年齢(2025年に誕生日を迎えた後) |
| 2005年 | 平成17年 | 20歳 |
| 2000年 | 平成12年 | 25歳 |
| 1998年 | 平成10年 | 27歳 |
| 1997年 | 平成9年 | 28歳 |
| 1996年 | 平成8年 | 29歳 |
| 1995年 | 平成7年 | 30歳 |
| 1994年 | 平成6年 | 31歳 |
| 1993年 | 平成5年 | 32歳 |
| 1992年 | 平成4年 | 33歳 |
| 1991年 | 平成3年 | 34歳 |
| 1990年 | 平成2年 | 35歳 |
| 1989年 | 昭和64年(1/1~1/7)/平成元年(1/8~) | 36歳 |
| 1988年 | 昭和63年 | 37歳 |
| 1985年 | 昭和60年 | 40歳 |
| 1980年 | 昭和55年 | 45歳 |
| 1975年 | 昭和50年 | 50歳 |
| 1970年 | 昭和45年 | 55歳 |
| 1965年 | 昭和40年 | 60歳 |
| 1960年 | 昭和35年 | 65歳 |
記入間違いを防ぐための使い方
- 締切日≒記入日のイメージで、「その日の時点の満年齢」を確認
- 年度末・年末・誕生日前後は誤記が増えるゾーン:早見表+電卓でダブルチェック
- 年齢要件がある募集は、募集要項の「◯歳以上/以下(満◯歳)」の表現を正確に読む(「以上/未満」で結果が逆転することも)
ネットで使える「年齢計算ツール」の紹介
オンライン上には、生年月日を入れるだけで「今日時点の満年齢」や「次の誕生日までの日数」を自動計算してくれる無料ツールが多数あります。試験申込・保険・ローンなど数え間違いが許されない場面では、こうしたツールと前日満了の理解をセットで使うと安心です。根拠ルール自体は上記の民法143条2項に基づいてブレません。
履歴書・申込書での「満何歳」の正しい書き方

履歴書に年齢を記載する際の基本ルール
- 記入日現在の満年齢を書く
- 見込みで加算しない(誕生日前は−1歳)
- 他情報(生年月日・和暦/西暦)と整合しているか最終チェック
- 企業のテンプレやフォームに**「満何歳」**と明記があれば、その指示に合わせる
記入例(満〇歳)と間違いやすいパターン
正しい書き方:
- 「2025年3月20日現在 満29歳(1995年12月31日生)」
よくあるミス:
- 誕生日前なのに翌年齢で記入
- 西暦と和暦が混在
- 応募要項が「満◯歳以上」なのに、“◯歳以上(数え)”と誤解
- 「満」の有無は要項に合わせる(企業側の指定がないなら、“満”ありが丁寧)
バイト・就職活動・資格試験申込での注意点
- 募集・受験資格の年齢基準日(例:募集締切日現在/試験実施日現在など)を確認
- 前日満了の扱いが合否や受験可否に影響することがある
- Web入力フォームでは自動計算される場合でも、自己申告欄は自分で整合をとる
- 迷ったら要項の問い合わせ窓口に確認(エビデンスが残るメール推奨)
- 厄年など伝統行事の“年齢”は実務と基準が異なるため、混同しない(実務=満年齢)
「満何歳」に関するよくある質問

「満何歳」と「何歳」の違いは?
日常の「何歳?」は多くの場合満年齢の感覚で使われています。ただし制度や手続きの場では厳密に**満年齢(前日満了)**で判定される点に注意しましょう。
「満何歳」と「満年齢」は同じ意味?
実務的には同義です。「満何歳」は**“あなたはいま満いくつ?”という表現で、「満年齢」は制度上の呼び方。どちらも誕生日基準(前日満了)**で増える年齢を指します。
履歴書に「満」を書かずに「〇歳」だけではダメ?
企業の多くは実質満年齢を想定しているため「◯歳」だけでも通るケースはありますが、要項に「満何歳」と書かれている場合は必ず合わせるのが安全。フォームやテンプレがある場合はそれに従ってください。
和暦(昭和・平成・令和)との併記が必要な場合は?
指定があるときは和暦・西暦を正確に併記しましょう。令和の年数があやふやなときは、社内既定の換算表やこちらの記事が便利です:
👉 「今は令和何年?」早見記事(内部リンク):https://sharefull.com/content/entertainment/21036/
まとめ
- 「満何歳」は**誕生日基準で増える年齢(満年齢)**を尋ねる表現。
- 法律的には**“前日満了”で年齢が加算**されます(年齢計算ニ関スル法律×民法143条2項)。
- 履歴書や申請書は記入日現在の満年齢で記入。誕生日前の“見込み加算”はNG。
- 迷ったら早見表+前日満了の理解でダブルチェック。要件が絡む場面では**募集要項の表記(満◯歳/以上・未満/基準日)**まで読み込むと安心。
- 伝統行事の数え年と実務の満年齢は別物。混同しないのがトラブル回避のコツ。
これで「満何歳」のモヤモヤは解消できるはず。履歴書や申請の前に、本記事をブックマークしておくと年齢まわりのミスをぐっと減らせます。